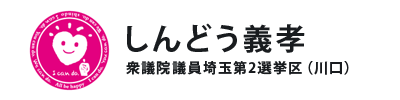憲法審査会の海外調査、最後となる4ヶ国目はエストニアです。
ロシアと国境を接し、人口約132万人(青森県と同じ)、面積は九州とほぼ同じながら、バルト三国のトップランナーとして旧ソ連から完全な欧州の一員への移行を目指し、2004年NATO,EU 加盟、他の二国に先行して2010年にOECD 加盟、2011年にユーロ導入(旧ソ連圏初)を成し遂げました。

経済自由度ランキング欧州3位、世界第7位を誇り、IT ・サイバー防衛の先進国であり、「e-エストニア」と呼ばれるデジタル先端国家を形成しています。

一方で、ロシアとの苦闘の歴史を持ち、ロシアとの国境画定は未だに国会手続きが停止中であり、ロシアへのエネルギー依存度を順次減らしています。
対露警戒心が強く、ウクライナ危機を受けたEUの対露経済制裁継続を主張しています。

エストニア共和国憲法は1992年に制定され、全168条で構成されています。
特徴としては、第一次世界大戦後に一度独立を果たすものの、再びソ連に占領されるという経緯を踏まえ、民族的帰属意識を保持する権利やエストニア語を公用語とする規定など民族に関する規定が多いことです。

こうしたソ連占領前からの国民の継続性を重視する政策を取り、1938年憲法下でエストニア国民であった人とその子孫のみが「国民」とされ、1992年に実施された国民投票の投票権もその範囲に限られました。つまり、ソ連占領時代に移住してきた人は居住権はあっても未だ国民とみなされず、国政選挙と国民投票の投票権は与えられていないということでした。(地方議会選挙は全住民が投票可能、)
また、リトアニアでは絶対に必要と言われた憲法裁判所を設置せず、最高裁判所の一部門である憲法審査部が法律その他の合憲性を審査しています。
①戦前のエストニアでも上訴を受け付ける裁判所が憲法の違憲審査を担っていたという歴史的背景。
②憲法裁判所が議会を規制する機関になることが危惧されているという政治的背景。
という興味深い指摘がなされています。

憲法改正は5回行われていますが、EU加盟やエストニア語の保護を前文に明記することなど、安定国家を建設する途上の意味合いが強いものとなっています。
私たちは、まずは連立与党を形成する3政党の代表議員と面談したのち、法務省において公法担当課長など意見交換とを行い、最近改正された地方議会選挙での選挙権が18歳から16歳にさげられたこと、インターネット投票導入後の課題、国民投票を実施する際の有料広告規制のあり方などについて意見交換を行いました。
私からエストニアにおける憲法改正の必要性についての考え方を質問したところ、憲法には明確性が必要であり、時代の変化や必要に応じ憲法改正を行うのは必然と考える、との明確な答えがありました。
その後は、教育科学省電子サービス局次長や、経済省国家サイバーセキュリティー政策課長などと、e -エストニア政策における教育のスマート化、ICT教育戦略についての現状、エストニアが世界に誇るeIDカードシステムとセキュリティ政策について、極めて興味深い意見交換を行いました。