3月28日の埼玉高速鉄道線(地下鉄七号線 浦和大門?東川口?鳩ヶ谷?元郷?赤羽岩淵?都内営団地下鉄・南北線に接続)の開通を控え、これを記念して、「戸塚ふれあい祭り」(実行委員長 藤波・戸塚地区連合町会長)が3月4日盛大に開催された。
 当日は、戸塚公民館から式典の会場である榎戸公園まで、3台のオープンカーとそれに追走する十数台のハーレーによるパレードが行われた。
当日は、戸塚公民館から式典の会場である榎戸公園まで、3台のオープンカーとそれに追走する十数台のハーレーによるパレードが行われた。
小雨の降る中、新藤代議士も岡村市長や豊田・宍倉両地元市議らと共にオープンカーに乗り、約30分間、沿道から見送る人たちににこやかに手を振っていた。
式典で新藤代議士は「永年の地域の悲願であり、期成同盟会を始め多くの関係者の粘り強い運動が遂に実りました。交通過疎地といわれていた地域が都心と直結
する事になります。便利になる反面、都心への求心力が強まります。沿線の魅力ある都市整備をさらに急がねばなりません。わが街の熱意を国へ責任を持って伝
えます。」と力強く挨拶した。
投稿者「shindo-office」のアーカイブ
2001.02.28 中国共産党内外連絡部とのセッション
2月27日、馬俊威中国現代国際問題研究所長ら中国共産党の経済、ODA、台湾問題など若手実務専門家十人がこのほど、二日間の日程で来日、新藤義孝衆院
議員(2区=川口市など)ら自民党の若手国会議員六人と活発な意見交換を行った。この意見交換会は昨年、中国で初めて行われ、今回日本側が招待した。
初日は午前九時から午後五時まで、東京・平河町の都道府県会館を会場に、経済や歴史認識、靖国神社、台湾、ODAなど双方の国に認識の温度差がある問題をテーマに徹底的にフリートーク、両国の認識の食い違いを明らかにした。
新藤議員によると、「例えば靖国神社問題では中国側は軍国主義の権化と主張して、その歴史を真っ向から否定したが、それに対し、日本側は祖先、戦死者の霊を悼み、敬うのだ説明、論戦は平行線をたどった」という。
しかし、中国側「ここまで素直に日本人と議論を交わしたのははじめて」とさっぱりとした表情で評価した。新藤議員も「違いを明らかにして、それを認め合うのも外交の一つ」と話し次回の来年は北京で開催する。
一行は話し合いの後、新藤議員の提案で近くのボーリングセンターへ足を伸ばし、ボウリングを楽しんで懇親を深めた。翌日、自民党本部の古賀幹事長、野中前幹事長を表敬訪問した後、帰国した。
2001.02.05 第9回日独フォーラムに出席(開催地・ベルリン)
|
今回は5つの議題に関して両国の担当委員からそれぞれ発言がそれぞれ発言があった後、ディスカッションを行った。 |
2001.01.31 カブリサス、キューバ国際経済関係担当大臣来日
1月24日に12日間のメキシコ・キューバ公式訪問から帰国した新藤代議士だが、 1週間後の30日午前にはキューバからカブリサス国際経済関係担当大臣が来日し、衆議院 議長公邸で綿貫議長らとともに、同大臣一行をお迎えした。
会談の中でカブリサス大臣は「今回の来日は、永らく中断していた日本・キューバ経済会議の再開の為であり、綿貫議長のご尽力に感謝する。また、新藤代議士を始め観光振興議員連盟のみなさんには、今後の協力を依頼したい。」と語った。
会談後、一行は経済産業省において平沼大臣等政府要人と協議を開始した。
新藤代議士は「カブリサス大臣は元在日キューバ大使であり、今後の両国関係のキーマンとなる人物である。キューバ訪問の際も親しく会議や会食を共にした
が、外交におけるコミュニケーションの大切さを痛感している。訪問の成果が早速現れた。」と嬉しそうに語った。
2001.01.14?24 新藤代議士、メキシコ・キューバを公式訪問
1月14日から24日までの11日間の日程で、綿貫衆議院議長に随行し、メキシコ・キューバを公式訪問した。
 新
新
藤代議士は、党青年局国際部長を務めており、エトロフ島視察、南アフリカで開催されたIPU会議(世界国会議員会議)や国連招待によるニューヨーク訪問三
度に亘るコソボ支援、トルコ地震救援活動など国際派議員として活躍しており、今回の同行は、その経験を認めた綿貫議長から直接指名を頂いたもの。
 メ
メ
キシコでは、カントゥ下院議長代行やエチェベーリア元大統領との会談を行い、その後のフォックス大統領との会談では、今後の日墨自由貿易協定についての意
見交換を行った。また、日本メキシコ学院や日墨会館を訪問し、大使公邸で催された夕食会では、在留邦人や日系の方々と懇談を行った。
 キューバでは、カストロ議長をはじめ、アラルコン全国議会議長、ラヘ国家評議会副議長やペレス外務大臣ら政府・党要人と会談し、二国間における諸問題を話し合うとともに、日本・キューバ観光振興議員連盟の設立に合意し、同事務局長に就任した。
キューバでは、カストロ議長をはじめ、アラルコン全国議会議長、ラヘ国家評議会副議長やペレス外務大臣ら政府・党要人と会談し、二国間における諸問題を話し合うとともに、日本・キューバ観光振興議員連盟の設立に合意し、同事務局長に就任した。
新藤代議士は、議長に随行しての公式訪問について、「両国とも国家元首級の歓迎を受け、非常に過密なスケジュールではあったが、メキシコは41年ぶりの政
権交代直後の初交渉、キューバとは新たな外交展開のきっかけを作ることが出来、中身の濃い訪問であった。よい経験をした。今後も顔の見える国際貢献活動を
続けていきたい」と時差ぼけにもめげず抱負を語った。
日本国憲法に関する件(質疑) 衆議院憲法調査会-4号 2000年11月09日
日本国憲法に関する件
150-衆-憲法調査会-4号 平成12年11月09日
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
佐々木参考人には、大変意義ある、そしてまた興味深いお話を賜りまして、心から感謝を申し上げたいと存じます。そして、きょうお話しいただいた、佐々木先生の今のお話をもとに、また私なりに、高名な政治学者でいらっしゃいます先生に御質問をさせていただきたい、このように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
私は、最初にお断り申し上げておきますが、ごらんのように三十三年生まれで、世代的にはこの中で最も若い方の部類です。先ほど先生がお話しされました、憲法に対する考え方、また国家に対する考え方が国民の中でいろいろ変わっているようだというお話がございました。ですから、多分その変わっている方の部類に入ると思いますので、少しぶしつけになるかもしれませんが、お答えをいただければありがたいな、このように思います。
まず私は、今回まさに先生がおっしゃいました政治主導、これは、政策の体系を整える、それからそれを実際にできるように計画する、それがまさに政治だと思っております。ですから、政を治める、物事を決めていくのが政治、そして政を行うのが行政だ。ですから、官僚をうまく活用しながらリーダーシップをとって物を決めていくのが政治なんだと。だから、ある一面で、もう役所は要らぬ、政策、法律は全部自分たちでつくるというような声もあるけれども、私はそこはちょっといろいろ考えた方がいいな、こういうふうに思っているのです。
きょうの憲法の話なんですけれども、五十三年たちました。世界で十五番目に古い。しかも一度も改正されていない。私どもはそれが当たり前のように大切に、先生も何回もお話しいただきました、不磨の大典という形になっておるわけなんでございますが、ドイツは四十六回、先生に釈迦に説法でございますけれども、一週間前に四十七回目の改正があったそうでございます。そしてフランスも九月に十四回目の改正ということなんですね。
御案内のように、我々はこれをどうしてこんなに大切にするのかな、もちろん国家の基本法ですから大切にするのは当たり前なんですが、なぜさわってはいけないんだ、ここが私は不思議で仕方がないのです。無理に直す必要もないけれども、さわることを許さぬというのは私には全く理解ができないということでございます。
そして、実は、そういう意味で政治主導のもとで憲法調査会がこの衆議院に設置された。その前に、二年間でしたか、中山先生また先輩方が御努力をされて憲法制度調査会設置推進議員連盟というのができておりまして、私もそこに入っておりました。
今でも忘れられないのですが、二年前でございましたか、憲法五十年を記念して、GHQのまだお元気な方に三人おいでいただきましたけれども、憲法調査会のシンポジウムをやったのです。よく覚えておりますけれども、そのときに、憲法草案にかかわったとされる方のお話は、この憲法は確かにマッカーサーから指示を受けて民政局で六日間でやりました、そしてそれは日本の占領下における私たちがつくった憲法だと思っておりました、独立後は自主憲法を制定しているものだと思っておりましたが、まさか五十年間、一字一句変えずに使っていただけるとは思いませんでした、ありがとうございましたと。そういうことを向こうから来た人がおっしゃったときに、何と皮肉なことかな、こういうふうに思ったわけでございます。
そこで、私は、だから直せばいいんだとは思っておりません。ただ一方で、時代にそぐわないところが出てきている。それから、先ほどから先生がおっしゃっていらっしゃる、政治が主導して国の形、そして国の方向の基本を整えるものとして、これは今まさに時代が変わろうとしている中、大いに議論していかなくてはならないのではないか、このように思うのでございます。
そこで、これは本当に基本的なことなんでございますが、先生は、憲法改正の手続の問題、そして発議と国民投票、こういうことにお触れになりましたが、私はもう一つその前に、一体全体この憲法は、原案をつくるのはだれがどういう形で作業をすべきなのか、このことも考えるべきだと思っているのです。
我々は、政を治め、そしてルールを決めていく仕事です。でも、決める前に、原案となるもの、立法作業といいますか、これは一体どういう形で行われていくべきなのか。これは、通常の法律と同じように、我々が議員立法でやっていくやり方もあると思います。しかし、国の基本となる憲法が果たしてそういう形でいいのかどうかというところに私はちょっと疑問を持っておりますし、法律学者として先生の御見解をいただければありがたいと思います。
例えば、大日本帝国憲法はだれがつくったのか、実際に書いた人はどなたなんでしょうか。そして、アメリカの憲法もそうです。ジョージ・ワシントンが出したといっても、一体だれがそのとき書いたのか。私は、審議のたたき台になる、また我々がこれから議論していくことはその原案の中に盛り込んでいくかもしれないことなんでございますが、これを一体全体どこがどういう機関でやるのかということは、実は非常に政治の役割として大きなことになるのではないかというふうに思うのです。
今の日本国憲法は、大日本帝国憲法改正案という形で出た。これも、今いろいろ資料がございまして、読むと極めて興味深いのですが、ホイットニー民政局長のもとでメンバーがやった。そして、マッカーサー三原則とアメリカ憲法及び州憲法、ワイマール憲法、フランス憲法、ソ連憲法、それから前文はアメリカ憲法とリンカーンのゲティスバーグ演説、テヘラン会議宣言等々が参照された。そして、その当時出していた日本案はほとんど重要視されなかった。ただ、一方で、唯一重要視された、GHQが参照したのが、学者さんの私的グループによる憲法研究会、これが発表されたものについては重要視されたというようなことが過去の歴史を振り返ってみると出てくるわけなんです。
今私たちは、九条をどうしましょうとか、前文をどうしましょうとか、そういう議論に入っている場合もあります。ただ、政治主導として行って憲法をつくっていく過程、これはもう少し考えを深めるべきことがあるのではないかなというふうに思っているのでございますが、先生の御意見をいただければ大変ありがたいと思います。
○佐々木参考人 今、いろいろな形での憲法のつくり方についてお話があったかと思います。つまり、ゼロから全面的に変えるというような場合ももちろんあるわけでございまして、ですから、それぞれ、どういう範囲のものを変えるのかというようなものによって、つくられる仕組みというものに多様なものが出てくる。だから、憲法をつくるための特別の国会みたいなものをつくってやるというケースも、もちろん昔はあったわけでございます。
ただ、今先生言われたようなお話のうち、例えばこの中のある部分について変えるというようなことを考えるとしますと、その手続というのは、もちろん各党で事実上いろいろなアドバイスを受けるなりなんなりというのは幾らでもおやりになって結構だと思いますけれども、第三者の審議会みたいなものに投げるというのは、先ほど来議員が言われた趣旨とも非常に違うのではないだろうか。
私自身、確たる提案があるというほどのものではございませんけれども、例えば国会にこういった、調査会なのか何なのかわかりませんけれども、憲法を議するコミッティーみたいなものがアドホックであれ何であれつくられるということがやはり一つのベースになるのではないだろうか。いつもつくっておく必要はないかもしれませんけれども、そのことを考え続けるための場があるということはそんなに不自然なことではないだろうというふうに私自身は考えております。
ですから、どういう委員会かわかりませんけれども、何か憲法を扱うコミッティーといったようなものを舞台にして、そこで、果たしてどういう手続でもってどれだけの賛成があればどうだこうだという話は、これは最後は非常に政治の問題になろうかと思うのですけれども、ある程度議論を煮詰めないと、国民に対して提案をすることはできないのは言うまでもございません。
ですから、どこまでが煮詰まり、どこまでは対立点は残るんだけれどもあえて提案するという形にするのかどうかというようなことについて、そういう場で審議をされるというのが一番オーソドックスなやり方ではないだろうか。ですから、事実上のアドバイスその他の問題は全部切り離して申し上げたつもりでございます。
○新藤委員 なかなかどっちと決められるものではないと思うのです。ただ、私は、当然自分たちだけでやればいいんだ、国会で決めればいいんだ、例えば公職選挙法を直すのに国会議員だけで直していいのか、こういうのと同じ部分があるんではないかなというふうに思っておりまして、これは先生からもまさに参考になる御意見をいただければいいなというふうに思っておるのです。
そして、実は今のお話にもありましたし、先ほどもお触れになりましたが、先生としては結論を出されていないなというふうに思っていることがございます。憲法の改正のことなんですけれども、結局、今論議をしていく中で、先ほどからまさに先生がおっしゃっているように、全面改正すべきなのか、それとも、部分的に国民的合意ができた上、そこからまず改正するのか、こういう二つがあるとおっしゃいました。
そこで、これは一体どっちがいいんですかということを我々もやっていかなきゃならないわけです。どっちがいいんだとだれも決められないと思うのです、みんな意見はそれぞれですから。
ただ、政治主導として、今のこの国のこういう状況を見て選択するならば、より望ましいのはどちらなんだ。できるかできないかということではなくて、より望ましいのはどちらなんだという観点からすると、これは、現実的な方をとるか、それとも、対立は厳しいけれども、いろいろともめるかもしれないけれども、全面改正か。これは先生の個人的な感覚で結構でございますので、もし支持をされるとすれば、二つしかなければ、先生はどちらをお選びになるか。
それからもう一つ、その場合に、改正の手続の問題も出てくるんですね。今、不磨の大典化しているのは、まさに厳格な手続の中で非常に動きづらくなっているという部分があると思います。
もし作業が進んでいったとして、改正をするということになったとして、果たして、今度改正をする憲法ではその改正の手続は柔軟にするのか。そして、諸外国のようにそれこそ何十回も場合によっては時代によって変わっていくこともある、そういう状況のものにしていった方がいいのか。それとも、やはり日本は日本独自の、一度つくったら五十年、百年、もちろん手続を厳格にすればそういうことがあり得ることになるのではないかと思うのですが、これも、先生のお考えでは、望ましいとすればどちらなのか。ちょっとお答えをいただくのは難しいかもしれませんけれども、参考までに教えていただきたいと思います。
○佐々木参考人 私は、先ほども申し上げたかと思いますけれども、国民生活に非常に重大な影響を及ぼすとおぼしき条項、こういったものは改正ということになりましてもなかなか難しいだろうというふうに思います。これは、必要万やむを得ざる状況に陥って、とにかく何はともあれやらざるを得ないという場合ももちろんあるかもしれないけれども、そういうことでないとすれば、大事なのは、今の御質問と若干ニュアンスは違うかもしれませんけれども、そんなに対立がないようなことでもやってこなかったのかもしれない。発議条件が厳しいからということでそこも全部説明してきたところはなかったろうかというのを、まさに一つは考えていただきたいというふうに思う。
ただ、全体的な方向として言うと、私は、発議条件を緩和することは十分考えるに値するというふうに思っております。その具体案はいろいろあると思うんですけれども、三分の二という問題もございますし、両院という問題もございますし、それから国民は過半数ですから、これをどう考えるか、それぞれについていろいろな提案があり得るかなと思っております。ですから、改正手続について、今の制度をとにかく何はともあれこれだけは守るべきだという議論に私はくみするつもりはございません。その点だけは申し上げておきます。
○新藤委員 ありがとうございます。
今の時点ではまだどちらと決めるべき段階にまで来ていないことでもあるんですね。ただ、これから作業していく上で、議論をしていく前提として、やはり先生に今そういうふうにお話をいただいたのは非常に大きな意義があると思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
それから、要は、今までの議論も、結局、本来ならば初めに憲法ありき、初めに法律ありきで、その法律のもとで何ができるのかということを考えるのか、それとも、自分たちのやりたいことや望むことがあって、そして何をやるべきなのか、法律の中でやるのか、それとも法律を決めていけばいいじゃないか、こういう行って来いの議論があると思うんですね。
要は、それが堂々と憲法を論じられるようになったということは、私は、それだけこの国が成熟してきた、そしてまた、いろいろと御批判いただいておりますが、政治もそういう意味での成熟度を増したんではないかな、このように思っているんです。
その大前提として、憲法は国の基本となるものですから、その意味で、国民意識とかそれから国に対する国家観、こういうものをこれからどういうふうに我々日本人は持っていくべきかということが大切な要素になってくるんではないかなというふうに思っているのでございまして、きょう先生お触れになっておりませんけれども、恐縮ですが、また参考になる御意見をいただければありがたい、このように思うんです。
それは、今私たちの国、非常に連帯感が薄れているような、個人個人がばらばらになっている、こういうことをよく言われます。そして、そういう意味での国としての統一性というんでしょうか、国民としての、私たちは日本に住んでいるんだ、こういう一体感が弱いというよりも表に出ていない時代だなというふうに思っているんです。
これは一方で、不思議なことに、友達同士とか自分にかかわりのあることについては物すごく強烈に結びつくんですね。そのかわり、ちょっと離れて、自分に直接関係ない、所属しているけれども自分には直接関係ない、そういうものについては今度は極めて冷淡になる、こういう不思議なというかおもしろい現象があるんではないかというふうに思っています。
ふだんは全然知らぬ顔している人たちが、例えばオリンピックだとかワールドカップのときによくわかるんですけれども、もともとはまとまりがいい民族なんだなとそのとき改めてわかります。これ一回でワールドカップに出られるんだ、もう一回勝てばメダルとれるんだ、そのときの日本人の熱狂ぶり、特にふだん白けている若い連中が、おれは君が代なんか知らない、日の丸なんか嫌いだ、こんなことを言っている人たちが外国へ出かけていって、もう一回ここで勝てば日本がワールドカップに出られるとなるとみんなで立って国歌を歌う。
何か私は、日本人のアイデンティティーというのは、昔の一億総火の玉、これに尽きるなというのが個人的な感覚なんですけれども、そういう底に流れているものと、それから表面上の表現の仕方が今全然違ってきている、このように感じております。
それに、うがった見方かもしれませんが、これに対して、戦後の日本社会をつくってきたこの憲法や日本の国の進め方、これは影響が出ていないのかどうなのかというようなことを私は感じているんです。
今の憲法は戦前の軍国主義、全体主義を否定して、基本的人権を尊重しましょう、こういうもとで封建制を壊しましょう、こういう憲法だと思っているんです。個人の権利を尊重しなさい、それから農地解放だとか財閥解体だとか、要するに富や権力の集中を排除した、教育改革や、労働者や女性の解放を行った、これは非常にいい効果をもたらしてきましたけれども、その一方で、無理やり、国家国民だとかそういうことを考えるのはおかしいよ、自分のことを主張しなさい、こういうような風潮を生んできてしまったんではないかなというふうに思うのでございます。
特に、この憲法の中には基本的人権の尊重規定というのがございますけれども、国だとか公共への義務とか奉仕、こういうものについての規定がないに等しいというか、極めて少ない。教育の義務と勤労の義務と納税の義務しかありません。こういうことがありますし、今話題になっている教育の改革についても、基本法についても、まさに個人を追求しなさい。これは憲法から導き出されてきている道だなと私は思っているんです。
そこで、長々になって恐縮なんですが、先生、これからの私たちの国のあるべき姿として、一体日本の国、個人の権利と公共や国に対するこういう意識、これはどこまでどういうバランスをとるべきなのか。先生、今現状をごらんになって、私は今のがだめだと思っていませんよ、結局、最終的には日本人はみんなまとまります。でも、今百花繚乱で、議論は自由なんだ。権利を主張することをどんどんやって、そのおかげでいろいろな仕事が進まなかったり、この政治の場もそうなんですけれども、ある意味での混乱も巻き起こっているような気がするんです。個人と国や公共との集団、公のバランス、これはどういうふうにとるべきなのか、お考えをお聞かせいただければありがたいのでございます。
○佐々木参考人 大変難しい問題で、いろいろな観点から議論できる問題を提起されたというふうに思っております。
ただ、私自身の認識を申しますと、自分の非常にプライベートな利益に関心があるというのは、これは万国共通で、どこもそうです。それから、だんだん豊かになりました結果、日本人は自分の趣味に興味を持つようになった、海外旅行も含めてなんですが、これも議員御案内のような形で、それは確かにふえてきていますね。
問題は、それだけでいいんだろうかということを、私の世代も含めて国民はやはり考え始めているんだと思うんですよ。それで、そういういわば非常に自分、個人に近いところで満足するというのを超えて、何かしなきゃいかぬじゃないかという気持ちをかなり潜在的には持っているのかな。ですから、これは必ずしも議員のおっしゃる意味と同じかどうかわかりませんけれども、例えば外国の貧しい人々のために自分は何かをしたいんだという言い方もこれはある。
ですから、それは国とか日本というのに必ずしも一元化されるとは限らないんだけれども、非常に個人ないし自分の周辺のことだけで全部がんじがらめになっているという状態は、ちょっと人間としてのバランス上必ずしも好ましくないなという意識は今の日本に結構存在し始めているのではないだろうか。ですから、そこからどこへどういう形でそれがあらわれていくのかなということについては、いろいろなあらわれ方があるのかなというふうに私は思っております。
ですから、議員があるいは意図されたことのように必ずしもならないかもしれませんけれども、非常に身近なところだけで何かやっているというので十分だという時代は終わって、それは高齢社会の問題もあるかもしれないし、地域の問題もあるかもしれないし、何か自分たちで、生きがいの問題も含めて、ちょっとパブリック的なことをやってみたいな、あるいはやるべきではないかなという状況に今日本人はいるのではないかなというふうに私自身は思っております。そういうエネルギーをどういうふうにうまく活用していくかというのが、これが政治の側の知恵にかかわることではないかなというふうに思っておりまして、一部お答えになったかどうかわかりませんが、そんな感じを持っております。
○新藤委員 ありがとうございました。もう十分なお答えをいただいております。
すべてそれが憲法なり法律なりに原因があるわけではない、これは先生おっしゃるとおりです。でもしかし、大きな流れの中で、やはり国が戦前から戦後の大きく方向転換をした大きな目的といいますか、一つになっていると私は思うんですね。ですから、結局、国の基本法たる憲法を論じるときには、一体、日本人と国というものをどういう方向でどの程度でバランスさせておくかというのは非常に重要な問題だ。もちろん、このことは違う考えの方もたくさんいらっしゃいますので、大いにこれから憲法調査会で議論すべきことではないかというふうに思うのでございます。
最後に、残り時間も少なくなってまいりましたが、これまた先生、非常に総花的とか大枠の話で大変恐縮なんですが、私はそういう自分の物の考え方を長い目で見るようにしたらというふうに思っておりまして、今日本人は、国内においては自分たちはすごいと思っているわけですよ。ですから、国の中では日本人一人一人はみんなそれぞれ自分でプライドを持って物すごく自己主張をします。でも一方で、外国へ出ると、自分は東洋の小さな島国だ、こういうふうに思っている人がすごく多いのですね。外国に出ると、我々日本人はまだ小さな東洋の国だから、こういうふうに言っている。内にあっては、経済にしても何にしても、国内では一流だ、自分たちはすごくレベルが高くなっている、こういうふうに思っている人たちが多いというふうに思うんですね。
そこで、例えば、アメリカは確かに日本の人口の二倍、国土は二十五倍です。でも、イギリスは日本の人口の半分しかありません。それから、国の大きさは実は日本の六割なんですね。それで、GDPは八掛けです。ドイツにしても中国にしてもしかり。ドイツは大きな国かと思ったら、やや日本の方が大きいのですね。
国の大きさとか人口で別に競争するわけじゃないのですけれども、これから私たちは、戦争に負けて、そしてその後、奇跡的な復興を遂げて、今こういう価値観が多様化している中で、次の時代の私たちの国の位置、これは国際社会できちんとした尊敬と、それから自分たちの義務を果たせるような、そういう位置を占めるために一体何が大事なんだろう。
結局、考えてみると、歴史上、今まで日本の国は、あるときまで、ある線まではいいところまでいったと思うんです。明治時代も列強列国に伍して戦うほどにいって、そしてめちゃくちゃになった。まただめになったかと思ったら、もう一回立ち直ってきた。でも、いつでも共通しているのは、やはり東洋の特殊な国で、世界の中で、私もちょっとそれはコンプレックスになっているのかもしれませんが、どう見ても、やはり日本の国力やこれだけの勤勉性を持った国の評価というものはまだ正当なものになっていないのではないかな。だとすると、それは私たちの国の今のあり方に問題があるのではないかなというふうに思うんです。
非常に総花的とまさに申し上げましたけれども、恐縮なんですが、これからの日本のあるべき姿を考えるときに、一体どんなポイントが重要になってくるのか。国際社会の中の日本ということで、先生のお感じになっていることがあったら、最後に教えていただきたいというふうに思います。
○佐々木参考人 時間もあれですから、簡単に私の考えを述べさせていただきます。
それはもちろん政府なりなんなりの役割は非常に大きいということはそうなんですけれども、やはり我々が持っている国民の能力を生かす仕組みというものをもっと工夫する必要があるのではないだろうか。まさに政治主導というのも、国民の能力を今までとは違った形で動かしていこうということなのではないでしょうか。だから、そういう点で、まず何か今までなかったようなことをぜひやっていただきたいのですよ。
これは時間がかかることですから簡単にはいきません。だから、あそこのかなりの数の人々をいろいろな形で政治的なアポインティーとして使えるというふうになったことをどう活用されるのかという、具体的なことで私としてはぜひ成果を見たいなというふうに思っている、例えば外国に派遣する人をどういう形で決めるのかというようなこと一つをとりましても。ですから、いろいろな段階の議論があって、まず隗より始めよというタイプの話もございますので、例えばそういうことも考えられると思うんです。
ただし、何か非常にまどろっこしい気持ちは私もよくわかります。だけれども、何か特効薬と言われても、これだけやれば十分だというふうなものがあるかと言われると、私は、やはり御時世も変わってきていますから、必ずしもこれだというふうにもなかなか言えないところがある。だけれども、まず足元の問題として言えば、例えばそういうことで随分日本の政府のイメージというものも変えることができるのじゃないか。そういう試みもぜひやっていただきたい。
これもちょっとまたお答えになっていませんけれども、私の手短な感想だけを申し上げました。
○新藤委員 ありがとうございました。
2000.08.03 川口市のために
川
口といえば、故小渕前総理の第1回国民対話集会を新藤代議士が招聘し、他にも中小企業のモデル地区として指定などで国から近い街に変わった。8月3日、岡
村市長の、県南治水の予算と来年度国庫補助の陳情を、野中幹事長にセットした。さらに日本発の情報新拠点となるSKIPシティへの政府の協力づくりなど、
首都圏の核として、川口をさらに構築していくことに全力を傾けている
再生資源の利用促進に関する法律の一部改正法律案(質疑)衆議院商工委員会-12号 2000年4月19日
再生資源の利用促進に関する法律の一部改正法律案
147-衆-商工委員会-12号 2000年04月19日
○新藤委員 おはようございます。自由民主党の新藤義孝でございます。与えられた時間が十分でございますので、非常に難しい質問でございますが、ポイントだけ御質問させていただきたいというふうに存じます。
私どもは、自由民主党の立場として、政府とともにこの独占禁止法の改正についてさまざまな作業をやってまいりました。私も個人的な信念の中で行わせていただいたわけでございます。
この総括で申し上げることは、とにかく日本の商業環境、そして産業構造、これを直さざるを得ない、そういう時代の背景を受けて、その代表たるものが規制緩和である。これは、委員の先生方皆さんが共通認識のことだと思っております。
ただ、私どもは、この何年間かの規制緩和というものを見ておりながら、やはりそこにはある前提が必要だ。すべての規制を緩和してしまってなくなるということは、究極論は法律も要らない、何にも要らないということになりますから、規制緩和を行うについても、最低限の社会的な規制だとか、それから公正取引環境の整備、こういうものを前提とした規制緩和をやっていかなきゃならぬ、こういうふうに私は思っております。そして、そういう活動をやる大勢の仲間とともにこの作業にタッチさせていただいたわけでございます。
この中で、今回は我々の考えが盛り込まれた法律の改正案になっております。そして、基本的にこれを進めさせていただきたいという賛成の立場でやっておるわけなのでございますが、あえてここで確認という意味で、また公取の方でどういうお考えを持っているかということのために質問をさせていただきたいというふうに思っております。
特に、私どもは、規制緩和が進み過ぎた結果として大変な問題が起きているものとして、ガソリンスタンド、それからいわゆる小売の町の酒屋さん、こういった皆さん方に今いろいろ不安が出ているということを確認しております。
そういう中から出てきたものとして、今までは、公正取引委員会に申告をして、そして不正な取引が行われているかどうか、それから不当廉売だとか差別待遇、さらにはメーカーによる優越的地位の濫用、こういうものが行われていると個人的に思っていても、なかなかそれが仕事の面で立証できなかったり、業界として対応できない、こういううらみがございました。そのために、今回は、公取に申し入れをするだけではなくて、個人の立場で裁判所に訴える、差しとめ請求をするんだ、この導入をしたことが今回一番大きな成果ではないかな、我々はこういうふうに思っているのでございます。
この場合に問題になってくるのは、差しとめ請求をするのですけれども、その場合に、不正の目的の提訴の場合は原告に担保を提供させる。これは当然、差しとめ請求制度を濫用され、悪用されては困るということで歯どめが必要だと思うのだけれども、この原告に担保を提供させるということが逆に差しとめ請求をしづらくなってしまう、こういううらみがあるのではないかな、そういう心配をしている者があるのだけれども、濫用防止の精神、原告に担保を提供させるということを導入した目的というか、その部分を確認をしていきたいと思うのです。
○根來政府特別補佐人 今回提出いたしました法案には、私人の差しとめ請求の制度を入れているわけでございますが、こういう制度は光と影の部分がございまして、光の部分は非常に結構だという評価を受けるわけでございますが、やはり影の部分として、濫用といいますか、特に商売の話でございますから、商売の目的のために濫用するということもあり得るわけでございます。
そういうことをおもんぱかりまして、特に、これは被告の抗弁といいますか、被告の申し立てによりまして、かつその被告が疎明した場合に限りまして裁判所が担保の提供を求めるということになりますので、その光と影の部分がうまく調整できるのではないかというふうに思っております。
○新藤委員 もう少しわかりやすく確認させていただきたいと思うのです。要するに、言葉のとおり、不正の目的の提訴の場合は原告に担保を提供させる、だから、逆に言えば、不正の目的ではない正常な目的の提訴の場合は担保は必要ない、こういうふうに私は判断できるんだし、また、それをしていただかなければこの請求制度をつくった意味がないわけでございまして、これは大変な誤解を生じるおそれがあります。だから、当然これは正当な提訴なんだという場合には担保は必要ないんだよということをきちっとPRする必要があると思うのだけれども、どうですか。
○根來政府特別補佐人 おっしゃるとおりでございまして、正当な場合は何ら担保なしに請求ができる、こういうことでございます。法案が成立した場合に、私どもも、その点誤解のないように十分PRといいますか宣伝したい、こういうふうに思っております。
○新藤委員 ありがとうございました。そこが大切なところでございまして、これは要するに、一般の素人というか、個人的な請求、この制度を使おうと思っている人にはそこをきちんと言わないとだめなんで、法律にはそこまで書く必要はありませんから、やはり私は、ここではっきりさせていただきたいということでございます。
それで、時間がありませんので、あと、大切なことは、独禁法を緩めてさらに取引を活性化させるわけですから、いろいろな市場を開放して、新しい方々が入ってくる。当然取引がふえる。ということは、またこれに対して、取引がふえたことによって、独禁法の適用を検討しなければいけない作業がふえてくると思うのですね。
だから、その場合に、窓口を開放してどんどん市場を活性化しなさい、その結果、今度は独禁法に抵触するおそれのあるものが、ハードルが低くなったんだから、数がふえる。では、そのふえた案件を迅速に処理できなかったならば、結局またこれは意味がないということになる。ということは、この公正取引委員会の機能を強化する、それから体制を充実させる、このことが大変必要になってくるというふうに思うのです。
そういうことについて、きょう公取の委員長おいででございますから、これは決意のほどと、それから、私どもとしては、こういうものを推進させるんだから、やはり体制を充実させるための人員だとかそういうものを我々も考えていかなきゃいけないのじゃないか、こういうふうに思っておりますが、公取側の立場として、この決意というか、また要望、こういったものがあれば聞いておきたいと思います。
○根來政府特別補佐人 まず、体制の強化でございますけれども、これは国会でも、また政府部内でも大変な応援をいただきまして、小さい政府を目指しているときに、やはり年々、私どもとしては少ないと思っておりますが、増員をいただき、体制の強化を図っていただいておるところでございます。
それからもう一つは、私どもは、やはりこういう自由経済、自由競争の時代になりますと、今までの独禁法でとらえ切れない点がたくさんあると思うわけでございます。そういうことについては常々検討を怠らないという態度で、また国会等の御議論を踏まえまして、法律の改正等をお願いしているわけでございます。私が就任してからも、先ほども言っていたのですけれども、毎年この独禁法の改正をお願いしているわけでございますので、引き続きよろしくお願いしたいと思っております。
それから、最近の風潮にかんがみまして、親切な行政と言うとまたおしかりを受けるかもわかりませんけれども、やはり国民にわかりやすい独禁法の執行ということが必要であろうかと思うわけでございます。そこで、民間の方々の御協力も得、また私どももいろいろ考え方等を公表しまして、できるだけわかりやすく、かみ砕いて、理解していただくような努力を積み重ねているわけでございますので、各般にわたり御指導をお願いしたい、こういうふうに思っております。
○新藤委員 ありがとうございました。
とにかく、これはきっちり運用しないと、別に犯罪ではないんだ、犯罪行為ではないから取り締まれないんだ。ただ、要するに、日本の商環境というのは町のいわゆるコミュニティーの中で成り立っている部分がある。人間と人間のことなんだから。だから、これを壊してしまったら日本の地域コミュニティーも壊れるんだ、商業を保護するだけではないんだということから、これは厳正に執行してもらいたいというふうに思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
中小企業事業活動の活性化等法律の一部改正法律案(質疑)衆議院商工委員会-7号 1999年12月3日
中小企業事業活動の活性化等法律の一部改正法律案(質疑)
146-衆-商工委員会-7号 1999年12月03日
○新藤委員 先生方、きょうは朝から大変御苦労さまでございます。私は、自由民主党の新藤義孝でございます。
先生方からただいまいただいたお話に、少し質疑をさせていただきたい。ただ、時間が二十分しかございませんので、大体お一人様一問になってしまうかな、このように思うのでございますが、短い時間の中で意は尽くせませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、本国会は、小渕総理が大々的にぶち上げておりますように中小企業国会ということでございまして、まさにさきに可決いたしました中小企業基本法と、それに引き続く今回の関連の、中小企業活性化のための関係法案、さらには新事業創出促進法、これは今国会の目玉だと思うんです。
それは、イコール、先ほど先生方おっしゃっておりましたけれども、日本の中小企業、今回カテゴリーを広げましたから、これでたしか日本企業の九九・六%は中小企業になってしまう。日本の経済を再生もしくは新生させるためにはここの部分が頑張るしかないんだ。そういう意味で、いろいろと実利の上がるように法律をつくろう、こういう趣旨で私どももこれを見ているつもりなんです。
まず、橋本先生、中小企業政策審議会の議論に参加されて、この法案の一連の流れ、組み立てに絶大なお力をいただいた方だ、このように思っております。
今回、特に中小企業基本法の中で、要するに数を合わせて、数の論理から、今度はきめ細かくそれぞれの独立した中小企業をつくっていこう、こういう趣旨が今回のポイントかなというふうに私は思っておるんですが、こういう意味で、本関連法案がきめ細かな対策を行ったと言い得るかどうか。社債を発行する、それから中小・ベンチャーに対しては無担保の貸し出しを可能にした、さらには小企業、創業者には無利子貸し付け、一応カテゴリーごとにはそろえたつもりと私は理解しておるんですが、大もとの組み立て人として、まず橋本先生、御意見を賜ればありがたいのですけれども。
〔委員長退席、小林(興)委員長代理着席〕
○橋本参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、従来、中小企業というのは業種を対象にして考えてきたと思いますが、今回の法案は企業を対象にしていく、したがってきめ細かい対応が必要だということになると思います。
ただ、今回の提案されております法案は、先ほども申し上げました金融に限られておりまして、ほかの法案も今後準備されるのではないかと想像いたしますが、そのきめ細かさが十分かというふうなことに関しましては、実は大変基本的な重要な問題点があると思います。
それはどういうことかと申しますと、どういう政策が最適かということが事前にはわかっていないんだと思うんですね。かつての近代化政策とか高度化政策というのは、ある程度事前にわかっていた。ところが、今回は事前にはわからないわけでして、ですから、信用保証の問題でありますとか、エクイティーファイナンスの問題でありますとか、あるいは税制の問題でありますとかというのを組み合わせていかざるを得ない。
それで、私の期待しているところは、具体的に政策を、今先生御指摘のとおり、ワンパッケージで一応金融に関しては考えたわけでありますから、そのワンパッケージの政策がうまく機能するかどうかを適切に政策評価して、もしまずい点があったらこれを迅速に変える、あるいは修正していいものに変えていく、そういうふうにお考えいただけると大変いいのではないかと思っています。
○新藤委員 ありがとうございました。
先ほど、日本の政治に関して、スピードが世界一遅い、こういう御指摘もいただいたり、また逆に、ベンチャーキャピタルの方は今すごいスピードだと。まさに今の先生のお話のように、即時即応していく、そして我々も柔軟に、小出しにしないで大枠でもって方向を定めて、それで必要があればどんどんつくっていく、これでいいんじゃないかと思うんですね。ぜひ今後参考にさせていただきたいというふうに思っております。そして、もっとお話を聞きたいんですが、申しわけございません。
次に、タカコの石崎社長さん、何か二十九歳から独立されて、先ほど来ておりましたけれども、私どもの仲間の岩永代議士と大変お地元が近いということで、タカコとは実は何かなと私は思ったんですよ。人のお名前だとすると、私のおふくろがたか子というものですから、これはいい会社だなと思っておりましたら、山の名前だそうでございますけれども、しかし、大変に御苦労されて、本当にたたき上げで、そして今、オンリーワンというか、日本でトップシェアで、しかも世界の七五%をお持ちになっている、こういうお話でございます。
大変御苦労されたと思うのですが、やはり語り尽くせないと思いますが、一点で言えば何が、ここまでうまくいった成功の秘訣というか、キーワードは何かというのがあれば教えていただきたいというふうに思います。
それからもう一つは、今法案について、まさに今橋本先生からも御指摘いただきましたように、金融面のパッケージをつくったわけでございます。そういう中で、この法案で、この枠組みで中小企業の資金調達がどの程度円滑化されるか、この法案に対する評価をできれば一言お願い申し上げたいと思います。
それから、蛇足ながら、先ほどの内部留保金課税については、きのう税制調査会で私どもの商工のヒアリングの場がありまして、とにかく連結納税と内部留保を必ずやろうじゃないか、こういうことで、大騒ぎで我々はやっております。
スピードも遅くないと思いますが、ただ、留保金課税全面廃止かというと、それこそ日栄の留保金はいいのか、こんな話が出てくるくらいでございまして、ベンチャーだとか体質のまだ弱いところを支援するための、しかもアメリカと日本しかとっていない税率ですから、我々も考えているということは御報告申し上げたいと思います。
では、済みません、何か余計な話になってしまいましたけれども、二点お伺いしたいと思います。
○石崎参考人 どうも失礼の数々を申し上げて申しわけございませんが、ふるさとの山の名前が高香山ということで、よく御婦人の名前かと言われます、奥さんの名前かとも言われるのですけれども、うちの家内は道子といいまして、全然違うのでございます。
何がというふうにおっしゃられて、ただ一生懸命頑張ってきたわけでありますが、ただ、人の嫌がる仕事といいますか、産業界には人が避けて通るような、あるいは非常に精度がいいとか厳しいとか、安いとか数が少ないとか、そういったふうな、人の嫌がるような仕事というのは世の中にたくさんあるわけでございますが、立派な会社でも、どうしてもできないような問題点も抱えておられまして、そういうものに対してチャレンジしていこうと。
たまたまオイルショックのときでありましたので、ほとんどの会社が、大手さんがグラウンドの草むしりをしていたのです。そのとき草むしりということが話題になったぐらいでございます。その中で仕事をとっていくには、ありきたりのものをやっていたのではいただけないわけでありまして、そういうことを主眼にして、国内、そして当時会社の売り上げの三カ月分ぐらいのお金を使ってハノーバーのドイツのメッセに出展いたしまして、世界にもそういう問題を抱えている会社もたくさんあるに違いないというふうなことでやりましたのが、大変皆さんのいろいろな協力を得て、一応、あすの日はわかりませんが、きょうまでお仕事をさせていただいたというふうに思っております。
それから、このたびのいろいろな法案で、我々中小企業や小企業、零細企業にとりましては、資金調達のニーズということに対しましてはこれから本当に助かると思います。そういう面では、利用していけば、従来と違う形で、今まで苦しんでいたことが少しはいやせてくるだろう、こう思います。
しかし、小規模零細企業にとりましては、例えば社債だとか転換社債だとかワラントだとか私募債だとかいいましても、ちょっとぴんとこないところが実はあると思います。そこそこの規模の会社になれば、それはそれで一つの形になるのかと思いますが、そういった底辺への、すそ野への手当てもこのたびいろいろとしていただいておりますが、それらをどういうふうにして浸透させていくのか。意外に、商工会議所とかいろいろなところからパンフレット等が来ても、会議所に入っていないところすら多いものでございますから、なかなか知る機会というのを知らないケースがありまして、この辺をどうPRしていただくかというのが一つのポイントでないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○新藤委員 ありがとうございました。
要するに、今お話を伺うと、人の嫌がること、それから志を大きく世界に、これがキーワードかなというふうに思ったわけでございます。それから、奥様の名前が道子さん、私もおばさんの名前が道子さんでございまして、とにかくみんなつながっているというか、何かそういうところから人柄が非常に今わかって、さすが大きな経営者は違うなという気がいたしました。
そして最後の、この制度をどう浸透させていくか、これはまさに私もそのように思っています。今回、この関係で国がナショナル支援センターをつくるのです。それから、都道府県単位で広域の中小企業支援センターをつくる、それから全国広域市町村圏でつくろう。国、県、市でそれぞれの事業規模に応じて支援センターをつくろうと。だから、この支援センターが役所的なものだったり、ただPRしたりとかそんなものではだめなので、ここをこれからやろうというのを私どもも今研究しているところなので、ぜひまた御意見をいただければありがたいと思います。
それから、松田先生、川分先生。それぞれエンゼルとベンチャーキャピタルのまさに専門の方々でございますし、松田先生は大学の方でビジネススクールまでおつくりになられている、このように聞いているのでございます。
特に、先生が先ほど指摘された、個人の投資が少ない、これは日本の金融の大問題だなと私も思っておりまして、千三百兆個人金融資産があるといっても、半分は貯金ですね、まさに眠っているお金だと。対する個人の市場に対する投資というのは、日本人の場合、私の記憶ではたしか三・六%とかそんなようなものなんですね。要するに、いかに市場が信用できないかということと、それから個人がそちらに目を向けていないかということだと思っています。逆に言えば、これだけ眠っているのですから、私どもがこの市場を開くことができれば、これは日本経済の活性化に大いに役に立つ。そういう意味でのベンチャーキャピタル、私はまことに希望をここに持ちたいなというふうに思っているのでございます。
ただ、そういう中で、今回はそのベンチャーを何とかしようということでもろもろの法律をつくりましたけれども、これについて、それぞれ御専門の立場から、今までベンチャーだベンチャーだと言っていても、正直申し上げて、いま一つ政府の政策は実効が上がっていないのかなという気も私しているのです。この意味で、今回この法律、我々としては鳴り物入りで、目玉でつくっているのですが、これによってどの程度よくなるのか、評価いただける点があれば教えていただきたいというふうに思うのです。
それから、日本とアメリカ。アメリカの場合、逆に貯金が全然ないのですから、もしおかしくなったときに本当に大丈夫かしらと私ども思うわけで、別にアメリカのまねをする必要はない、日本には日本のやり方があると思うのですけれども、そういう意味で、今法案でやり残したことがあるとするならば、お二人にそれぞれのお立場でお聞かせを願えればなというふうに思っているのです。
私は、個人的には、ベンチャーに対してはエンゼル税制がある、しかし、ベンチャーキャピタルに投資する人たちの税制というのはないわけですね。ですから、やはり投資を誘導するのは税制だと私も思っておりますので、その辺も含めて御意見をいただければありがたい、このように思います。
○松田参考人 いろいろ御指摘ありがとうございました。
まず、制度の評価でございますが、とにかく九五年当時から比べるとさま変わりでございまして、今回私は非常に高い評価をしているわけですが、先ほど先生もおっしゃいました全国に支援センターをつくるということが、ちょっと間違えると、何も役に立たないものを多くつくってしまうということになると思います。
と申しますのは、先ほど申し上げましたように、シニアベンチャーの方と若者ベンチャーの方とスピード軸が全く違います。三年とか五年、先はもう考えられないという今のインターネットのところと、十年、二十年技術を蓄えていくということは、ビジネスは違います。そうしますと、後半の方は大体対応できる人というのは結構おられると思うのですが、前半の方に対応できるとすると、相当頭のやわらかい若い人たちのサポーターをつけなければいけないかなというふうに思っていますので、そこの運用が非常に大事かなと思います。
それから、今、ベンチャーキャピタルの税制問題として、業界で、私も日本で最大のところの監査をずっとしていたという関係がございますし、私ども自身が今、大学が何もしませんので、大学の教員がもう動き出していまして、ベンチャーキャピタル会社をつくって、トータルで四億のファンドで、今二十社ぐらい投資を行っております。
そういうことからも考えますと、債権には貸倒引当金というのがあるのですが、投資に対しては貸し倒れというのが全くないということで、これは、無担保でやるわけですのでリスクがもっと高い、引当金も回収になればより多く後から税金を納めていくわけでありますので、債権と投資というのを同じようなリスクという土壌、リスクが高い方がなくて、リスクが少ない方があるというのも、これも変な税制だと思います。その辺の整合性をぜひとっていただけるとキャピタル業界は助かるのじゃないかなと思っています。
○川分参考人 まず、評価ということについてですけれども、大きな方向性は、現場から見ましても、非常に合っていると思いますので、どんどん進めていっていただきたいというふうに思います。
ただ、これは時間がかかると思います。恐らくアメリカでも十年、十五年かかっておりますので、余り成果を焦って途中でやめてしまうとかいうことがないように、例えば、この第三次ベンチャーブームと言われる中でいろいろな制度をやっていただいていますが、これが本当に出てくるのはまだ数年かかるでしょうし、今この中小企業国会でやっていただいている施策が実際に効果をあらわすのは恐らく五年から十年かかると思いますので、粘り強くやり、どんどん改革を進めていっていただければ、我々も一生懸命やりますので、見守っていただくというか、世論もそうなんでしょうけれども、じっくり見ていただくということが必要じゃないかなというふうに考えています。
それから、やり残したことというか、希望といいますか、それにつきましては、確かに私ども、資金調達、ベンチャーキャピタルがお金を集めてベンチャー企業にお金を出すわけですから、私どものベンチャーキャピタルファンドにお金が集まりやすい仕組み、例えば先ほどおっしゃったような、ベンチャーキャピタルファンドに個人が出したときにいろいろな税制の恩典があるというのがあれば非常にありがたいし、さま変わりになると思います。
それと、今研究しておりますのは、会社型投資信託を使ってベンチャーファンドをつくりまして、そちらに個人の小口資金を入れようとしておりますが、これが若干、ちょっと税制面の不備があるような感じでございますので、会社型投資信託の方はもう少し税制面での工夫が要るのかなというふうに考えておりまして、今研究中でございます。
あと一つ、ちょっと投資とは違うのですが、銀行の動きについてですけれども、私どもが投資したお金は、成長資金、企業が伸びるために使っていただくはずなんですが、銀行の方が、約弁というんですか、ほっておいても銀行の回収が進んでいきますので、結果的に、私どもが出したお金が一年たってみると銀行の返済に回ってしまっているということが起こっているんですね。
ですから、銀行が残高を維持するというのでしょうか、ほっておいたら回収になっていくので、それをストップしていただくような何らかの工夫、あるいは、銀行に追加で資金注入されるのはいいのですけれども、そういうお金があったら新しい銀行をつくっていただいて、そのニューマネーでもって新しい融資をしていただくということであれば回収と逆の方向になりますので、古い銀行を救うよりも新しい銀行の創設ということをやっていただいた方が、効果はプラスマイナス逆転すると思いますので、いいと思います。
以上でございます。
○新藤委員 済みません。ちょっと時間が来てしまったのですが、最後に一点だけ、申しわけございません。
ただいまのお二人のお話を聞いていて、松田先生と川分先生、ベンチャーファンドというのはアメリカで一兆二千億の市場がある、対する日本が千二百億だということですから、とにかく我々もいろいろ工夫をしてやらなきゃいかぬ。今回、産業基盤整備基金とそれから中小企業事業団、これを合わせても二百五十億ですから、やはりこういうのは政府の金を当てにするのじゃなくて、いかに民間のお金を市場に巻き込んでくるか、これをやらなきゃいかぬ、今回はその支えるための施策だ、私はこのように理解をしております。
最後に橋本先生、実は今回の側面として、新しい中小企業をつくるんだ、概念を変えるんだというところまではすごくいいのです。ただ問題は、そういいながら、ベンチャーだとかそれから新事業だとか、そういうものばかりではないですよね。むしろ、九九・六%ある中小企業は、これまでのような、やはり下請だとか地場産業、これが圧倒的に多いわけで、こういう人たちに対する施策、今までは組合をつくったり業界ごとにいろいろな指導をする、ここからどう転換していったらいいのかというのが私ら今非常に苦しんでいるところなんです。
私の川口という地元が、中小企業集積率日本一の町なんです。そこはすべて下請と地場産業なんです。だから、こういう業界の人たちにどうしたらいいんだということを私どもはあわせて考えなきゃいかぬと思うのです。
そこで、総括的に、橋本先生、時間がなくて恐縮なんですが、御意見をいただければありがたいことだと思います。
○橋本参考人 御指摘の点は極めて重要なポイントだと思います。私が書いた短い文章がお手元に渡っているかと思いますが、中小企業というのは極めて多様な存在である。多様な存在で、それぞれが少しずつレベルアップできるというのが好ましいのではないかというふうに考えておりまして、今回の法案は、その上の方に近いところをいかにつくり出すかということを考えておりますが、御指摘のとおり、下請制が今大きく再編の場にさらされておりますし、それから地場の産地が国際的なマーケットとの連携がうまくいかなくなっているという例がたくさんございます。
それも、実はいろいろな情報通信の仕組みを支援するようなことをすればよみがえるという事例もございますし、あるいはコーディネーターがうまく入ればよみがえったという事例もございますから、そういう支援策が、今後金融のみならずきめ細かく行われていくことが好ましいのではないかと思っております。
○新藤委員 ありがとうございました。
1999.09.20 新藤議員の活躍で『予算満額獲得』市政初の快挙!
- 川口・鳩ヶ谷市の国庫補助要望が、初めて満額を確保した。過去、両市の要望といえば、良くて6割、中には3割という実績だ。今回は最高が街路の940%、また次世代対応型焼却施設、朝日環境センターも380%と軒並み数倍という予算を確保したわけだ。
- この背景には、地域選出の新藤議員の招きで、官僚クラスが続々と川口を視察。国家の対応が変わったからだ。次に、岡村市長、名倉市長と共に、ある時は、国へ出向き、ある時は、視察に招き、この地域への国庫補助の必要性を説明して回った成果でもある。
- 9倍という額に喜ぶ市がある陰には、要望の3割5割がやっとという市町村も。その差は、要望を的確に国家と担当省庁に届ける道を持ち、積極的に動いたかどうかの差だ。
- 29年間自前の与党衆議を持たず、国からも県からも冷遇され、国庫補助の活路を見出しにくかったこの地域。予算獲得は、新藤議員の誕生で、大きくはずみをつけた。
|
- まず国政の目を川口・鳩ヶ谷に向けさせるために、橋本総理に3回、小渕総理には4回の来訪を実現させた。他にも通産・農林・運輸大臣、党幹部、同僚議員、各省庁担当者など70人へ地元に招いた。
- 結果平成11年度予算において公園・河川・下水・区画整理は、川口市・鳩ヶ谷市とも100%要望通り。街路については最大940%、朝日環境センターも380%など。市の要望を超える国庫補助を市政始まって以来初めて実現させたことである。
- さらに工業振興のため、川口・鳩ヶ谷地域に産業集積法の地域指定を獲得。続いて工業等制限法の大幅緩和を実現。さらに商業振興のための大臣賞など、たった3年で川口・鳩ヶ谷を確実に変えた。
1999.09.20 より早く、より大きく、より確実に
●NHK跡地に市民運動広場開設!
上青木NHK跡地を活用したSKIPシティ事業が進んでいるが、この工事に伴い現在使用中のグランドが廃止に。利用団体からの要請を受け、NHKに強い
パイプを持つ新藤議員が交渉を行い、まだ事業化が決まっていない北側用地を川口市へ貸与し、市の管理する連動広場として利用できることになりました。平成
13年度にグランドが開設される見込みとなっています。
●JR・市内全駅にエスカレーターが設置!
川口・鳩ヶ谷市が利用する駅で、エスカレーターが設置されていたのは3年前まで川口駅のみでした。街のバリアフリー化が都市政策の柱と信じる新藤
議員は、当選直後よりJRに猛烈にアタック。西川口、蕨に相次いでエスカレーターを設置し、東川口には、上下2基の計画が実現しました。2001年までに
市内全ての駅に設置されます。
●大蔵省から公園の払い下げを!
今まで地権者の好意で市民に開放されていた元郷の池田児童公園。相続の発生で大蔵省に現物納税され、公園は廃止に。住民署名を受け、新藤議員が大蔵本省と交渉。川口市に払い下げとなり、公園は復活されることになりました。
●荒川河川敷に車の乗り入れが!
三領グランドは休日のたびにフル稼働ですが、車の乗り入れが禁止の為利用者は大変不便。利用団体の要望に、建設省は河川保護を名目に交渉が進みま
せんでした。相談を受けた新藤議員は建設本省と現地事務所双方と交渉を重ね、50台の駐車場整備と併せて乗り入れが実現しました。
1999.09.20 97'98'99 しんどう義孝 国政報告ダイジェスト
新藤議員が活躍した主な法案・外交活動
■PRTR法成立を導く[99.5]
地方分権への移行に関する政策では、市職員の経験を持つ議員として常に的確な指摘を。
商工委員において企業に化学物質排出量の報告義務を旨とするこの法案成立を担当した。行政担当窓口を市町村とする民主党の意見もあったが、市役所業務に精通している経験から「行政担当窓口は県単位が得策」と提言。野党側の学識経験者の賛同を得、野党合意を引出した。
■住民基本台帳法案、賛成派の旗手[99.4]
フジテレビの特集枠では、推進派代表としてコメント求められる
全国どこでも住民票の交付ができたり、資格申請や、年金手続きが簡素化され住民サービスの向上されるこの法案。しかも16省庁92事務が統一され、国の事務も大幅に省力化する。
しかし便利になる一方、国民のプライバシーの侵害が野党の議論対象となった。新藤議員は、地方行政委員会で質問し、新たに個人情報の包括的保護法の制定を提案し、野党の賛成を引きだすことに成功した。
フジテレビの特集枠では、推進派代表としてコメントを求められる。
■住宅ローン減税、子育て教育減税で、景気に活を[98.11]
税制調査委員として住宅ローン減税などを担当。大蔵省を相手に大激論。オオナタを奮った。
所得・法人減税をはじめ、小渕内閣は減税総額9
兆4千億円の減税を決定した。
その決定の舞台裏では、税制調査会での新藤議員など若手と、大蔵省側の大激論があった。大蔵省は、それ以前の国民との不平等性から減税反対を唱えたが、景気回復が緊急課題という新藤発言が流れを変えた。
新藤議員は調査会で『住宅ローン減税・子育て教育減税・企業のコンピュータ導入百万円まで一括償却』を主に担当。特に、住宅ローン減税は景気回復誘導のメイン政策と主張し、170万円の控除を580万円まで減税。今年度のマンション戸建ての購入を大胆に活性化させた。
■オウム対策新法の制定へ
川口にオウム真理教が進出したとの情報を警察からいち早く聞いた新藤議員は、警察庁、公安調査庁の担当者から、オウムの活動状況についての報告を受け、素早く行動を起こした。
新藤議員は、岡村市長を同行し、自治省、警察庁に要望書を提出するとともに、陣内法務大臣、木藤公安調査庁長官に直接会い、住民の不安を解消するための具体的対策を要望した。
引き続き臨時国会での成立を目指し、オウム対策新法案編成作業に取りかかり、現在最終段階に入っている。
■相続税・固定資産税の減税へ
今国民に最も不評なのは、世界一高い相続税と、地価が下がっても上がる固定資産税。昨年の小渕減税で、所得・法人税は先進国で最も低い水準まで下げた。
新藤議員は次は相続税と固定資産税に的をしぼり活動を開始した。まず大蔵・建設両省よりデータを集め、現状を把握。
さらに小渕総裁の再選に向けた政策立案チームに参加し、総裁公約として相続税減税を取り上げるよう提案。8月以降の新聞報道の様に今実現に向け党内作業が進んでいる。
固定資産税は、9月に党内に設立された固定資産税プロジェクトチームに志願し、現在取りまとめ作業の真っ最中。毎週の会議では、不況の中での国民生活のコスト軽減をと主張している。
■国連招待でアメリカへ[98.11]
マンスフィールド元駐日大使より小渕総理へのメッセージをあずかる。
国連の招きで『日米若手議員交流会』が国連本部で開催され、新藤議員ら超党派の7名が参加。安全保障やPKO等に関して積極的に意見交換が交わされ、マンスフィールド元駐日大使との会談も行なわれた。
■IPU会議(南アフリカ)出席[98.4]
会議の合間を縫って各国議員とのロビー外交。この写真はロシアの女性議員。
世界中の国会議員などが一同に介する『第99回IPU会議』が南アフリカで開催。新藤議員は日本代表として出席し、今回のテーマであった政治軍縮や女性問題をディスカッション。国際社会の中での各国議員の交流と情報交換という大きな意義を果たした。
■外務委員として硫黄島を視察[97.11]
硫黄島の慰霊碑へ。祖父・栗林大将の好きだったジョニ黒を供えた。
硫黄島は第2次世界大戦末期の激戦地であり、最高司令官・栗林陸軍大将の活躍は今でも有名な話。その栗林大将とは、新藤議員の母方の祖父。
「奇しくも国会議員として硫黄島を訪れ、玉砕した祖父に議員になった報告が出来たことに大きな感慨を」と新藤議員。
■エトロフ北方領土を訪問[97.9]
エトロフの民家に泊り、人々や子供との交流から、まず日本を知ってもらった。
沖縄北方領土委員として、橋本・エリツィン会談に先立ち、現地調査と下準備のため、北方領土を視察。現地民家にホームスティをし、島民との対話集
会などから、返還の可能性を模索した。行程は、根室港からエトロフまでは速力15ノットという小さな船で30時間という劣悪なものだったが、『アクセスこ
そ交流の基本』という新藤提案で今では高速艇に変わった。
■アフリカ議連にも積極的な参加を
ガーナ大統領候補。ジョン・クフォー氏一行が議員室へ
国連活動において、国の大小に関わらず各国は平等に1票を持つ。そこで今後の常任理事国入りも踏まえ、新藤議員はアフリカ各国議員連盟の全てに入
会。ちなみにアフリカ議連は国別に16の連盟があるが、新藤議員は『日本・モザンビーク共和国議員連盟幹事長』、『日本・ナイジェリア友好議員連盟幹事』
を務め、アフリカとの友好と協力体制の基盤づくりをしている。
マスコミで
■広域行政問題でラジオ出演[99.8]
国民の70%は都市住民。都市派の議員として地方への偏重を見なすべきと語った。
新藤議員の大きな柱の政策の一つに都市政策がある。今まで地方に、農業に偏り過ぎていた地方重点行政を是正し、不公平のない国民への還元を柱に『首都圏都市政策議員連盟幹事』『都市問題対策協議会主査』として活躍している。
この日は都市派の議員の代表として『文化放送・クローズアップ首都圏』に出演。作家でパーソナリティーの村野まさよし氏と都市問題についての討論をした。
■世界の釜本と名コンビ![99.3]
惜しくも韓国には敗れたが、新藤議員は大健闘のプレイを。
新聞各紙でも報道があったが、ワールドカップ共催『日韓国会議員親善試合』が国立競技場で行なわれた。
ワールドカップと同じユニフォームで、番号は年齢と同じ40を指定し、高校時代からの俊足を見せた。写真は釜本議員の名コンビネーション?
■テレビでテリー伊藤氏と大激論[98.7]
マスコミのイメージ操作を厳しく批判。生番組は大混乱に。
フジTVの土曜一番花やしきに新藤議員ら新人21人が生出演。総裁選直後のテーマは『小渕政権』。当時は支持率24.8%と低迷していた。冒頭で
テリー伊藤氏は、「議員の皆さんは国民の意見も聞かず、小渕さんみたいの選んじゃって、呑気というか、面の皮が厚いというか…」と先制攻撃を。
それに対して新藤議員は「そうやってマスコミが間違った前提をつくり、先に色をかけるのは止めてもらいたい」と厳重抗議。この一言から生番組は騒然。後のコーナーが2つ飛ぶほどの混乱になった。
しかし今、小渕政権は国民の支持率50%を超え、安定した政局運営を。あの時のテリー氏のうがったイメージ操作こそ間違っていたと、時間が答えを出した。新藤議員の面目躍如だ。
特定化学物質の排出量の把握・管理の改善に関する法律案(質疑)衆議院商工委員会-12号 1999年5月14日
特定化学物質の排出量の把握・管理の改善に関する法律案(質疑)
145-衆-商工委員会-12号 1999年05月14日
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
今ちょっと頭が混乱しておりまして、四人の専門の方から大変にそれぞれ意義ある御意見をいただいたわけでございます。順次質問させていただきますが、私も専門ではございませんので、もし言葉の言い違い等があったら、しんしゃくしてお酌み取りいただければありがたい、このように思っております。
そもそも化学の物質の分野でございますから、なぜそれが商工なんだ、こういう話があるわけなんですが、私は、これからの産業活動というのは、環境にどう適応させていくか、それをどう産業活動に取り込んでいくかということが最も大事なことである、それが世の中を便利にすることである、生活の利便性を向上するとともに、やはりそれが生活の一番根幹をなすところになるだろう、こういう観点で、これはもうぜひ私どもで取り組んでいこう、このように思っております。
しかも、いろいろ資料を調べますと、化学物質と言われるものが世界じゅうに千八百万種もあって、我が国では五万から十万種のものがある、そして、年々数千種ずつふえていっているんだ、こういうような、もちろん、我々の周りは全部化学物質で囲まれているわけなんでございます。しかし、それに対して、規制をすべき化学物質というのは数十物質しかない。それ以外のものについては、どこで何が使われているのかわからない。私は、これは本当に不思議なぐらい、今一体日本で、いい悪いではなくて、化学物質と言われるようなものがどれぐらい使われているのかというのを把握していないこと自体が不思議だったなと、私たちの世代から言わせていただくと。だから、これは非常に意義あることだろう。しかも今回のは、規制に至らない化学物質を、その排出量を把握するとともに管理の改善をするんだ、まさにここに私は今回の法律のコンセプトがあるのではないか、こういうふうに思うわけなんでございます。
ちょっと時間がございませんので、そういう中で、これはもうぜひ推進すべきという観点から、各参考人の先生方にお話を聞かせていただきたいと思います。
まず、産業界で中心となってお取り組みをいただきました寺門参考人さんにお尋ねをいたします。今回の案でいきますと、PRTRの実施が、二〇〇一年の排出量を二〇〇二年の夏までに届け出よというのが一番早いスタートかな、こういうふうに思うのでございます。二年半です。しかし、これは全然今までそういうことを考えずにやっていた産業者が、特に中小企業者がこれに対応していくというのは、届け出事務の手続から、化学物質の計量、推計、そういう作業をしていかなければいかぬ。これはかなり負担がかかるのかなという気がするのですが、それについて産業界としてはどんな要望があるか、この制度の実施に際しての産業界からの要望があれば、お聞かせいただきたいと思います。
それと、さらに、インターネットの活用、私は、こういうものはもうどんどん電子申請をすべきだと思っておりまして、各事業所が共通フォーマットのもとで、例えば、インターネットを使うと自動計算してくれますとか、数量をこことここに入れれば自分たちで計算しなくてもコンピューターが計算してくれる、そういうソフトを国が無料でフリーダウンロードしてあげればいいのですね。それで、事業者にこれを使ってくださいと、そうすれば、国の方も一発で計量できてしまうわけですから、そんなようなことを使った方がいいのではないかと思っておりますが、産業界でそんな意見があるのかどうなのか、ちょっと状況を教えていただきたいと思います。
さらには、データの取り扱いでございますが、住民、関係者との理解を深めるというリスクコミュニケーション、これはよその国の法律では入っていない規定だそうでございますね。ですから、こういう新しいリスクコミュニケーション、まさに企業の自主的な取り組みを促すんだ、こういう観点で入れたということなんですが、この辺、実際、事業者とリスクコミュニケーションとの責務の関係はどんなふうにお考えになるかということを、あわせてお尋ねをしたいと思います。
それと、届け出だけじゃなくて、今度は情報公開のときもインターネットを使った方がいい、行って来いでやった方がいいなと思っているのですけれども、その辺も産業界での御意見があれば、お聞かせいただきたいと思います。
○寺門参考人 今三点ほどの御質問がございました。
最初に、二〇〇二年の夏にデータが出てくる、その期間にどんな努力が要るのかということだと存じますが、一昨年、私どもは自主的なPRTRをやったわけですが、先ほどもお話があったように、それは大企業だけじゃないのかというお話もあったわけでありますが、それでもなお大変努力が要るわけでございます。
実際にデータをとるマニュアルといいましょうか、そういうものを決めて、そして、各発生のプロセスに応じたマニュアルというものを一つずつつくり上げて、そこから出るデータをサムアップして、それで正しいかどうか、そういうものをつくり上げていって、初めてそのデータが最終的にまとまってくるわけでございます。
中小企業の方々にとりましては、それぞれの企業によりましてやっている作業の内容が大変違いますから、それにマッチするように自分たちで考えていかないとできないわけでございます。そういう意味では、十分なマニュアルというものをつくって、その理解活動というものを進めていくということが必要であるわけでございますので、二〇〇二年に百点満点がとれるかということになりますと、とれないということも、またこれは逃げでございますけれども、とれるように努力するということしか申し上げられないわけですが、中小企業の方々にとりましては、大変負担のかかることであるということだけは申し上げさせていただきたいと思います。
それから、インターネットの活用についてでございますが、私どももインターネットの活用というものを通じてでないと、この作業というものはできませんし、データの集計もできませんし、膨大な資料をだれが見るのかということも、これは結局限られた人になってしまう。やはりインターネットの中から選択されたデータというか、自分の意思で選択できる、これは地方公共団体の方々にとりましても同じようなことだと思いますが、インターネットの活用というものがぜひ必要でございます。これらも、どのような形でインターネットを構築していくのか、今後十分検討していただきたいと思います。私どもも、それに早くマッチするような方法を早く事業者の方に伝達して、みんなでやろうというふうに取り組んでいきたいと思います。
それからリスクコミュニケーション、これは常にPRTRの制度の導入のときから議論があったものでございます。この中で、私どもは、データを出せばいいという問題ではないわけで、そのデータの意味といいましょうか、そういうものをやはり理解していただくというコミュニケーションというものは非常に大事でございます。そういう意味では、地方公共団体の方々とともに、地域の方とやはり我々は前向きに円滑な情報交換といいましょうかそういうものを進める、これはやはり自主的に自分たちでやるという、隠すという意味での意思ではなく、自分たちでやっていく。
しかし、ここには限界があるわけでございます。この物質の、常に言われております健康等への影響のおそれ、そのおそれというものは言葉では簡単でございますが、定量化がなかなかできない。そういうところでは、やはり心を通じていくということしか結局ないわけでございます。そういう意味では、信頼関係を確保しつつやっていく、こういうことだと思いますので、私どももこのPRTR制度ができます前から、そういうことを志してまいりたいというふうに存じております。
以上でございます。
○新藤委員 ありがとうございました。
恐らく中小企業者に対しては何らかの技術的な支援ですとか、金融関係の制度も充実させていかなければいけないのかな、こういうふうに思っておりますので、そういうときはどんどん私どもにまたお申しつけいただければ、ありがたいと思っております。
ちょっと時間がございませんので、申しわけございませんが、引き続きまして、浦野先生にお尋ねをしたいと思います。
浦野先生の御主張というのはかなり明確なものがございまして、国の一元管理、国に集約させるのではなくて地方自治体をもっと使っていくべきだ、幾つもお話がございましたが、私はそういうところがまず一番ポイントだなというふうに思いました。
実は、私は市の職員だったんです。これをやったことがあるんです。埼玉なんですが、地元の市会議員もやったことがあります。そういう自治体のこともよくわかっているつもりなんですが、一番恐れるのは、やる気のある自治体、それからできる自治体と、そこまでなかなかできない自治体がある。三千三百、自治体があるわけです。それで、先生がお話をされたように、情報が確実で正しくなければ意味がない。だから、一律のレベルで集まらないと意味がないんですね。それから、全国津々浦々にPRが難しいんだよ、こういうお話がありました。
そうすると、それは逆に、まさに熱心な地域がばかを見るのは、あってはならないことです。でも、不熱心な地域がもしあったとして、そこの不熱心な地域の不熱心な自治体によって、それがもし発生してしまったら、これは逆説的な話になっちゃいますが、かえって危険になるのかな。ましてや、パイロットプランをやったときにも、なかなか趣旨が徹底していなかったというようなお話もございました。
であるならば、別にこれは国にやらせておいて、自治体が知らぬ顔をするということではないと私は思っているんですね。また、そんなことをさせるつもりはありませんし、データは一元的に国が集めるんだ。しかし、それをそのまま丸ごと自治体に出しちゃうわけでしょう。だから、そこで自治体にしっかりと、もし危険があったり、それからモニタリングをしなきゃいかぬ、さらに追跡調査をしなければいけないとか、そういうようなことが発生したら、それはそこで自治体にやらせればいいのじゃないか。
むしろ逆に、今度は資料の収集、データを一元管理するという観点からすると、自治体ごとでまとめられちゃうと、市役所でまとめました、はい、それを県庁に持っていってください、県が、また四十七都道府県集めて、それを国になんというようなことをやったら、時間がかかっちゃってしようがないのじゃないか、私は逆にそんなふうに思っているんですね。だから、この制度は国も県も市も全部同じ立場でやらなくちゃならないんです。させなくちゃならないんです。ただ、その手続というか窓口、どういう流れをつくるかということを私は思っておりますから、その辺、先生、もしお考えがあったらどうかなと。
ごめんなさい。本当はちょっとやりとりをしたいんだけれども、時間がないんだ、もう終わらなければならなくなっちゃうから。
それと、あともう一つ、中小企業でたくさんの物質が出ている、こういうお話がございました。であるならば、これは大変な問題だと思うんですね、中小企業の皆さんは五人とか十人とかでやっているんですから。そういうところに今度は新しい制度をかけて、あなたたちはやっていることをちゃんと報告しなければいけないんだと。
そうすると、先生、逆にこの中小企業の皆さんに、どんなお手伝いを国なり我々はしなくちゃいけないのか、対策は。中小企業に必ず出させろ、出させなければだめだよというお話もわかるけれども、逆に、では、そういう企業に出してもらうためにはどんな対策が必要だとお考えになるのか、もしあったら、参考に教えていただきたいんです。
○浦野参考人 ただいまの御質問は大きく二つあったと思っております。自治体の関与の件と、中小企業の支援の件だと思っております。
私は国に一元化することに反対しているわけではございません。現在の政府案では、事業所管官庁ということで非常に窓口が多くなっている。事業者は特に多業種になっておりますし、業種も、業態も非常に変化が激しくなっております。今回のパイロット事業でも、この業種ということで報告を求めたところ、一割が業種が違っておったという事実もございます。そういった中で、少なくとも国でも窓口は一ないし二省庁に絞るべきであるというふうに私は考えております。
それから、自治体に出すという場合に、民主党案では市町村を経てという形になっております。私は、おっしゃるとおり、少し市町村は無理だというふうに考えておりまして、都道府県レベルで集める、あるいは事業者が、アメリカのように、そのほかの国のように、同じものを二つ国と都道府県に出すという形も、これは弁護士会が提案している案でございますけれども、非常にいいのではないか。都道府県が国と市町村との間に入るということは、非常に有効であるというふうに思います。
先ほど来話がありました、非常に熱心に取り組むところと、そうでないところがある、これは私も非常に心配しております。
自治体というのは、熱心なところはどんどんやるから問題ないのですが、熱心でないところをどうやって動かすかといいますと、一番は、法律的に何らかの責務や権限が与えられると、自動的にそのようなセクションができて対応するのでございます。それが不明確ですと、やる、やらないが非常に差が出るということで、地域で問題を生ずる。ですから、都道府県レベルには少なくとも、もう少しきちっとした権限あるいは責務をつけるべきだ、それが私の主張でございます。
それから、自治体に情報が行けば当然やるのではないか、やらせなければいかぬということになるわけですが、今の政府案で自治体がもらったときに、果たしてどこが自治体にやれと言えるのか。あるいは、自治体が企業者に何かを言うときに、どういう権限で言えるのか。あるいは、間違いがありそうだ、報告をしてなさそうだというときに、どうやってそれを言いに行くのか、調査しに行くのかというと、できないわけです。
それは、自治体が環境庁ないしは事業所管官庁にまず問い合わせをしなきゃいけない、問い合わせをしたらどういう返事が来るか、その先わからないわけですね。それでは自治体もちゃんと動けないのではないか。もちろん、動くところは動くのですが、動かないところは動かないだろう、そこを非常に心配しているというのが事実でございます。
それから、中小企業についてでございますが、中小企業といいますのは、この制度は、一応従業員数あるいは化学物質の取扱量で、すそ切りという形を多分行われる、パイロットでもそうでございます。ですから、非常に小さいところは直接報告をする必要がない制度に多分なる。
しかし、すそ切りより上ではあるけれども、小さいところで知識のないところというのは当然あるわけですから、そういうところに対して、当然、業界あるいはその他で指導もされると思いますが、きめ細かな指導や助言、手助けをするのはやはり地元自治体であるというふうに私は思っております。その自治体がまずレベルが上がって、その上で中小者にもいろいろな支援をするということが、自治体自身も予算をとったりしてやらなきゃいけないと思うのですね。そういった根拠をつくることが非常に重要であるというふうに私は申し上げておるわけでございます。
○新藤委員 ありがとうございます。
本当は、もう少しお話をやりとりした方がわかってくるのかなと思いますが、先生のお考えも大体よくわかりました。ただ、私は、一点、自治体に法律を課すことによってやらせる、やるようになりますよというのは、まさにそうだと思うのです。ただ、それは限りなく規制法に近づいていってしまう、こういううらみもあるような気がするのですね。ですから、自主的な改善を促すという意味からすると、かなりの工夫をしなきゃいけないものはあると思います。どちらがということではないと思うのですが、結局、仏つくって魂入れずでは意味がないということですから、これはきっちり我々も監視していきたい、このように思っています。
申しわけありません、山下参考人さんには、お尋ねしようと思っていたのですけれども、ちょっと時間が、私が長話をしちゃったものですから、足りなくなってしまいました。自治体として、とにかく、これは国が所管になるからではなくて、まさにパイロットで御苦労いただいた先達として、逆に国がこういう全国データベースをつくるのだから、それを生かして、いかに地方自治体がしっかりと取り組んでいくか、これの先頭の旗振り役になって御活躍いただきたいと思います。
最後に、近藤先生にちょっとお尋ねをしたいのでございます。それも、一点だけ申し上げさせていただきたいと思います。
いろいろとこの法律についても御検討いただいて、随分と詰めていただいた、御苦労いただいたというふうに思っておりますが、この専門家として、今回の話が、事業者と、国であり市町村であり行政と、市民もしくは市民団体、きょうも御関心ある方がこうやっておいでいただいておりますが、この方たちが心配をして、どうしようか、こうしようかとやっております。でも、そもそもこの化学物質が安全であるかどうか、それともその危険性がどの程度影響が出てくるのか、ここの部分を決めるのは、事業者でも行政でも市民団体でもないのだと思うのですね、やはりこれは科学界のことですから。ですから、基礎研究なり科学的な研究にしっかりと取り組んでいく必要があるのじゃないか。それが、きちんとした指針が出れば、何も皆さん心配することなく、そして危険も未然に防げることもあるということだと思うのです。
そういう意味で、先生は第一人者で御活躍いただいております。ですから、逆に、今、国の体制で、こういう化学物質の研究をするときに、もし必要だ、またこういうものをやってほしいんだというような御要望がありましたら、ぜひこれは政治の場に、我々に入れていただきたいのです。
日本の産業がこれから世界に伸びていくために、環境問題に適応できなければ死活問題になります。ですから、そういう意味でも、逆に今度は学術的な研究にももっと金を出したっていいじゃないかと僕は思っているのですけれども、その辺で先生方からの御要望があれば、これはぜひお聞かせいただきたいと思います。
○近藤参考人 ありがとうございます。
今おっしゃいましたこと、前半に関して、全く同感でございますし、後半に関しましても、ぜひお願いを申し上げたいと思います。
こういう化学物質の問題に関しまして、一番大事なことは、正確なる科学的知見を得るということでございます。それをもとにして論議がなされるべきである、こう考えておりますので、その科学的知見をより多くの化学物質に関して、より詳細にこれから決めていかなくてはならないと思います。
そういう意味におきましては、大学研究機関、それから政府の研究機関その他いろいろなところで協力をして、いち早く化学物質の毒性、生体影響あるいは人に対する被害、影響といいますか、こういうものを突きとめていただきたいと思いますけれども、研究費というのが何しろ足りませんので、非常に皆さん難儀をしておられるというところで、各省庁の機関でもそうだとは思います。
それからもう一つは、環境モニタリングというのはぜひ必要になってまいります、その毒性等に応じての話でございますね。この環境モニタリングは、環境庁が大いにやっていただいておりますけれども、一件に対する費用というのは大変たくさんかかりまして、年間の調査物質が数少ないわけでございます。したがって、もっと数多くこれが検討できるような予算配慮というものはぜひ必要かと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
○新藤委員 では、質疑時間が終了しておりますのでこれで終わらせていただきますが、今のお話ですと、要するに政治の場に求められているのは予算だ、こういうことだと私は思っておりますけれども、商工委員長、これはぜひ皆さんで相談して、しかるべきお手伝いをさせていただきたい、このように思っております。
大変ありがとうございました。
住民基本台帳の一部改正法律案(質疑)衆議院地方行政委員会-12号 1999年4月20日
住民基本台帳の一部改正法律案(質疑)
145-衆-地方行政委員会-12号 1999年04月20日
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
地方行政委員会には初めてお邪魔をさせていただきまして、質問させていただくわけでございまして、どうぞよろしくお願いをいたします。特に、野田大臣には初めてお目見えをさせていただきます。大変アグレッシブな方だと私は尊敬しておりますので、私が今回質問させていただく中でこれはと思うことがあったら、ぜひ御答弁いただければありがたいと思っております。
ただいま、滝実先生の明治時代からさかのぼることの歴史を踏まえた格調高い専門的な御質問があったわけなのでございますが、私は、これから先の将来の日本の情報化、こういう観点から今回のこの住民基本台帳の法改正をどうとらえていくかということで、御質問させていただきたいというふうに思っております。
いろいろなところで、行政もそれから政治家も含めて、二十一世紀の社会のキーワードは何かということになると、必ず出てくるのが高齢化社会とそして情報化社会だ、こういうことになっています。そして、閣議決定を何度も繰り返しまして、この住民基本台帳はもう既に平成九年の段階でやるんだというふうに決まっているわけでございますね。そして、政府の方でも、高度情報社会推進本部において、去年の十一月に基本方針をきっちりと決めているわけなのです。しかし、私の思うところ、我が国の情報化というのは思ったほどに、期待しているほどに進んでいるのかな、こういう気がするのでございます。
先進であるアメリカなんかと比べましても、これはもうどんどん離れているばかりなのですね。インターネット利用は、アメリカが六千二百万人、日本は一千四百万人でございますし、人口一万人当たりのホスト数、これは日本は世界で二十三位なのですね。世界一の通信技術、コンピューター技術を誇る我が国が、自分のところでつくっているのですが、しかし、どれだけ使われているかというと、ホスト数においては、シンガポールが十三位、香港が二十二位、そして日本はその次になっている、こういうような活用状況でございます。それから、電子商取引がこれから拡大するんだ、拡大してきたといっておりますが、アメリカが二十一兆円、日本はまだ八兆円だ、こういうことになるわけなのです。
ですから、なぜこれが進まないのか。私の考えるところ、率直に申し上げますと、便利でないのですよ。結局、自分の生活や仕事にみんなが使えるような創意工夫をしていかないと、ただ見るだけだったり、それからデータが集まってきたものを集計するだけ、そういう状況ではなかなかこれは普及が進んでいかないというふうに私は思っているのです。
ですから、そういう意味で、今回の住基台帳法の改正が、まずは行政の効率の向上、それと住民の利便性が上がるんだ、こういうことで私は大変歓迎しておりますが、これとあわせて、情報化を進めていく中で、今回の住基台帳のネットワーク化、これは自治省、どういう取り組みをされるつもりなのか、今のお考えを聞かせていただけるとありがたいと思います。
○野田(毅)国務大臣 幾つかの論点が指摘されたと思うのです。全体として、日本の社会全体の中で、高度情報化社会に対する対応が、世界的なレベルで見て、非常に本来のあるべき姿よりもテンポが遅過ぎるのではないかという、そのことに対するトータルとしての危機感といいますか問題意識というものが指摘されたわけであります。
この点は私も全く同感でありまして、これはそれぞれのミクロの企業レベルにおいても、あるいは、場合によっては学校における子供のころからのそういうような教育の内容そのものにおいても大事である。シンガポールなんかは日本よりもはるかに小さいころから学校教育の中で徹底してそれをやっているわけで、そもそも民族の繁栄というのは進取の気性ということが非常に大事なことであって、このフロンティアの部分をどう育成していくかということが一つの大きなポイントだと思います。
それから、自治省において、情報化に向けてどのような取り組みを行ってきたか、あるいはまた、おるのかというようなことでございました。この点につきましては、地方公共団体における情報化というのは、地域住民の福祉の向上や、あるいは地域の活性化を図るとともに、新しい行政ニーズへの対応あるいは行政事務の一層の高度化、効率化を図るということを可能にするものでありまして、セキュリティー対策や個人情報保護に十分留意しつつ積極的に推進をしていかなければならないというふうに考えております。
そこで、このために、自治省では、地方公共団体に対して、既に地域の情報化の推進に関する指針及び行政の情報化の推進に関する指針というものをお示しいたしておりまして、各地方公共団体における情報化を積極的かつ戦略的に推進をするように要請をいたしております。同時に、地方債及び地方交付税による財政措置により支援をいたしておるというところでございます。
○新藤委員 ありがとうございました。
それで、とにかくこれを進めていく、どんどん進めていくべきだと私は思っておるわけなのですが、しかし、そのときにやはり留意しなければいけないのは、盛んに新聞等でも言われておりますが、やはり国家の一元管理、権力の乱用が行われるのか、こういう危惧があるという声と、それから、そもそも個人情報が保護されるのか、こういう部分が今回の改正の一番の課題になるのではないかな、こういうふうに思うのです。
そして、ただ、私の考えですけれども、今回の住基台帳ネットワークができることによって、個人情報が漏れるなり、勝手に使われる、流用されるおそれが増す、こういう心配があることについては、私は、逆じゃないかな、こういうふうに思っているのですよ。というのは、結局今回のネットワークをやるということは、これはもう最先端のセキュリティー技術、それから暗号技術、こういうものを徹底的に工夫する、それからまた、実際運用上においても随分の工夫が、やり過ぎかなというぐらいに私は思うのですが、工夫が入ってきている、こういうふうに思っております。
現状で、むしろ個人情報保護法というもの、これは今国家行政機関の情報だけはその保護法によって制約がありますが、民間情報それから地方公務員に関しては、その情報を守りなさいという法律すらないという今の現状の中で、社員名簿だとかそれから顧客リストの流出だとか売買なんというのはむしろどんどん横行してしまっているわけなのです。
だから、私は、今回この住基台帳のシステムをきちっとするところで、まずシステム設計、セキュリティーを徹底的なものにする、それから職員の教育と罰則、こういう法令に基づく制約をかけていく。しかもこれに加えて、例えば住基台帳のデータを個人で、ICカードを持ってもらう、こういうことになったとすると、このICカードというのは極めて偽造だとか不正使用ができない、今のところ一番難しい、要するに今セキュリティー度が一番高いわけなんですね。
紙なんというのは、だれか持っていっちゃえば済むわけなんですが、自分の複雑な番号をもってしては、他人様がそれを知ることはできないんですよね。そうすると、例えばこのICカードをしっかりと運用していくと、むしろ今までデータがとれたはずのものがとれなくなってしまう、そういうふうに考えたらどうかなというふうに思っているのでございます。
それで、今回、本法改正におけるネットワークのシステム、それからルール、こういうものがどのように検討されているのか、工夫されているのか、ちょっとさわりで結構です、時間がだんだんなくなってきますので。
国の一元管理の問題は、先ほど滝先生が御質問されました。私も御答弁に納得しております。国がやるのではなくて、国がいわゆる公益法人をつくって、そこの中で委託、県と市がやるんだよ、こういうことでございますから、納得しておりますので御答弁は結構でございます。
○鈴木(正)政府委員 この住民基本台帳のネットワークシステムにつきましての、特に個人情報保護面での配慮措置ということでございますが、先ほど申し上げましたように、基本的には国際基準を踏まえまして、法律上、技術上、十分な保護措置を講じるという考え方で構築をしてきております。
例えば、制度面での保護措置といたしまして、本人確認情報の提供先、あるいは利用目的については、法律で明らかにして規定するということといたしております。また、本人確認情報を取り扱う関係者、市町村、県、全国センター、あるいはそれの電算処理を委託される機関等に対します安全確保措置、これを義務づけております。また、従事する職員の秘密保持の義務づけも行っております。
また、本人確認情報の目的外利用の禁止ということを法律上明らかにしております。民間部門での住民票コードの利用も禁止しております。そういうことで、公的部門での利用ということにいたしておるところでございます。
システム面の保護といたしましては、これまでの全国的なシステムというものの実績の上に立って、それにまさるとも劣らない内容のセキュリティー面の配慮措置を講ずることといたしているところでございます。
○新藤委員 このICカードは、別に持ちたくない人は持たなくてもいいということになっているわけなんですから、そのメリットを感じる人がお持ちになるということでございまして、別に全員に持たされるということでもないんですから、問題ないんじゃないかと思うんですよ。
ただ、きょうは御答弁はいただきませんが、むしろ個人情報保護法というものをしっかりと包括的なものにしていく、これは絶対やらなきゃいけないと思いますね。むしろ、国だけになぜ外しているのかというのが私不思議なんですが、これはやらなければだめだというふうに思っております。
それから、次のポイントとして、今回の課題としては、個人情報の保護と国の一元管理を、権力の乱用を排すということだとすると、逆に今度は、今回の法改正のポイントとしては、とにかく全国人口の九九%がコンピューター処理されているこの住基台帳を自治体間でネットワーク化させること、これによる物すごい行政事務の効率化が行われるということだと私は思っております。
要するに、今までは自分の住んでいるところでなければとれなかった住民票が、勤務先のどこでもとれるし、それから転入転出の際は一回で済むんだ、こういうようなことでございます。
それで、これに加えて、ほかの行政機関がこの住基台帳にアクセスすることができるようになれば、これは住民票をとるだけじゃなくて何かほかの、その個人が例えば雇用保険だとか労災給付、それから恩給、共済年金支給、建築士免許、宅建資格、こういうものを登録するときの申請に、一々住民票をとりに行かなきゃならなかった。それが今回は、役所同士で連携をとってくれて、個人としては自分は本人なんですよと申請をすればそれでいい、こういうことになる。非常に便利になるんじゃないかなというふうに思うんです。
これはかなり工夫をして、さっきのお話ではたしか十六省庁九十二事務ございましたね。こういう話ですから、便利になるということで、答弁してもらおうと思ったんですけれども、時間がもったいないですから、それはもう結構なんです。
それで、私、これに加えて本当は考えていただきたいのは、今回民間利用を禁止しております。言いかえれば、個人が行政のデータに直接アクセスすることはできない。民間の商行為ではなくて、一市民が私はアクセスしたいんだといっても、アクセスできないことになっているわけなんですね。そこが実は大変なポイントになってくると私は思うんです。
今回、状況として踏み込めないというよりも、考えていないということなのかもしれないんですが、二十一世紀型の高度情報化社会というのは、一々自分が足を運ばなくても、自分のコンピューターで、または自分の認証されたICカードでいろいろなコンピューターのネットワークにアクセスできることで、初めて飛躍的な高度情報化社会が訪れる、こういうふうに思っているんです。
例えばどんなことができるかといえば、自分のうちのパソコン、もしくはカードを持って駅のキヨスク、売店だとか、それからコンビニエンスストアなんかにそういう端末があったとします。そこで住民票をとりたいんだと、そうするととれちゃうんですよね。とれることになるんです。それから、介護保険の手続だとか、そんな検索なんかも自分でできるようになりますし、いよいよ始まりますけれども、高速道路で、有料道路のところにITSというのですか、自動料金算定装置、これも、自分のカードを出せば全部それでもって決済できるようになるわけなんですね。
だから、結局、今日本の情報化が進まない最大の原因は、さっき一番最初に申し上げました、使える情報処理ができないんだ、役に立つものがないんだ、少ないんだというお話をしましたけれども、ここの部分だと思うんです。
それで、アメリカはパソコンが家庭において半分以上普及しております。日本はまだ二割行っておりません。この最大の原因は何かなと調べました。そうしたら、アメリカは総合課税制度になっておりまして、源泉徴収もありますけれども、個人が申告するんですね。それの申告ソフトが、物すごく使いやすいソフトが普及しておりまして、だから、みんな税金の申告をするためにパソコンを買うんですよ。それから、アメリカの大学生は宿題はEメールで出るんです。ですから、大学に行って、パソコンができない者は宿題を出せないんです。だから、それを子供のころからさわらせて教育させる。自分と一対一でやっているんですよね。
だから、ちょっと住基台帳から離れちゃっているように聞こえるんですけれども、結局、そういうすべてのネットワークを、この九九%がコンピューター処理されている日本最大のネットワークを使って、それを民間利用と個人利用をさせることでこの情報化というのは物すごく普及する、こういうことになってくる。
それで、例えば教育問題。教育現場にパソコンを入れろというので、日本の方針ですと、平成十二年度までにすべての学校に、それで十五年までにすべての小学校に、十三年までに中高ですね。これはすごいなと思うんですけれども、アメリカは二〇〇〇年までにすべての教室、学校ではなくて、そして十二歳以上のすべての生徒なんです。日本は学校ですよね。片や世界の国は、教室、もしくは十二歳以上になったら一人一人に持たせるという、この差なんです。この差が恐ろしいんです、どんどん。
だから、そういう意味で、私は、今回の法改正に盛り込めという気持ちはありません。ただ、今回あえて民間利用を禁止した、セキュリティーだとか権力の乱用だ、そういう不安のもとに禁止した部分、将来のことを、取り組み、お考えを聞かせていただきたいのです、どんなふうに考えるか。
○鈴木(正)政府委員 率直に申し上げまして、現在、この新しいシステムの法律を通していただきまして構築するということに精力を注いでおりますので、今お話しのように、現在考えている内容は、民間については利用を規制するという考え方でございます。
将来のあり方でございますけれども、お話しの、民間の商業部門で使うということでなくて住民の方がアクセスするという問題でございますが、行政分野で申し上げますと、行政のいわば申請とか届け出等の行政手続面でオンライン化を進める、その場合に、認証のシステムとしてこの新しいシステムが使えないかどうかということだろうと思います。
お話しのように、市町村の区域、県の区域を超えた全国的な本人確認のシステムでございますから、そういうものを認証システムとして利用可能性があるのかないのかということは、この制度が動きまして、あわせまして、そういったことも検討課題として考えていかなければならないだろう、こういうふうに考えております。
○新藤委員 現状では、今のところ、この法律をまず始めることからだ、このように思っておりますから、私もそれは重々承知をしています。ただ、大臣、これは自治省の仕事ではなくて国家全体の情報化を進める上で多分極めて大きなポイントになってくるはずなのでございまして、これはぜひ頭にお含みおきいただいて、そして将来に向かって検討していただきたいな、このように要望をしておきます。
それからもう一つ、先ほどからどうしてもネットワークというよりもICカードの話が多くなってしまうのですが、この住基台帳ネットワークに伴ってICカードを入れることで、もう一つ別の利用可能性が広がります。これは要するに、この住基台帳ネットワークに入っていって使うのではなくて、それを持っていることによって個人認証がしっかりできるということによって、ほかの仕事に使えるわけなんですよね。
要するに、本人が自治体から発行されたカードを本人と認めてもらいたい相手に渡して、そして自分が本人であることが間違いないと認証されれば、住民票要らないよ、こういう話ですね。パスポートだとか免許証だとか、いろいろあります。少なくとも紙なんかより全然安心なわけですよ。だから、こういうことで非常に私は有効だなというふうに思っております。ましてや図書館で本を借りるときだとか、それから、この間ちょっと実験をやりましたが、電子投票ですね、こういうものをやる上でも、これはぜひ本格的な導入を実施すべきだ、こういうふうに私は思っているのです。
ただ、諸外国でいろいろもう行われています。日本はこの件に関しては後進国なんですが、お隣の韓国で、何かこのICカードの取り組みでこれまでの方針を撤回するというような週刊誌の記事が出たり、それから御視察いただいた方もいらっしゃるようですが、そういう情報が聞こえております。これについて、自治省としては、韓国の問題、どういうふうに分析されているのか、わかっておる範囲で教えていただきたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 韓国におきましては、ICカードの利用ということで、それは、偽造、変造を防止し、情報化社会に対応した多目的な身分証とするということで、現在、紙製の住民登録証がございますが、それをICカードの電子住民カードとするための法律改正を平成九年十一月に行いまして、成立しました。その後、韓国の厳しい国家財政にとって相当の費用を要するという点、それから二つ目は、国民監視が強化されるのではないかという不安に基づく反対運動が強まったということで、電子住民カードの関係条文の削除ということを内容とする改正法律案が議員立法で国会に提出されたというふうに聞いております。
この電子住民カードは韓国の住民登録制度の一環でございますが、日本とはかなり住民登録制度は実情を異にいたしております。
韓国におきましては、全国民について住民登録番号をもとにして多数の情報が住民登録ファイルとして管理されておりまして、その情報が行政、民間を通じてさまざまな分野で利用されている。また、満十七歳以上のすべての国民は常時住民登録証を携帯するということが義務づけられております。この住民登録証につきましても行政、民間を通じて利用されている、こういうことでございますので、制度のもとが大分違います。
住民基本台帳ネットワークシステムの方では、これまでもお話ししましたが、保有するデータは住民票コードと四情報、氏名、住所、性別、生年月日及び付随情報のみであるという点、また、国の機関等へのデータの利用、提供については法律上明確な根拠が必要である、また、目的外利用というものが禁止されている、それから、民間部門による利用が禁止されている、また、住民基本台帳カードは住民サービスの向上の観点から希望者にのみ発行するといったことで、韓国の住民登録制度及び電子住民カードとは異なっている、このように考えております。
○新藤委員 まあ、韓国、経済危機が深刻でございますから、そういう側面もある。そしてまた、国の一元管理、権力の乱用が心配だ、これは私に言わせれば、もう極めて感情論である。このことをやると悪いことをしてしまうからやらないよ。悪いことをしたら罰する、悪いことをさせないように工夫をする、それが知恵を使うということであって、物理的にこういうものをつくらなければ悪いことがないんだと。
ところが、どんなことをやったって、なければないなりに、今は個人情報なんというのはむしろ横行してしまっているわけなのですから、だから、骨太の議論をしっかりすべきだ、感情論でやってもらっては困るし、私もそんなことをもし国家に管理されてしまったら困りますから、そういうことをやられないようにルールをつくり、法律をつくるということなのでございます。
韓国と日本は違うのだということがよくわかったわけでございます。
そして、最後の質問にさせていただきますが、結局、システムとルールをきちんとすればこれは問題なく運用できるではないか。しかも、先ほどから御答弁が繰り返されているように、四情報に限ってとか物すごい制約をかけてしまって、本来ならもっと使える、国の基幹、根本を変えられるような、産業の活性化も含めて新産業の創出も含めてできるはずのものを縛ってしまっているわけなのですけれども、将来の話として、これを国民総背番号制だといって反対されている方がいる、こういうことも聞いております。
ただ、背番号制とは、確かにそれは全員に番号をつけるわけなのですが、しかし、広い意味でこういうものはさっきの韓国だってもう昔からですよね。含めて、アメリカ、カナダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、イタリア、オーストラリア、ほとんど使ってしまっているわけなんだ、このように思います。
それから、やはり嫌だと言っている人がいるけれども、統一された番号によって所得の正確な把握をする、これは徴税の公平化からすればやらざるを得ませんよ。こんなことを、隠しを認めるようなことが暗黙の了解というのはいかにも日本的です。こんなの絶対だめです。
それから、社会保険だとか介護保険の対象者の把握、それから本人確認、行政事務の効率化、幾らでもありますけれども、まず第一点に、もう年金の基礎年金番号制が始まってしまっているではないか、別の番号がついてしまっているのでどうするんだという話があるわけなのです、二つ番号持たなければいけないのかと。
それから、これから介護保険制度が始まってまいります。これも、介護保険制度はシステムの基本設計、全三千三百自治体の中の三千二百自治体が厚生省にシステム設計の補助申請を出しています。ところが、このシステムを構築する上で、ある自治体は住基台帳を根本にして介護保険の台帳をつくろうとしているのです。でも、ある自治体は国保台帳をベースにしているのですよ。統一した見解をつくっていないから、ばらばらになってしまっているわけです。
このほか、これから例えば免許だとかほかの事務に、それから、きょうは余り僕はここで言いたくありませんが、例の納税者番号、ある新聞の社説によると、別のシステムをつくれというのです。それでは一人の人間に三つも四つも五つも番号をつくって、それのシステム運用で、私の地元、埼玉県の川口ですけれども、川口の町で介護保険のシステム基本設計をやるのに七千八百万かかっているのですよ。これまた別の台帳を使えとなったら、また同じ金がかかるわけで、三千二百自治体で、もちろん大きさは四千五百万が基本ですけれども、これはむだ遣いなんですよ。でも、国が方針を定めないから結局やっているわけなんでございます。
とにかくこれを、この住基台帳のシステムが九九%捕捉されて日本で一番ネットワークを張っているのですから、これを今回まず入れさせてもらって、その後の日本の情報化、そして個人がコンピューターにアクセスする、こういうことの前提として、やるべきだと私は思っております。
そういうことで、今回の決意というか、もう質疑時間が終了してしまいましたので、多分お答えは余りできないと思います。でも、そういう気持ちでやらないとこれはうまくいかないよ、私はこういうふうに思うのでございます。一点お願いするとするならば、この住基台帳コードの、将来他の行政事務への展開、このことについてどういう御見解があるのか、このことだけを最後に質問しておきます。
○野田(毅)国務大臣 基本的に御指摘のとおり、まことに私どもが申し上げたい事柄、もう随分お話をちょうだいいたしまして、大変心強い限りであります。
いずれにせよ、これからいろいろな行政事務等にどこまで広げていくかということにつきましては、まずこれをスタートさせていただいた上で、法的な手当てをしながら具体的には展開をしてまいりたいというふうに思います。
ありがとうございました。
○新藤委員 いろいろ申し上げましたが、いろいろな意見があると思いますが、しかし国民大多数の利便性を向上させるという観点から、私は、これは積極的にぜひ推進していただきたい、このように申し上げまして、質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
1999.04.19 県内1市のみ 中心市街地再活性法の指定を川口へ
平成10年7月に施行された中心市街地整備改善活性化法。『新・都市コミュニティの創造』をキーワードに、吸引力を高め、住む人を増やすことを目的に、全国百ヶ所程度の指定都市が考えられた。
新藤議員は商工委員として担当した他に、地方自治経験の都市計画専門家という立場から、党のプロジェクトチームにも特命を受け参加した。当初大蔵省は、地
方都市の空洞化を対象に予算組を考え、首都圏と30万人以上の都市の除外を考えていた。現実に10年の指定を見ると、遠野市、天童市、足利市などが並び、
地方の空洞化に合わせた法律であった。しかし新藤議員は、商工委員会で「東京に対する空洞化も重要な課題。立地と人口で指定地域を制限するといったことは
ないでしょうね」と質問。通産大臣に「そのようなことはない」という答弁を引き出し、活性化法は一気に『地方都市にこだわらない指定』へという広がりを見
せた。
11年度指定を見ると、首都に対する空洞化への配慮から、川口市をはじめに八王子市や小田原市など首都圏近郊都市が続々と指定へ。地方行政の経験を持つ都市派議員の働きで地方偏重の流れを公平なものに変えたのだ。
1999.03.31 20年ぶりの悲願 工業等制限法 川口・鳩ヶ谷をモデルに改正
大都市の産業・人口の過度の集中を防ぎ、都市環境を整備するための規制として、昭和40年に施行されたこの法律。東京23区・武蔵野市全域と三鷹市・横浜
市・川崎市・川口市の一部が制限区域になっていた。この規制の実質は工場追出し法。新設は500m2までしか認められず、設備拡張も新工場進出も不可能。
結果、転廃業と産業集積の崩壊に拍車をかけていた。川口市では毎年この規則の撤廃を要望していたが、20年間、相手にされていないのが現状だった。
新藤議員はこの法の規制緩和の動きに合わせ、小渕総理大臣を川口へ招き、現状を直談判した。総理は視察の翌日に『規制緩和は、中小企業のモデル地区・川口を主体に考えるように』との総理メモを、通産大臣と国土庁長官へ渡し、より実情に合った緩和となった。
この緩和で、新設・増設面積が1500m2と大巾に増え、工場が一つの地域に集中できるように。これによって生産の分業・技術の共有化などの製造ネットワークづくりが活性化でき、産業集積法と合わせて地域の産業振興の大きな力となった。
1998.12.30 国会初 新藤議員の働きかけで鋳物議連、設立へ
自民党衆参両議院からなる鋳物産業振興議員連盟は、日本の基幹産業で、世界一の品質を誇る鋳物業界をテコ入れし、関連予算獲得と国の振興策積極活用を促すのが狙い。
このような業種別議連の設立は今回が初めてだったが、『鋳物の火は、モノづくりと、中小企業の原点』という新藤議員の熱い呼びかけに、65名という多くの議員が賛同した。(会長・錦貫民輔、幹事長・新藤義孝)
この横断的な業種別議連によって、大企業よりの政策が、中小企業とその要である鋳物を軸に考えられるのは必至。
川口・鳩ヶ谷の基準を、国の基準と合わせる新藤議員の産業活動の第一歩だった。
1998.08.31 全国22ヶ所のうち 産業集積法の指定を川口・鳩ヶ谷へ
日本のモノづくりの根幹を支える製造業とその技術。国家が産業集積が高い地域を指定し、種々の優遇措置を敷く地域産業集積活性化法。この法案は、商工委員・新藤議員が担当した。
東京都大田区・川崎市・豊田市・日立市など名だたる産業の街が指定を受けたが、何故か中小企業シェア日本一の川口が、その指定から外れていた。調べてみる
と、この法律は各県の申請が必要だが、何と埼玉県からの申請がなかったのが原因。そこで早速、土屋知事にかけ合い、受け入れ準備の予算措置を行い、奥ノ
木、田中両県議の働きで本会議を通過。素早く県の申請を整えた。
ところが通産省は、20ヶ所分の予算取りは既に決定済みと言う返答。そこで新藤議員は、中小企業日本一の川口を外すことは、法案の目的から外れると強い折衝を行い、同じくもれていた千葉県の東葛地域と一緒に特別枠で地域指定を獲得した。
(川口地域は川口・鳩ヶ谷・草加・蕨・戸田・八潮・三郷の7市。東葛地域は市川・船橋・松戸・野田・柏・流山・我孫子・鎌ヶ谷・浦安・関宿・沼南の9市2町。合計6139事業所)
1998.07.02 初めて大臣が視察 世界のブランド安行に国家の眼を。
わが街の地場産業のもう一つの柱は植木。江戸時代よりはじまった植木産業は、神根・戸塚・安行・新郷に広がり、日本の庭園文化と技術に貢献した。世界の
ガーデニング博では『安行の植木』はひとつのブランドだが、国家ではあまり知られていなかった。今まで、市の主催する『花の文化展』に大臣賞をという要請
はあったが「市町村単位の行事には出せない」というのが農水省の返答だった。
そこで、新藤議員は農水大臣に『安行の植木の伝統と文化の価値』を直訴。平成10年には農林水産大臣賞、翌11年には内閣総理大臣賞の授与を獲得。さらに10年7月2日には島村農林水産大臣を川口に招き植木産業と都市型近郊農業の重要性を、国家に大きくアピールした。
1997.12.15 西川口駅エスカレーター決定!蕨駅いよいよ設置工事開始!
西川口駅東口にエレベーター、西口とホーム上にエスカレーターというこのプラン。かねてから新藤議員がJR東日本と詰めていたが、残すは議会や行政上の手続きとなり、設置は時間の問題となった。
また、奥ノ木県議・高橋市議・立石市議・田口市議らと共に署名運動を行い、自民党市議団経由で市長へ要望書を提出するなど街ぐるみの運動も進めている。
何と行っても1日の乗降数が6万人を超える首都圏屈指の西川口駅。1日で鳩ヶ谷市民以上の人が動く。これは川口・鳩ヶ谷市民のみならず、蕨市・戸田市民の悲願。
また、同時にJRに働きかけていた蕨市は今年度中の設置が決定。次は東川口駅!!と新藤議員は意気込んでいる。
1997.12.15 住民の悲願達成へ 西川口駅整備、大きく前進
川口駅周辺の整備はここ数年で大きく前進したが、それに比べて立ち遅れているのが西川口駅前整備。
だが、新藤議員とJR東日本は、旧国鉄長期債務処理問題を通して深い親交があり、新藤議員の動きで頓挫していた西川口駅エレベーター等、整備問題が今急ピッチで進展している。
数回に渡って持たれたJRとの会談には、駅整備を推進する奥ノ木県議・立石市議・田口市議らも出席。県からの助成金導入も含めて、JR・埼玉県・川口市3者協議で、駅舎のエレベーターとホームのエスカレーター設置案を強力に働きかけている。
1997.12.15 国との太い絆
地元輩出の与党議員が29年間空白だった川口・鳩ヶ谷。今までの陳情といえば、書類と名刺を置いてくる『面会無しの机上配布型陳情』だったが、地元・新藤議員の誕生で、『面談有りの実務型陳情』に一変した。
ある日の陳情を見ても、川口・鳩ヶ谷・浦和・戸田・草加からなる『県南治水促進規制同盟会』の陳情を新藤議員が先導。すると左記のように、1時間半の間に
3省のトップクラスとの会談がアポなしで実現している。「若さと情熱とスピードで霞ヶ関を駆け回る」これが新藤議員のスローガンだ。
1997.12.15 県と川口市の事業SKIPシティに国家を導入させるために
- NHK跡地に計画されているさいたま新産業拠点。県内の中小企業の振興・映像産業集積がコンセプトだが、新藤議員はこれをゴールにしていない。
- 「川口は首都圏の拠点として好立地です。たとえば私が市役所時代に企画したリリアも、川口という町の自治体ホールではなく、首都東京の
劇場として位置付け、機能しています。しかし大宮だったならばこうはならなかったでしょう。つまり、川口という場所は、埼玉という枠だけで捉え切れないロ
ケーション。無理に県や市の施設と限定すると失敗する場所なんです」。 - 「ここに埼玉一の施設ができ、隣の東京にはそれ以上のものができる・・・。それでは財政的にもじつにムダなんです」
- 首都東京という枠組で、国の予算とできるだけリンクさせた施設を川口に置く。そのために新藤議員が動く。それが真に狙う方向だと言う。
通商産業の基本施策に関する件(質疑)衆議院商工委員会-7号 1997年12月5日
通商産業の基本施策に関する件
141-衆-商工委員会-7号 1997年12月05日
○新藤委員 自由民主党の新藤でございます。
一般質疑ということで、大きく二点について御質問させていただきたいというふうに思います。
まず第一点は、さきに発表されました中心市街地再活性化に関する件でございます。
この件につきましては、我が党において中心市街地再活性化調査会というものをつくりまして、精力的に検討を重ねてまいりました。海外に視察へ行きましたり、我が党の山崎政調会長を中心にして、そして特に商工委員の武部先生が事務局長という形で自民党としても一生懸命に活動してきたというところでございまして、いよいよ予算化、また実施に向けての最終的なところに来ておりますので、その件について御質問させていただきたいというふうに思います。
ただ、一つ確認をしておきたいのですが、中心市街地再活性化のこの仕組みを考え出すきっかけが、一般の認識においては、地方の拠点都市の中心市街地において、その郊外に駐車場を伴う大規模店舗が出店している、それによって旧来の商店街があいてしまった。中心市街地の勢いを取り戻そうというふうに言われておりますが、これは地方に限らず、例えば私どものところは川口でございますが、要するに、近隣に大消費地を抱える、商業集積のある、御案内のように池袋から新宿から銀座からと、こういう近所に大商業集積地を控える都市部においても、この中心部の商店街の空洞化というのはかなり深刻な打撃になっております。そしてまた、余りにも大きな、対抗するものが大規模店舗の集積ですから、そして商業の、商店街の集積に対抗しているわけですから、かなり厳しいというところなんです。
ですから、今回のこの中心市街地再活性化というのは、各省庁にわたるいろいろな事業を取り合わせて総合的に町づくりの観点でやっていこう、こういうふうに私は思っておりますので、この中心市街地再活性化を進めるに当たって、一部には、どうやら地方都市の問題なんだ、法律上で言えばいわゆる既成市街地だとか、そういう大都市圏には優先度が低くなるんだよというような話もちょっと聞こえてくるのです。これについてどうなのか、確認をさせていただきたい。
これは全国津々浦々、どこにおいても同じ問題があれば、あとは事業の内容によるのだということにすべきだと私は思っておりますが、ここは大臣、お忙しい中お疲れさまでございますけれども、大臣の口から確認をさせていただきたい、このように思います。
○堀内国務大臣 先生には、中心市街地問題等におきましてもいろいろと御理解をいただき、御指導をいただき、お取りまとめをいただいたりしておりまして、まことにありがとうございます。
ただいまの中心市街地対策というのは、中心市街地の活性化に向けて、市町村等地元関係者が地域の特性を生かしたすぐれた計画を市町村のイニシアチブのもとにつくっていただいて、関係省庁が連携しながら重点的に支援をしていこうというものであります。
したがいまして、三大都市圏を一律に排除するとか、そういうようなものでは全くなくて、中心市街地の活性化に向けてすぐれた計画が作成され、かつ同時に、その地域においてそれが非常に必要であるという御熱意のもとに発生してきた問題、支援の必要性が相対的に高いと認められる場合については、地域は限定したものではございません。利用可能な支援措置を十分に活用しながら、中心市街地の活性化を推進させてまいりたい
と考えております。
○新藤委員 ありがとうございました。
所管の大臣から力強いお言葉をいただいて、我が意を得たりというところなんでございますが、ややもすると予算を査定する段階において、また特に公共事業の執行を抱えるような部門においては、どこかで切らざるを得ないとなると、そういうことが起こらざるとも限らないわけでございまして、そこはひとつぜひとも大臣にリーダーシップをとっていただいて、関係省庁にもよくよくのお願いを申し上げたい、このように存じます。
そして、その関連でございますが、まさに十一省庁が参加をした総合的な対策になるということなんですけれども、この仕事を総合的に、重点的にやっていくのですが、加えて、確実に仕事としてやれるようにしていかなければいけない。制度としては名乗りを上げたけれども、名乗りを上げただけで終わってしまうようなことになっては困るわけでございまして、そういう意味で、例えば縦割り行政を、ちょっと言葉は悪いですけれども、横の連携をとるためにということでいろいろな省庁が参加をしていただいております。
これは一例を挙げれば文部省の関係でございますけれども、いわゆる中心市街地というのは、まさに子供の教育の関係からいえば一番子供人口が少ないところでございまして、ここにおける空き教室の問題というのが前々から話題になっているということなんです。
それで、あえてきょうは文部省の方においでをいただいて、私はここで確認をさせてもらいたいのは、その地域というか自治体の関係者ですとか、そういう方々は前々から、空き教室ができてしまった、困った困った、では福祉の施設だとか社会教育施設に、ほかに転用しようじゃないか、こういう動きになっている。しかし、所管が違うと。それで、例えば補助金適正化法だとか、それからいわゆる自治法の行政財産の使用の関係等においてなかなかこれはうまくいかないのですよといって、最初からうまくいかないのですよで終わってしまっているケースというのは、市町村の方々に聞くと意外と多いのですね。
それで私は、それについては文部省が手を打っている、このように思っておりますけれども、あえてこの場で、今回中心市街地再活性化の中でも空き教室、社会教育施設の利用、こういうのが文部省関係の施策として出てきておりますので、この辺について、実際の運用上どういうふうに今回収り扱いをするようになっているのか、そのことを教えていただきたい、このように思います。――それでは文部省は後にしていただきまして、関連で、中心市街地再活性化の事業をやる人たちのことを聞かせていただきたいと思います。
事業をやるのは、地元の自治体がまずやりますね、計画をつくって、公共施設をつくります。それとあわせて、今度は、商店街の皆さんやその自治体がつくる施設に参加をする民間の事業者、こういう人たちがいると思うのですけれども、この事業に積極的に参加をしていただくためには、やはり特別の税制や財政の支援措置が必要ではないか、こういうふうに思うわけでございます。特に、今のところは新しい制度なのですから、この中心市街地再活性化に参加をした場合の民間事業者に対する支援というものはまだ決まっていないわけでございます。その件について、通産省としてはどんなような税制措置を考えているのか、教えていただきたいのです。
○岩田政府委員 お答えを申し上げます。
先生御指摘の、民間事業者によります事業に関連いたしましては、財政上の措置としてはまだこれから予算編成を経てのことで、まだ折衝中、要求中のことではございますが、通産省としては補助金の制度の要求をいたしております。
他方、税制の面につきましては、中心市街地におきます商業集積の関連施設の整備、そのほかに、駐車場その他の基盤整備というような切り口から、税制といたしましては、建物の所有者に対します特別償却制度の創設、不動産の取得に係ります登録免許税の軽減、施設整備に必要な土地等を売却した場合の譲渡所得の特別控除、事業所税の非課税、特別土地保有税の非課税、家屋についての不動産取得税、固定資産税の課税標準の特例措置を要求いたしておるところでございます。
○新藤委員 それでは、文部省の方、おいでいただきましたので、文部省さんに御質問させていただきます。
中心市街地再活性化の文部省としての制度の中で、社会教育施設の中心市街地の中における整備を推進する。それから、あわせて空き教室の転用についてのことも積極的に運用していくのだ、こういうふうに聞いております。
名乗りを上げていただいているのはありがたいのですけれども、地元の市町村だとかそういうところからよく聞こえてくる話は、いや、実はやりたいのだけれども、補助金適正化法だとか、それから地方自治法の、要するに行政財産の転用というか使用の関係で、実際にはなかなかできないのだと。それからあわせて、現場の役所の中でも、教育施設の中に社会福祉施設という目的である子供以外の方が入ってくることについてとか、いろいろあって、うまくいっていないところもあるのです。
文部省としては、こういうことについて、実際運用する上でどんな工夫を、またどういう取り組みをされるおつもりなのか、その部分をお聞かせいただきたいと思います。
○高塩説明員 先生、先ほど大変失礼いたしました。お答え申し上げます。
先生御指摘のように、近年、児童生徒数の減少に伴いまして、特に中心市街地、都市部を中心に余裕教室を持つ学校がふえてきております。この余裕教室につきましては、各学校の設置者でございます市町村が、それぞれの地域の実情に応じまして適切に判断いたしまして、積極的に活用を図ることが重要であると考えておる次第でございます。
文部省といたしましては、既に平成五年の四月に余裕教室活用指針というものを示しまして、その余裕教室を学校教育の充実のための施設に活用するとともに、いわゆる学校以外の施設への転用を積極的に図るようにということを市町村に対して指導を行ってきているところでございます。
そして、ただいま申し上げました学校以外の施設への転用につきましては、先生御指摘のとおり、補助金を受けた学校施設につきましては財産処分という手続が必要でございます。先生御指摘のように、補助金適正化法によりましては、補助金を返還するか、もしくは耐用年数に達しませんと補助目的以外には使用してはならないという規定があるわけでございますけれども、法律では、各省庁の大臣の承認を得た場合にはその限りではないということでございまして、私どもといたしましては、従来から、学校以外の施設、御指摘のございました社会教育施設、それから社会体育施設、文化施設等の文教関係施設のほか、やはり御指摘のございました老人デイサービスセンター等の社会福祉施設への転用につきましては、この承認という手続は報告をもって足りるという、非常に簡素な手続にしているところでございます。
さらに、先生方の中心市街地の御指摘等も踏まえまして、去る十一月二十日に新たに私どもの通知を全面改正いたしまして、一層この余裕教室が社会福祉施設等への転用を図れるようにするために、報告事項の拡大を図るとともに、これも御指摘のございました補助金につきましては、原則として十年を経過した学校施設については、それを公共に、かつ無償で転用する場合には補助金に相当する納付金は要らないということを明記いたしまして、現在、県を通じて市町村を指導しているところでございます。
ただいま申し上げましたような取り組みを通じまして、この余裕教室の転用につきまして文部省としても積極的に取り組んでまいる次第でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○新藤委員 十一月の二十日に出したということでございますし、私もちょっと見せていただきました。これは、明確に十年と、こういうふうに出
していただいて、本当にいいんじゃないかなと。
むしろ、今後は現場においてそういう啓蒙を徹底させることと、それから、やはり自治体をきちんと指導して、要は、教育局と社会福祉部の方でなかなか進まないことなんですよね。
これをわざわざ取り上げましたのは、私は、この問題は、市街地の活性化とともに、子供たちが教育の場において当たり前のようにお年寄りや、それから障害の方、そういう人と触れ合う、これが非常に将来の福祉社会の中で役に立つことだと思っておりますので、この中心市街地というものの活性化を機に、ぜひPRをしていただきたい。我々もそれは広めていきたい。十年で、しかも手続が簡単になりましたよ、この話をしていきたい、こういうふうに思います。
今、二例申し上げましたが、ほかにいろいろあるのですよね。それで、建設省は街なか再生事業をやると言っておるし、労働省や厚生省もそれぞれセンターや施設を中に入れ込んでまいりますと。それから、郵政省に至っては、マルチメディアや情報推進のものをその中でやる場合とか、警察庁や農水省までと、本当に盛りだくさんに入れていただいているのですが、私は、ここで大事なのは、従来やっているものを、中心市街地の再活性化という大きな、通産省挙げての事業ができ上がったので、そこに、言葉は悪いのですが、名乗りを上げたという形のものも間々ある。ちょっと中身を見てまいりますと、中心市街地のためだけではないような予算措置もあるわけでございまして、これはやはり真水というか、この政策をふやしていく必要があると思うのです。
特に大事なのは、要するに先ほどは民間事業者に対して税制上の措置を行う、これは大蔵省にしっかりお願いしなければいけないわけなんですけれども、あわせて大事なのは、これだけのことをやりますと、今度は地元の自治体の財政負担がきつくなるわけでございます。固定資産税は減免になりますし、事業所税も減収になるわけですから、なったとしたら、やはりこの部分の財政補てん、地方財政の支援というものを考えなきゃいけないのじゃないかというふうに思うのです。
それから、起債の特例ですとか、そういうのをやるとなると、これは今度は地方財政にしわ寄せが来るわけなんですね。私は、想像するに、今財政構造改革法が通って、縮減の中で新たなそういう財政支援を行う枠を決めるのはかなり厳しいぞ、こういうふうに思っております。
これについては、結局は通産省、そして大臣にリーダーシップを発揮していただいて、この必要性をしっかりと訴えていく必要があるのではないか。きょうは自治省の方はお呼びしておりませんので、これはぜひ商工委員会として、そういったことを大臣の方からお伝えいただけるとありがたい、こういうふうに思います。
あわせて、これだけのもろもろの大きな仕組みをつくったわけでございます。従来の法律で適用できない部分が多々ありますし、新たにつくらなければいかぬということになると、当然のごとく新法を制定しなくてはいけないのではないかと思うのでございますが、先ほどの各省庁にわたるリーダーシップを含めて、大臣に決意表明をいただければありがたいと思います。
○堀内国務大臣 中心市街地の活性化に向けましては、先生御指摘のとおり、市町村、地元の関係の方々に強力なリーダーシップを持っていただいて、イニシアチブを持ってもらって進めていかなければなりません。地域の特性を生かしたすぐれた計画をつくっていただいて、それに基づいて行う事業でありますから、その事業に対して、関係省庁が連携をしながら、重点的に施策を投入していくことが重要だろうというふうに思っております。
そういう意味で、通産省としては、こういう施策の実現を図っていくに当たって、所要の法的措置を講じる必要があると考えております。現在考えておりますのは、中心市街地活性化法と申しますか、そういう法律を一つしっかり柱にいたしまして、各省庁との連携も踏まえながら、具体的な内容について検討を進めてまいりたいと思っております。
通産省が中心となりながら、建設、自治、三省が中核であって、あと、八省庁との関連を持ちながら、御期待にこたえられるようなしっかりとした対応をしてまいりたいと思っております。
○新藤委員 ありがとうございました。
それでは、時間も少なくなってまいりましたので手短に進めさせていただきたいと思いますが、もう一点、大規模店舗の調整法に関連して御質問させていただきます。
私、十二月二日付で新聞を拝見したのですが、日経新聞に「大店法来年度末にも廃止」、こういうトップで記事が出ております。政府は方針を固めた、このような新聞記事になっておりますが、まず事実関係について、これは本当ですか、お答えいただきたいと思います。
○堀内国務大臣 大店法の制度の見直しにつきましては、現在、産業構造審議会と中小企業政策審議会の合同会議で審議を行っているところでありまして、この審議の結論を待っているところでありますが、特に今までのスケジュールにこだわらずに、さらに慎重に各方面の御意見を承って、答申に向かっての努力を、取りまとめをお願いするようにいたしているところでございます。
したがいまして、御指摘の新聞記事のように、現時点で審議会としての見直しの方針とか内容とかというものを固めた事実はございませんし、ましてや政府においては全くの白紙でございます。
○新藤委員 今の御答弁どおりだと思うのですけれども、この新聞が出たことによって、かなり反響は大きくて、全国から、大店法廃止反対だ、やめないでくれ、こういうような声がふつふっと沸き起こってきている。ちょっとタイミングが悪いのじゃないかな、こういうふうに思うわけでございまして、ぜひ、情報管理というか、これは徹底していただきたいというふうに思います。
そして、この大店法につきましては、私も少し勉強させてもらったのですけれども、結局のところ、昭和十二年から始まっている百貨店法が根拠になっている。当時は許可制でしたが、その後、今は届け出制になっておりますけれども、六十年たった法律だ。そして、その根幹にあるのが、要するに、商業床の面積コントロールを行う、それによって中小小売業者の事業機会を確保する、まさに保護的な法律であったということだと思うのです。
私は、この新聞記事そのものは、この時期にこんなものが出たというのはまことに遺憾なのですが、ただ、中身においてはやはり傾聴に値する部分もあるなと。今の時代に、ただ床面積を制限して、大きな店舗が来なければそれで商店街を、地元を守れるのだというだけでは、これはうまくいかないわけですね。
また、アメリカや外国からの外圧も大分来ております。外圧で、外国から言われたから直すなんて、そんな情けないことを日本の国はゆめゆめ考えないはずでございますが、やはり世界のスタンダードの中で、規模の大小を問わず、我が国の商業流通制度を世界に勝負できるようなものに直さなくてはいけないわけでございます。
こういうことからすると、閣議決定によりますと、アクションプログラムでは法的措置を含めた抜本的な検討を行う、こういうことになって、今まさに、先ほどもお答えいただきました合同会議がある。私が聞いている話では、きょうの二時から八回目があると。私はその三十分前にこの話をしているわけでございまして、きょうの話があってから新聞は出なければいけない話なんですよ。だから、ちょっと困ったなと思っているのですけれども、そういう中で大店法をどう取り扱っていくか。
そこで、私は一つだけ申し上げたいのです。
私も地元でかつて商業調整にかかわったことがございます。一番の問題は、要するに店舗の商業床の問題で、面積と時間それから休みの日、こういうものを調整するだけでは、実は大店舗が出店してその町がどうなるかというルールの調整にな
らないのです。お店が出てくれば、大きなものが出てくれば、それに関係する駐車場は整備しなければいけない、交通渋滞は巻き起こる、ごみはいっぱい出る、そして、例えば風俗が乱れる場合も間々あります。そういうもろもろのことをやるには、商業調整ではなくて町づくりのルールなんですよ。
だから、大店法を見直すのだとすれば、このお店の出店によって、周りの影響を調整することとあわせて、都市への影響をどういうふうに考えるか、それをまた拘束力を持たせるか、都市計画とか町づくりの観点が必要なんです。この部分を入れないと、結局は、今現状では都市計画法、建築基準法それから市町村の要綱で大店法にない部分をやっている、しかし、それは要綱行政だから全然コントロールがきかぬ、こういう話です。
だから、終盤の詰めが間際になっているところだと思いますけれども、ぜひこの部分ははっきりと、商業調整が都市機能においてどういう影響を与えられるか、そのルールづくり、この部分を織り込んだ形で大店法の抜本的な改正、見直しを行っていただきたい、このように思うのでございます。
これは大臣でよろしゅうございますか。お考えというか、ぜひ聞いておいていただければありがたいのですけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
○岩田政府委員 お答え申し上げます。
先ほど来大臣から御答弁申し上げておりますように、現在、産構審・中政審の合同会議で審議中でございまして、大詰めの議論が行われているところでございます。
ただ、御指摘のございましたような、大型店の適正な立地でございますとか良好な生活環境の保全でございますとかいうようなことにつきましては、この審議の中でも重要な問題と認識をされておりまして、まさに主要な論点として御議論をいただいているという状況にございます。
○新藤委員 ありがとうございました。
工場立地法の一部改正法律案(質疑)衆議院商工委員会-3号 1997年11月5日
工場立地法の一部改正法律案(質問)
141-衆-商工委員会-3号 1997年11月05日
○新藤委員 自由民主党の新藤でございます。
一般質疑ということで、大きく二点について御質問させていただきたいというふうに思います。
まず第一点は、さきに発表されました中心市街地再活性化に関する件でございます。
この件につきましては、我が党において中心市街地再活性化調査会というものをつくりまして、精力的に検討を重ねてまいりました。海外に視察へ行きましたり、我が党の山崎政調会長を中心にして、そして特に商工委員の武部先生が事務局長という形で自民党としても一生懸命に活動してきたというところでございまして、いよいよ予算化、また実施に向けての最終的なところに来ておりますので、その件について御質問させていただきたいというふうに思います。
ただ、一つ確認をしておきたいのですが、中心市街地再活性化のこの仕組みを考え出すきっかけが、一般の認識においては、地方の拠点都市の中心市街地において、その郊外に駐車場を伴う大規模店舗が出店している、それによって旧来の商店街があいてしまった。中心市街地の勢いを取り戻そうというふうに言われておりますが、これは地方に限らず、例えば私どものところは川口でございますが、要するに、近隣に大消費地を抱える、商業集積のある、御案内のように池袋から新宿から銀座からと、こういう近所に大商業集積地を控える都市部においても、この中心部の商店街の空洞化というのはかなり深刻な打撃になっております。そしてまた、余りにも大きな、対抗するものが大規模店舗の集積ですから、そして商業の、商店街の集積に対抗しているわけですから、かなり厳しいというところなんです。
ですから、今回のこの中心市街地再活性化というのは、各省庁にわたるいろいろな事業を取り合わせて総合的に町づくりの観点でやっていこう、こういうふうに私は思っておりますので、この中心市街地再活性化を進めるに当たって、一部には、どうやら地方都市の問題なんだ、法律上で言えばいわゆる既成市街地だとか、そういう大都市圏には優先度が低くなるんだよというような話もちょっと聞こえてくるのです。これについてどうなのか、確認をさせていただきたい。
これは全国津々浦々、どこにおいても同じ問題があれば、あとは事業の内容によるのだということにすべきだと私は思っておりますが、ここは大臣、お忙しい中お疲れさまでございますけれども、大臣の口から確認をさせていただきたい、このように思います。
○堀内国務大臣 先生には、中心市街地問題等におきましてもいろいろと御理解をいただき、御指導をいただき、お取りまとめをいただいたりしておりまして、まことにありがとうございます。
ただいまの中心市街地対策というのは、中心市街地の活性化に向けて、市町村等地元関係者が地域の特性を生かしたすぐれた計画を市町村のイニシアチブのもとにつくっていただいて、関係省庁が連携しながら重点的に支援をしていこうというものであります。
したがいまして、三大都市圏を一律に排除するとか、そういうようなものでは全くなくて、中心市街地の活性化に向けてすぐれた計画が作成され、かつ同時に、その地域においてそれが非常に必要であるという御熱意のもとに発生してきた問題、支援の必要性が相対的に高いと認められる場合については、地域は限定したものではございません。利用可能な支援措置を十分に活用しながら、中心市街地の活性化を推進させてまいりたい
と考えております。
○新藤委員 ありがとうございました。
所管の大臣から力強いお言葉をいただいて、我が意を得たりというところなんでございますが、ややもすると予算を査定する段階において、また特に公共事業の執行を抱えるような部門においては、どこかで切らざるを得ないとなると、そういうことが起こらざるとも限らないわけでございまして、そこはひとつぜひとも大臣にリーダーシップをとっていただいて、関係省庁にもよくよくのお願いを申し上げたい、このように存じます。
そして、その関連でございますが、まさに十一省庁が参加をした総合的な対策になるということなんですけれども、この仕事を総合的に、重点的にやっていくのですが、加えて、確実に仕事としてやれるようにしていかなければいけない。制度としては名乗りを上げたけれども、名乗りを上げただけで終わってしまうようなことになっては困るわけでございまして、そういう意味で、例えば縦割り行政を、ちょっと言葉は悪いですけれども、横の連携をとるためにということでいろいろな省庁が参加をしていただいております。
これは一例を挙げれば文部省の関係でございますけれども、いわゆる中心市街地というのは、まさに子供の教育の関係からいえば一番子供人口が少ないところでございまして、ここにおける空き教室の問題というのが前々から話題になっているということなんです。
それで、あえてきょうは文部省の方においでをいただいて、私はここで確認をさせてもらいたいのは、その地域というか自治体の関係者ですとか、そういう方々は前々から、空き教室ができてしまった、困った困った、では福祉の施設だとか社会教育施設に、ほかに転用しようじゃないか、こういう動きになっている。しかし、所管が違うと。それで、例えば補助金適正化法だとか、それからいわゆる自治法の行政財産の使用の関係等においてなかなかこれはうまくいかないのですよといって、最初からうまくいかないのですよで終わってしまっているケースというのは、市町村の方々に聞くと意外と多いのですね。
それで私は、それについては文部省が手を打っている、このように思っておりますけれども、あえてこの場で、今回中心市街地再活性化の中でも空き教室、社会教育施設の利用、こういうのが文部省関係の施策として出てきておりますので、この辺について、実際の運用上どういうふうに今回収り扱いをするようになっているのか、そのことを教えていただきたい、このように思います。――それでは文部省は後にしていただきまして、関連で、中心市街地再活性化の事業をやる人たちのことを聞かせていただきたいと思います。
事業をやるのは、地元の自治体がまずやりますね、計画をつくって、公共施設をつくります。それとあわせて、今度は、商店街の皆さんやその自治体がつくる施設に参加をする民間の事業者、こういう人たちがいると思うのですけれども、この事業に積極的に参加をしていただくためには、やはり特別の税制や財政の支援措置が必要ではないか、こういうふうに思うわけでございます。特に、今のところは新しい制度なのですから、この中心市街地再活性化に参加をした場合の民間事業者に対する支援というものはまだ決まっていないわけでございます。その件について、通産省としてはどんなような税制措置を考えているのか、教えていただきたいのです。
○岩田政府委員 お答えを申し上げます。
先生御指摘の、民間事業者によります事業に関連いたしましては、財政上の措置としてはまだこれから予算編成を経てのことで、まだ折衝中、要求中のことではございますが、通産省としては補助金の制度の要求をいたしております。
他方、税制の面につきましては、中心市街地におきます商業集積の関連施設の整備、そのほかに、駐車場その他の基盤整備というような切り口から、税制といたしましては、建物の所有者に対します特別償却制度の創設、不動産の取得に係ります登録免許税の軽減、施設整備に必要な土地等を売却した場合の譲渡所得の特別控除、事業所税の非課税、特別土地保有税の非課税、家屋についての不動産取得税、固定資産税の課税標準の特例措置を要求いたしておるところでございます。
○新藤委員 それでは、文部省の方、おいでいただきましたので、文部省さんに御質問させていただきます。
中心市街地再活性化の文部省としての制度の中で、社会教育施設の中心市街地の中における整備を推進する。それから、あわせて空き教室の転用についてのことも積極的に運用していくのだ、こういうふうに聞いております。
名乗りを上げていただいているのはありがたいのですけれども、地元の市町村だとかそういうところからよく聞こえてくる話は、いや、実はやりたいのだけれども、補助金適正化法だとか、それから地方自治法の、要するに行政財産の転用というか使用の関係で、実際にはなかなかできないのだと。それからあわせて、現場の役所の中でも、教育施設の中に社会福祉施設という目的である子供以外の方が入ってくることについてとか、いろいろあって、うまくいっていないところもあるのです。
文部省としては、こういうことについて、実際運用する上でどんな工夫を、またどういう取り組みをされるおつもりなのか、その部分をお聞かせいただきたいと思います。
○高塩説明員 先生、先ほど大変失礼いたしました。お答え申し上げます。
先生御指摘のように、近年、児童生徒数の減少に伴いまして、特に中心市街地、都市部を中心に余裕教室を持つ学校がふえてきております。この余裕教室につきましては、各学校の設置者でございます市町村が、それぞれの地域の実情に応じまして適切に判断いたしまして、積極的に活用を図ることが重要であると考えておる次第でございます。
文部省といたしましては、既に平成五年の四月に余裕教室活用指針というものを示しまして、その余裕教室を学校教育の充実のための施設に活用するとともに、いわゆる学校以外の施設への転用を積極的に図るようにということを市町村に対して指導を行ってきているところでございます。
そして、ただいま申し上げました学校以外の施設への転用につきましては、先生御指摘のとおり、補助金を受けた学校施設につきましては財産処分という手続が必要でございます。先生御指摘のように、補助金適正化法によりましては、補助金を返還するか、もしくは耐用年数に達しませんと補助目的以外には使用してはならないという規定があるわけでございますけれども、法律では、各省庁の大臣の承認を得た場合にはその限りではないということでございまして、私どもといたしましては、従来から、学校以外の施設、御指摘のございました社会教育施設、それから社会体育施設、文化施設等の文教関係施設のほか、やはり御指摘のございました老人デイサービスセンター等の社会福祉施設への転用につきましては、この承認という手続は報告をもって足りるという、非常に簡素な手続にしているところでございます。
さらに、先生方の中心市街地の御指摘等も踏まえまして、去る十一月二十日に新たに私どもの通知を全面改正いたしまして、一層この余裕教室が社会福祉施設等への転用を図れるようにするために、報告事項の拡大を図るとともに、これも御指摘のございました補助金につきましては、原則として十年を経過した学校施設については、それを公共に、かつ無償で転用する場合には補助金に相当する納付金は要らないということを明記いたしまして、現在、県を通じて市町村を指導しているところでございます。
ただいま申し上げましたような取り組みを通じまして、この余裕教室の転用につきまして文部省としても積極的に取り組んでまいる次第でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○新藤委員 十一月の二十日に出したということでございますし、私もちょっと見せていただきました。これは、明確に十年と、こういうふうに出
していただいて、本当にいいんじゃないかなと。
むしろ、今後は現場においてそういう啓蒙を徹底させることと、それから、やはり自治体をきちんと指導して、要は、教育局と社会福祉部の方でなかなか進まないことなんですよね。
これをわざわざ取り上げましたのは、私は、この問題は、市街地の活性化とともに、子供たちが教育の場において当たり前のようにお年寄りや、それから障害の方、そういう人と触れ合う、これが非常に将来の福祉社会の中で役に立つことだと思っておりますので、この中心市街地というものの活性化を機に、ぜひPRをしていただきたい。我々もそれは広めていきたい。十年で、しかも手続が簡単になりましたよ、この話をしていきたい、こういうふうに思います。
今、二例申し上げましたが、ほかにいろいろあるのですよね。それで、建設省は街なか再生事業をやると言っておるし、労働省や厚生省もそれぞれセンターや施設を中に入れ込んでまいりますと。それから、郵政省に至っては、マルチメディアや情報推進のものをその中でやる場合とか、警察庁や農水省までと、本当に盛りだくさんに入れていただいているのですが、私は、ここで大事なのは、従来やっているものを、中心市街地の再活性化という大きな、通産省挙げての事業ができ上がったので、そこに、言葉は悪いのですが、名乗りを上げたという形のものも間々ある。ちょっと中身を見てまいりますと、中心市街地のためだけではないような予算措置もあるわけでございまして、これはやはり真水というか、この政策をふやしていく必要があると思うのです。
特に大事なのは、要するに先ほどは民間事業者に対して税制上の措置を行う、これは大蔵省にしっかりお願いしなければいけないわけなんですけれども、あわせて大事なのは、これだけのことをやりますと、今度は地元の自治体の財政負担がきつくなるわけでございます。固定資産税は減免になりますし、事業所税も減収になるわけですから、なったとしたら、やはりこの部分の財政補てん、地方財政の支援というものを考えなきゃいけないのじゃないかというふうに思うのです。
それから、起債の特例ですとか、そういうのをやるとなると、これは今度は地方財政にしわ寄せが来るわけなんですね。私は、想像するに、今財政構造改革法が通って、縮減の中で新たなそういう財政支援を行う枠を決めるのはかなり厳しいぞ、こういうふうに思っております。
これについては、結局は通産省、そして大臣にリーダーシップを発揮していただいて、この必要性をしっかりと訴えていく必要があるのではないか。きょうは自治省の方はお呼びしておりませんので、これはぜひ商工委員会として、そういったことを大臣の方からお伝えいただけるとありがたい、こういうふうに思います。
あわせて、これだけのもろもろの大きな仕組みをつくったわけでございます。従来の法律で適用できない部分が多々ありますし、新たにつくらなければいかぬということになると、当然のごとく新法を制定しなくてはいけないのではないかと思うのでございますが、先ほどの各省庁にわたるリーダーシップを含めて、大臣に決意表明をいただければありがたいと思います。
○堀内国務大臣 中心市街地の活性化に向けましては、先生御指摘のとおり、市町村、地元の関係の方々に強力なリーダーシップを持っていただいて、イニシアチブを持ってもらって進めていかなければなりません。地域の特性を生かしたすぐれた計画をつくっていただいて、それに基づいて行う事業でありますから、その事業に対して、関係省庁が連携をしながら、重点的に施策を投入していくことが重要だろうというふうに思っております。
そういう意味で、通産省としては、こういう施策の実現を図っていくに当たって、所要の法的措置を講じる必要があると考えております。現在考えておりますのは、中心市街地活性化法と申しますか、そういう法律を一つしっかり柱にいたしまして、各省庁との連携も踏まえながら、具体的な内容について検討を進めてまいりたいと思っております。
通産省が中心となりながら、建設、自治、三省が中核であって、あと、八省庁との関連を持ちながら、御期待にこたえられるようなしっかりとした対応をしてまいりたいと思っております。
○新藤委員 ありがとうございました。
それでは、時間も少なくなってまいりましたので手短に進めさせていただきたいと思いますが、もう一点、大規模店舗の調整法に関連して御質問させていただきます。
私、十二月二日付で新聞を拝見したのですが、日経新聞に「大店法来年度末にも廃止」、こういうトップで記事が出ております。政府は方針を固めた、このような新聞記事になっておりますが、まず事実関係について、これは本当ですか、お答えいただきたいと思います。
○堀内国務大臣 大店法の制度の見直しにつきましては、現在、産業構造審議会と中小企業政策審議会の合同会議で審議を行っているところでありまして、この審議の結論を待っているところでありますが、特に今までのスケジュールにこだわらずに、さらに慎重に各方面の御意見を承って、答申に向かっての努力を、取りまとめをお願いするようにいたしているところでございます。
したがいまして、御指摘の新聞記事のように、現時点で審議会としての見直しの方針とか内容とかというものを固めた事実はございませんし、ましてや政府においては全くの白紙でございます。
○新藤委員 今の御答弁どおりだと思うのですけれども、この新聞が出たことによって、かなり反響は大きくて、全国から、大店法廃止反対だ、やめないでくれ、こういうような声がふつふっと沸き起こってきている。ちょっとタイミングが悪いのじゃないかな、こういうふうに思うわけでございまして、ぜひ、情報管理というか、これは徹底していただきたいというふうに思います。
そして、この大店法につきましては、私も少し勉強させてもらったのですけれども、結局のところ、昭和十二年から始まっている百貨店法が根拠になっている。当時は許可制でしたが、その後、今は届け出制になっておりますけれども、六十年たった法律だ。そして、その根幹にあるのが、要するに、商業床の面積コントロールを行う、それによって中小小売業者の事業機会を確保する、まさに保護的な法律であったということだと思うのです。
私は、この新聞記事そのものは、この時期にこんなものが出たというのはまことに遺憾なのですが、ただ、中身においてはやはり傾聴に値する部分もあるなと。今の時代に、ただ床面積を制限して、大きな店舗が来なければそれで商店街を、地元を守れるのだというだけでは、これはうまくいかないわけですね。
また、アメリカや外国からの外圧も大分来ております。外圧で、外国から言われたから直すなんて、そんな情けないことを日本の国はゆめゆめ考えないはずでございますが、やはり世界のスタンダードの中で、規模の大小を問わず、我が国の商業流通制度を世界に勝負できるようなものに直さなくてはいけないわけでございます。
こういうことからすると、閣議決定によりますと、アクションプログラムでは法的措置を含めた抜本的な検討を行う、こういうことになって、今まさに、先ほどもお答えいただきました合同会議がある。私が聞いている話では、きょうの二時から八回目があると。私はその三十分前にこの話をしているわけでございまして、きょうの話があってから新聞は出なければいけない話なんですよ。だから、ちょっと困ったなと思っているのですけれども、そういう中で大店法をどう取り扱っていくか。
そこで、私は一つだけ申し上げたいのです。
私も地元でかつて商業調整にかかわったことがございます。一番の問題は、要するに店舗の商業床の問題で、面積と時間それから休みの日、こういうものを調整するだけでは、実は大店舗が出店してその町がどうなるかというルールの調整にな
らないのです。お店が出てくれば、大きなものが出てくれば、それに関係する駐車場は整備しなければいけない、交通渋滞は巻き起こる、ごみはいっぱい出る、そして、例えば風俗が乱れる場合も間々あります。そういうもろもろのことをやるには、商業調整ではなくて町づくりのルールなんですよ。
だから、大店法を見直すのだとすれば、このお店の出店によって、周りの影響を調整することとあわせて、都市への影響をどういうふうに考えるか、それをまた拘束力を持たせるか、都市計画とか町づくりの観点が必要なんです。この部分を入れないと、結局は、今現状では都市計画法、建築基準法それから市町村の要綱で大店法にない部分をやっている、しかし、それは要綱行政だから全然コントロールがきかぬ、こういう話です。
だから、終盤の詰めが間際になっているところだと思いますけれども、ぜひこの部分ははっきりと、商業調整が都市機能においてどういう影響を与えられるか、そのルールづくり、この部分を織り込んだ形で大店法の抜本的な改正、見直しを行っていただきたい、このように思うのでございます。
これは大臣でよろしゅうございますか。お考えというか、ぜひ聞いておいていただければありがたいのですけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
○岩田政府委員 お答え申し上げます。
先ほど来大臣から御答弁申し上げておりますように、現在、産構審・中政審の合同会議で審議中でございまして、大詰めの議論が行われているところでございます。
ただ、御指摘のございましたような、大型店の適正な立地でございますとか良好な生活環境の保全でございますとかいうようなことにつきましては、この審議の中でも重要な問題と認識をされておりまして、まさに主要な論点として御議論をいただいているという状況にございます。
○新藤委員 ありがとうございました。
特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案(質疑) 衆議院商工委員会-6号 1997年3月21日
特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案(質疑)
140-衆-商工委員会-6号 1997年03月21日
○新藤委員 この今回の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案、私もみずからの政治活動の中で大変に中小企業、また国内の産業の育成、活性化、この点については大きな関心を持っておりまして、過日、予算委員会でも、分科会で大臣には質問させていただきました。また重なって恐縮でございますが、何点かお考えをお聞かせ願いたいというふうに思います。これまで各委員の方々からも何度も質問が出ております。私もこれは触れざるを得ないわけでございますが、まずは、産業の空洞化についてでございます。
私は、このときにも、空洞化と申しましても二つあるなと思っております。一つは、いわゆる生産機能が海外展開をするという、国際分業化時代を迎えての生産拠点の海外移転、こういうことだ。それからもう一つは、内なる空洞化として、国内にある中小製造業の縮小化、こういうものがあるのではないかというふうに思っております。
海外シフトの方はもういろいろ言われておりますからあえて数字も挙げませんが、この内なる空洞化につきましても、中小企業の事業機会の縮小というのは、中小企業等の開発業率、こういう数字を見ますと、八九年以降、廃業率が開業率を上回っている、こういう実態が出ております。そして、製造業全体の雇用は今後五年間で百二十四万人の減少になるだろう、こういう予測が出ておるわけでございます。
この点も踏まえて、実際の、現在の産業空洞化の現状についてへどうなっているのか、また、問題点の御認識、どこの部分をされているのか、大臣からお聞かせいただきたいと思います。
○佐藤国務大臣 今おっしゃるように、中小企業といっても大変すそ野が広い、幅があるわけでございます。今言われている空洞化現象、これはやはり工業、この方面が主に言われておりまして、この法律も商業的な中小企業者よりか工業的なと、こういうふうに力点が置かれていると思うのです。
そこで、よく申すように、やはりこれまでの認識というのは、海外に行く、そういうことによって雇用が喪失するという、これが非常に今問題視されているわけです。昨年の通産省の方の調査でも、このままでいくと、五年間、ですから二〇〇一年ですか、これに百二十四万人ぐらい減少する。この減少は当然へ当時の一ドル百十円ということではじいたのですが、これが今みたいな円安の百二十円になっても余りこうした傾向は変わらないだろう、こういうことでございます。
そこで、企業が最適な事業環境を求め国際展開を図っていくということ自体は評価できますが、今のように、我が国の高コスト構造や制度的規制ということが要因で、本来ならば日本の国内において比較的優位を保たれるような産業までどんどん行く、こういうことでございまして、今委員御指摘のように、日本から外に行く、アメリカのように入ってくるものが多いかというと、それが十三分の一ぐらいしか入ってこない、こういうところに非常に問題の深刻化というのがうかがえるわけでございます。
そういうことを踏まえて、新たな雇用の担い手となる新規産業の創出、それからそれと並んで高コスト構造の是正等による我が国の国際的に魅力ある事業環境、こういうものの整備が急務だな、こういうふうに認識しているわけでございます。
〔委員長退席、小川委員長代理着席〕
○新藤委員 それに加えて、私は、またここで自分なりの定義をさせていただきたいと思いますが、日本の企業の中で中小企業はいわゆる全事業者の九九%、全従業員数の七八%、生産額ですと、いろいろな統計がありますが、半分から半分ちょっと過ぎたあたりの人間が従事をして生産活動を行っている。この中小企業が集積をすると、国ではいわゆる産業集積と言うし、我々は、地域では地場産業という言葉になるわけでございます。
この地場産業というのは、私は地元は川口でございますし、子供のときからの触れ合いの中で、もうどう転んでもこれは産業だけの問題ではなくて、要するに地域のコミュニティーなんですよね。やはり地域の行政の方向性だとか町の運営についても一番関心を持たざるを得ないし、持って町の運営にまで携わっているのが地場産業の経営者の皆さんです。そして、そこに携わっている従業員の皆さんも、そういう町への帰属意識とかこういうものは非常に高くなっているわけなんです。
私は、産業従事者が多いからというだけではなくて、やはり日本の独特の中小企業、地場産業というものに対して、これはもうコミュニティーである、町づくりの一環なんだ、こういうふうにぜひ位置づけなければならないと思っています。そして、中小企業が全くクールに事業の採算性だとか立地の有利性だとか、そういうものを考えながら適宜動くようなことになれば、それは町自体のコミュニティーもおかしくなっていくようなことになるのではないか。
ましてや、ここのところ、日本経済が穏やかな回復基調にあるということでもう何カ月も言われておりますが、実態として、大企業に比べて中小企業の回復度合いというのはまだまだ追いついておりませんし、現実の問題で、中小企業経営者は、今回の空洞化に伴い、大企業が海外進出して、そして前だったら景気がよくなれば発注が戻ってきたのが、今はその後発注するべきものが外へ行ってしまっている、こういう中で非常な経営不安を感じておる。この中小企業がしっかりしてくれないと、日本の国の本当の大もとがぐらぐらになるのではないかというふうに私は思っております。
そういう意味で、中小企業の現状の経営状況だとかそれから今後の景気回復の見通し、これについて、国の方では、政府ではどうお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。
○石黒政府委員 お答え申し上げます。
中小企業をめぐる景気認識といいますか、状況認識という御質問だと思いますけれども、委員御指摘のありましたように、我が国経済が緩やかな回復の動きを続けている中で、依然として厳しい状況にあるものと認識をいたしております。
個別具体的に少し申しますと、生産は上昇傾向で推移しているものの、大企業に比べましてそのテンポは緩やかであり、依然として生産水準には大きな差が見られております。また、設備投資につきましても、中小製造業にも回復の動きが広がりつつございますけれども、これを商業にとってみますと、中小商業の設備投資は引き続き低調なものという状況にございます。
今後の見通しといたしましては、生産の動き等、足元に明るい材料が見られるものの、中小企業の景況感は足踏み状態にあるという認識でございまして、まだ依然として不透明感が残っているという認識をいたしておりまして、引き続き慎重に状況を見続けていかなければいかぬというふうに考えております。
○新藤委員 当然のことながら、これは厳しい状況であるということでは国内で違う認識を持っておる方はほとんどいないのではないか、こういうふうに思いますけれども、そこで、結局そういう事態を打開するための今回の臨時措置法案だというふうに思っております。
そして、加えて、今回私が大変ありがたいなと思っているのは、橋本総理もいつもおっしゃっておりますが、いろいろな演説をされたり、それから所信表明でも触れられておりましたが、今後の日本経済の発展を支えるのは物づくりなんだと。そして、先ほど大臣は、古きをたずねて新しきを
知れ、こうおっしゃいましたが、まさにそのとおり、日本の歴史を振り返ってみると、我々の国の発展は職人の物づくりの腕によって支えられてきた、こういうことだと思っております。
そういう意味で、よく総理がおっしゃるのは、大田区には、NASAのスペースシャトルの部品を開発したんだ、おれがいなければあのスペースシャトルは飛ばなかったんだということを、ちょうど打ち上げのときに総理は技術者の皆さんと話をしていたのだ、大分自慢されてしまったんだよという話も聞いておりますし、加えて、昔、江戸から明治にかかるときに、大砲だとか、要するに西洋技術を日本に入れてきた。勝海舟なんかがいろいろな技術をとってきて図面をかいたわけなんですが、しかしそのときに、その図面を見て鋳物でその物をつくったのは川口の鋳物屋さんだったんだよなんていうので、私も地元でございますから、総理が、こっちから言ったわけではないのですが、触れていただいた。事ほどさように、とにかく自分たちで物をつくれるというここの部分は大変に大事なわけでございます。
そういう意味で、今回は、産業集積といっても産地の集積、それから大企業の下請企業群による企業城下町的な集積、それから幅広い基盤的な技術の産業集積、金型だとか鋳鍛造だとかそういうようなものです。こういうものの部分に目を当てて、光を当ててくれたという意味で、大変に私は評価をしているのでございます。
そこで、そのことはもう少し後で聞きますが、ただ一つ言わせていただきたいのですが、大変に政府としては、今回物づくりに力を入れるのだ、中小企業頑張れよ、元気にしろと言っていただいているのですが、これまでの経過を見て、通産省が、または日本政府が、そういう地域のコミュニティーだとか物づくりだとか、それから地域産業集積だとか、そういうものを大事にしているんだ、すごい力を入れているんだ、こういうふうに果たして国が自分たちのことを思ってくれているのかなということになりますと、もちろん政府は一生懸命やっているに決まっているのです。だけれども、現場の地域の皆さんと話をしていく中で、我々は国に支えられている、国がバックアップをして、そういう自分たちの苦しい操業環境の改善だとか技術開発にすごい力が入っているのだとは、そこまでは思ってないのではないか。私は思っていないというふうに聞いております。
この部分で、ぜひやはり、これからこの法案をいろいろなふうに運用していくに当たって、もっとこの物づくりの基盤の重要性、総理がおっしゃるだけじゃなくて、どんどんとそういうことをアピールしていく必要があると思うし、その対策についても幅広く積極的に普及をするように努力をする必要があると思うのですが、今後具体的にそういった観点からどんな行動が考えられるのか、お答えをいただきたいと存じます。
○稲川政府委員 御指摘のございました物づくりの基盤の重要性など、この法案のコンセプトになっておりますものにつきましては、法律成立後、早急に活性化指針という形で策定をいたしまして、その中で具体性を持って世に明らかにしてまいりたいと考えてございます。
また、この法律の運用あるいは各種施策の利用方法につきましては、都道府県あるいは地域の支援機関などが実施します説明会を通じまして、積極的に普及、広報に努めてまいりたいと考えてございます。さらに、その他できる限りの機会をとらえまして、物づくりの重要性、基盤の重要性とともに、政策のPRを行っていきます。
また、現場からの政策ニーズ等の生の声が政策の実施に反映されるように現場との情報交換、交流ということを配慮してまいりたいと思っております。
○新藤委員 そういう、何というのですか、気合いの問題もあると思うのですよ。気持ちの問題でございまして、これは私も地元へ帰っては、どんどんと国が本気で取り組んでいるよ、こういう話をさせていただこうというふうに思っておりますし、それは通産省としてもぜひ、余計なことを申し上げて恐縮なんですが、大体通産政策というのは自分でやりませんので、自分で事業を持って直接執行するわけではありませんで、あくまで実業のお手伝いの部分でございますから、そういう意味で、やはり制度だとか法令だとかそっちの方が強くて、自分のプロジェクトだという意味合いが、我々が受ける感じとしては若干低いわけでございます。ぜひここはそういったことを積極的にやっていただきたい、こういうふうに思います。
そして、今回私が法案を評価するというのは、いわゆる産地だとか特定中小企業集積に加えて、幅広く基盤的な産業集積に対してお手伝いをする、こういう部分を加えたところを評価しているということなんですが、産業政策上の講じられる支援策、通産省として目いっぱい結集したというふうに聞いております。ぜひそこの部分で少し具体的に、どんな内容にそういうことを言えるのか、お聞かせをいただきたいと存じます。
○稲川政府委員 この法案におきましては、産業インフラの整備、研究開発、人材育成の促進、さらに三つ目には新たな事業展開への投資促進という三本を柱といたしまして、省を挙げまして地域の産業集積の活性化に政策を重点化しております。
この結果、具体的には、この法案の適用を受けます集積のみを対象とした予算措置としては八十一億円を計上いたしてございます。研究開発施設・機器、人材育成施設、賃貸工場等の産業のインフラ整備、それから中小企業の新商品・新技術開発、人材育成への支援等が内容でございます。
そのほか、地域における研究開発の重点的支援、技術を核とした新たな事業のもととなる特許技術流通促進、産業集積の活性化のために活用される関連予算を含めますと、総額で二百二十五億円の計上になります。
また、都道府県知事による計画の承認を受け、新たな技術開発や新分野への進出を行おうとする事業者に対しましては、こうした予算面以外にも、新たな設備投資に係ります特別償却制度、政府系金融機関からの低利融資や債務保証など、各般の支援措置を手当てしております。
さらに、建設省の道路整備事業、それから労働省の雇用・能力開発施策、文部省の文教施策など、関係省庁とも密接な連携を図りつつ、総合的な施策を講じまして、その効果を最大限に発揮するように政策を構築いたしてございます。
○新藤委員 すばらしい内容なんだと思いますが、これに加えて、本法案が目的とする産業集積の活性化ということで、事業者の活動、特に、先ほども申し上げましたように中小企業の活動がポイントになるんだ、こういうことでございます。
やる気のある中小企業を元気にしていくような、そういう対策を行っていくことが大事であると私は思うのですけれども、これもやはり厳しいですよね。九〇年から九四年、ここの部分の製造業全体の出荷額、これがマイナスの七・五%。これに対して、いわゆる今回の基盤的技術産業と言われるような金型製造業、これはマイナス二三%。それから電気メッキなんかも一三%ということで、非常にこういう基盤的技術産業の部分、それは大半が中小企業というか、ほとんど中小企業ですから、そういうことで逆に弱まっているということなんだと思います。
そこで、この法案の中で、中小企業の支援の援護策というか対策、ここの部分はどんなふうになっているのか、お聞かせをいただきたいと存じます。
○田島政府委員 お答えを申し上げます。
何とかの産業集積といいましても、そこに実際に御商売をやっておられる方の大部分は中小企業者でございます。そういったことから、そういった中小企業の皆様方に元気を出していただいて、積極的な事業展開をやっていただくということが極めて重要でございます。こうした観点から、この法案におきましては、県が活性化計画をつくられるわけですが、それをベースに研究開発とかそういった積極的な事業展開を行われる中小企業者の皆様方を、予算や税や財投を総合的に活用して
御支援を申し上げる、こういうことにいたしております。
多少具体的に申し上げますと、新たな技術や商品の開発などに取り組む中小企業の皆様あるいは組合等に対しまして、補助金、低利融資、設備投資減税などといった御支援を申し上げる。そういったことに加えて、組合やあるいは地場産業振興センターあるいは公設試験研究機関等が、人材育成とか販路開拓とか、そういったことをやって中小企業をお手伝いするというような事業に対しても助成をするというようなことにいたしておるところでございます。
○新藤委員 いろいろなことをお考えいただいて対策を打っていただくということでございますので、引き続き、これはもうやってみなきやわかりませんので、どんどんとやっていこう、こういうことだと思います。
そこで、少し総括的にお話をさせていただきますと、今回の空洞化の問題というのは非常に深刻である、こういうふうに思っているのです。その大前提というか一番の問題は、何といっても高コスト構造でございます。ですから、この我が国の高コスト構造に耐えかねて、技術力もあり競争力のある企業、国内にもいられるはずのものまでが外に出ていってしまう、これは非常に問題なんでございまして、しかし、それは別の観点から、土地それから税制、流通機構、こういうものを総合的に今回の橋本総理の掲げる六大改革の中でやっていかなきゃならない。まさにそれは日本の弱みでもありますので、この弱みを直すための高コスト構造是正だ。それにも中小企業の浮沈は非常にかかっている、こういうことだと思うのです。
しかし、これともう一つ私は着目しなきゃいけないのは、優秀な技術力を背景にして、大企業ではできない、それこそ本当の職人芸でずっと積み上げてきたものの集積によって、あの会社じゃなきやできないとか、あのおやじじゃなきやできないよ、こういうような優秀な技術力が日本にはあるんだ、それが橋本総理いわく我々の国の財産なんだ、こういう日本の強みだと思うのです、この技術力というのは。これは世界じゅうのだれもが認めていただけるところではないかな。この技術力をいたずらに外に出すんじゃなくて、どうやって国内でそれをうまく活用できるようにするか。そこの部分の、いわゆる研究開発力だとか技術力だとか、それから集積することによっての恩典を与える、こういう意味で私は今回の特定産業集積活性化臨時措置法案というものが生まれたんだなと自分なりに解釈をしているわけでございます。
いずれにしても、この問題は非常に総合的な観点から対応していかなきゃいけないのじゃないか、こういうふうに思うのですけれども、考えてみると、先ほど予算の割り振りが、今回の法案で直結予算が八十一億、新法関連で二百二十五億ということで、これは胸を張ってお答えになられたのでしょうが、考えてみると本当に小さい予算ですよね、国の産業を生かすというのに。今財政構造改革元年でありますから、余り大それたことを言つちやいけないのでしょうけれども、そもそもが、通産省の予算が三千四百億ぐらいですか、中小企業関連で千二百億、ここをもうちょっと何か枠組みを変える必要があるんじゃないか。私は、もっとどんどんとこういう部分については予算をつぎ込んで、そのかわり、確実にみんなが喜ぶように、また収益が改善できるような、そういうきっちりとした対策を打っていく必要があると思うのです。
ですから大臣には、とにかく豪腕大臣でございますから、確実にこの法案を早期に制定するとともに、この運用をどんどんと矢継ぎ早に、先ほどのいろいろな御質問の中にもありましたけれども、計画をつくったり周知徹底したりしなきゃいけないわけですから、こういう部分を実施をお願いしたいというふうに思うのです。こういった、ちょっと大ぶろしきになっちゃいましたが、日本の産業空洞化対策、これをどうやって総合的に対策をやっていくおつもりなのか、これはぜひ大臣にお答えをいただきたいと存じます。
〔小川委員長代理退席、小此木委員長代
理着席〕
○佐藤国務大臣 きょうのテーマである物づくりということ、いろいろな表現をされたわけでございますが、確かに物づくりという表現自体、私は今の時代にいかがなものかと思っているのです。と申し上げるのは、先ほどからのお話のように、やはりこういうものをつくったという職人というか技術屋が、誇りそして喜びというものをどう感ずるかということなんです。今までは確かに、あの仕事はあれしかできない、おれしかできない、こういうことだった。その考え方が、ややもすると徒弟奉公みたいな考え方につながり、それがいわゆる三K、こういうことにおいて今若い世代の人というのがそういうものに定着しないのではないだろうか、とう思っております。
そういうことで、今のお話のように、これからどういうふうに日本の産業を持っていくかということになると、まさに今中長期的展望として我々が考えている経済構造改革、これを六つの改革の中でもって優先的に私は考えるべきではないだろうか、こう思っているのです。
御存じのように、昨年の十二月に経済構造の変革と創造のためのプログラムを閣議決定したわけですが、その中には具体的に新規産業を生み出すという観点、もう一つは国際的に魅力ある事業環境をつくり出す、二つに分けて、新規産業、これが非常に国内に関係あるわけですが、それに関しては、個別産業分野ごとのニーズに対応した規制緩和、人材育成、技術開発、こういう総合的な施策をするということ、そして新規産業創出にかかわる共通の課題を解決するための資金、技術、人材面の施策、こういうことを推進していくことにしてありますし、今申しました国際的に魅力ある事業環境の創出という点では、高コスト構造是正のための規制緩和、そしてまた企業と労働に関する諸制度の改革、その中には御存じのように持ち株会社の解禁だとか税制の見直し、こういうものが入っておりますし、また、地域の産業・技術集積の活性化、こういうような施策を進めていこうということでございます。
それで、この法案の着実な実施によって、今申したように、今までと違った新しい意味の物づくりというもの、これがやはり国の基盤となってきて、そして国際的に魅力ある産業の集積地域もできる、活性化してくる、かように思っているわけでございます。
○新藤委員 これは、理論といっても難しいのですよね。非常に難しいと思います。お考えはそのとおりだなというふうに思うのですけれども、特にこれからのこういう通産省政策を進める上でも、本法案には入っておりますから、私はこれをもっと追求すればいいなと思っているのですけれども、いわゆるインフラ整備において建設省と連携するのだ、それから、技能の継承支援という意味では労働省ともやりますよ、こういうふうになっております。
それから、先ほどの中小企業庁長官のお話のように、何か学校に行ったらこういう汚いところということで、あれは逆に、それこそ文部省との連携プログラムの中で、私は今教育の問題について、これは文部省の教育改革プログラムのところで言っているのですけれども、僕はあっちで発言しているのですけれども、子供たちに、こういうような技術力があるんだよ、こんな人たちが一生懸命働いています、これを社会科見学をやったり、中学、高校ぐらいになったら、あなたの身近にあるこれは、我々の技術によって実はこんなふうにしてやっているのですという、こういう部分は、子供たちに就業機会の枠を広げるという意味からも、ぜひこれは文部省だって入れていかなければいけない話なのではないかな、こういうふうに思います。
それに加えて、私、最後の質問にさせていただきますけれども、これは直接通産省だけで片づかない問題でもあります。しかし、あえて言わせていただきますと、結局のところ、今までの我が国の産業立地政策というのが、要するに全総以来、
大都市での工業、産業の立地の抑制と地方への分散、こういうものを大前提にして、制限に関する法律があったりとか、要するに企業の集積、産業の集積は人口集中につながる、これを均衡ある国土の発展ということで分散させようということでやってきたのだろう、こういうふうに思っております。
しかし、結果的には本当の地場でやっている人間までがいられなくなってしまって、特定産業集積地域の中においても空洞化が発生してしまっているのですよ。これは、やる気のある企業とそうでない企業がある、技術力のある企業と、そうでない追いつかない企業がある。当然、淘汰はあります。そういう中で産業集積地の強みというのは、結局、そこならば工場操業関係に対して非常に周辺の理解が得られやすいということがあります。それから、関連の工場群や企業がいっぱいあって、ねじ屋から部品屋から、いろいろな作業がトータルでその地域でできるというので便利なんですよね。だから集まってくるわけなんです。
だけれども、これからそういう中で淘汰が行われて、さあ土地があいた、それは決して大きな土地ではありません、何方平米とかというような土地ではないのです、せいぜい二、三千平米から、大きくても五千平米ぐらい、そんなようなレベルの土地があいてしまった。しかし、そこは国の都市計画というか、大都市圏には工場は要らないよという前提において、そこに入れないわけですね。今ある会社、工場をもうちょっと増改築する部分では大分緩和されてきたと思っています。だけれども、せっかくその産業集積地の中で、そこではまだ操業ができるにもかかわらず、別の企業が、ああそういう地区なら私も行くよと。大体、都市周辺で近いから便利だというのも、これまた立地が集積した原因でもあるのですから、そういういいところなら行くよといったときに入れなくなってしまっているわけなんですよね。ですから、やる気のあるところまで完全に外に出ざるを得なくなってしまう。それは産業集積のメリットを生かせなくなってしまうのですよ。
だから、そういうことを考えると、ぜひ住工共存というのを前提に置いて、今度やる五全総の中においても、この工業立地、産業立地に関しての土地利用のあり方をもう少し見直してもらいたいな、私はこういうふうに思うのです。
工業地域に当たり前のように――工業地域ならば当たり前なんです。だけれども、大体、地場産業とか中小企業が集積しているというところは、意外と準工業だとか、もともとから集積しているのですから、その集積しているところを現行追認型で都市計画が用途を決定しているわけですよ。だから準工業の中で、どっちでも建てられるようなところに産業集積というのは意外とあるのですよ。ここのところは今の考え方を切りかえないと、もう完全にアウトになってしまうわけなんです。
そういう意味で、ちょうど今、国でも大分そういう方向になってきているのですよね。産業構造審議会の産業立地部会、「今後の地域産業政策・産業立地政策の検討の方向」というようなことについては、工業再配置促進法、工業等制限法、工場立地法、こういうものを含めて、企業活動のグローバル化、我が国産業の空洞化懸念を背景としつつ、地域における内発的、自律的発展の支援を重視する方向へ見直しを行うこと、こういう方向が出ております。
今回の法案を実効あるものにしていくためには、結局我々が集積をして、この町は産業集積の町なんだ、自分たちがこういうふうにやってきたところに新しい仲間も入れられるんだよ、やる気のある人がもっと固まっていくよ、こういうことになるきっかけにもなるんじゃないかというふうに思うのです。
とにかく、中小企業対策とか産業政策というのは、全部に適用できる政策というのはあり得ないと思うのですよね。だって自分たちがやらなければ、結局、国や我々はお手伝いするだけなんですから、そのやる気のある人たちに対して、もっと特段のいろいろな配慮をしていく必要がある、このように思っております。
そういう意味で、くどくどと申し上げておりますが、この法案を機に、さらにその辺の産業立地政策上の今後の方向性は、私は住工共存と言っています。人によっては住工共生と言っております。国にはこういう言葉があるのかどうかわかりませんが、私が一つ聞いているのは、住工混在というのは聞いています。住工混在地域は、うまくやれば住工共存地域になれるわけでございまして、これがうまくいくと、本当の意味で中小企業が元気になれるのではないか、こういうふうに思っておりますが、ぜひそういったことで御見解をお聞かせいただければありがたいと存じます。
○佐藤国務大臣 おっしゃるように、この住工共存というのは、大変我々も関心を持っておるところでございます。
今、新藤委員言われましたが、やはり物づくりの場合には、私、歴史的に見て、いわゆる城下町と言われている、それからまた産地、厳密に言うとやはり違うと思うのですよ。それからまた、何にもないところにこれから新しい産業というものが生み出されて集まる、こういうようなことがある、こういうふうに分類できるのじゃないだろうかと思います。
そこで、今おっしゃるように、住工、そこに新しいものが割り込んでいけるというけれども、そういうのが、例えば城下町だとなかなか入りにくいけれども産地なら入りやすいとか、いろいろな問題があると思うのです。
そういうことで、今の御指摘の点、私たちにも非常に関心がございまして、具体的な施策については御指摘の点も踏まえて今後引き続き検討してまいりたい、かように考えております。
○新藤委員 やや時間が余っておりますが、今回のこの新しい法律、ぜひとも実効あるものにしていきたいと思っております。これは政府にお願いするのではなくて、我々が地元へ帰って、こういうことで国も真剣に地域の中までおりてきて考えているんだよということを、これは我々もPRしたいと思いますし、それを仕事のベースの上に乗っけていきたいと思っております。
そして加えて、各省との連携をうまくとっていただいて、手続だとか、もうこれは事務的なものになってしまいますが、意外とそういうことがうまくいかないと実効が上がらないわけでございまして、それは私が言わなくても、技術的な問題ですから政府の皆さんがよく御存じだと思います。
我々も目いっぱいにお手伝いをしていきたい、こういうふうに思っておりますし、そういう意味でこの法案の成立を御期待を申し上げるところで質問とさせていただきます。ありがとうございました。
平成9年一般会計・特別会計等予算(質疑)衆議院予算委員会第六分科会-1号 1997年03月03日
平成9年一般会計・特別会計等予算(質疑)
140-衆-予算委員会第六分科会-1号 平成09年03月03日
○新藤分科員 自由民主党の新藤義孝でございます。
きょうは、産業政策にかかわる、特に中小企業の関係についてお尋ねしたい、このように思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、全体の経済概観でございますが、日銀の金融経済概観によると、我が国の景気は穏やかな回復を続けており、民間需要は底がたさを増している、こういうことでございます。そしてまた、ちょうどきのうの日経新聞を見ますと、上場企業は四年連続の増益だ、今期の経常利益も八・九%アップだ、こんなふうに出ております。要するに、経済的な見地からいうと、景気は底がたさで少しずつでも回復しているのだ、こういうことになるわけなのでございます。
それに対して、では本当の地場の、地域で営業活動をされている中小企業の皆さんたちはどうなのか。私は、地元の企業、川口でございますが、大変中小企業の集積の多い町でございます。皆さん方とお話ししている中で、景気がよくなったなという話は一度も聞いたことがないわけでございます。
そういう中で、よく調べますと、大企業の回復に比べて中小企業の回復のテンポというのはまだまだだと。中小企業庁の調査によっても、平成八年の七月から九月期以降足踏み状態が続いているという、大企業の回復、日本経済の回復基調に対してこんな状況が出ております。また、製造業の工業生産指数を見ても、平成二年を一〇〇とした場合に、大企業が一〇二、中小企業が九五・二だ。こういうことで、数字を見ていくと、言われている全体の経済の話と中小企業との間には相当な隔たりがあるのではないか、このように思っております。
これについて認識を聞こうかなと思いましたが、しかし、これは大体こういうことなわけでございまして、これを前提にして先に進めたいと思います。
こういうことで、中小企業はまだまだなのだ、何とかしてあげなければいけない、させていただきたい、こういうふうに思っているわけなのですけれども、そういう中で、特に私が今心配しているのは空洞化、これもよく皆さんから御指摘いただきます。空洞化も、やはりちょっと調べますと、設備投資面においても、今回中小企業の先行性というのは失われている。それから、要するに企業マインドでいえば、今までの不況は、どんなに苦しくても頑張っていれば、景気が回復すれば親企業からまた発注が戻ってくる、こういうことだったと思うのですが、今回ばかりは、皆さんからお話を聞いていると、なかなか戻るのは難しいのじゃないか、こういうようなことも聞いております。
これの背景になっているのは、やはり大企業の海外進出。これは八五年のプラザ合意以降どんどん進んできておりますが、家電製品の海外生産比率で見ると、八五年から九四年までの十年間で、カラーテレビは三八%から七八%に海外で生産が進んだ。ビデオが六・三%から五三%、冷蔵庫が一八%から四四%と、こういうふうにすごい勢いで海外展開が大企業で図られておる。そうすると、初期のころは別にして、もう最近では海外での生産の品質だとか生産体制がしっかり整ってしまってくると、一番最初のころに大企業が海外へ出ていって、そして製品調達は国内の下請だとか部品メーカーに発注していたものも、これも含めて海外に行ってしまっているのではないか。そういうことで、企業の収益は上がっているのだけれども、中小企業に仕事の戻りが来ないのじゃないかという心配につながっているのではないか、こういうふうに思うわけなんです。
ここで、ちょっと能書きが長くなって恐縮なんですけれども、私は中小企業ということに対して少し自分なりの定義がございます。大企業に対する中小企業ということではなくて、中小企業というのは、まさに地域産業、地場産業化しているわけでございます。それは、商売だけの問題ではなくて、地域と密接に結びついた企業というものは、これはもう完全にコミュニティーの一部になってしまっている。例えば、町会運営だとかそれからいろいろな行政に協力をしたり、町を運営していく中に本当にすばらしいほどに地場産業の、地域集積をされた産業の皆さん方が、自分たちの仕事だけではなくて、町の問題として産業が集積しているということでございまして、私は、地場産業は地域コミュニティーだ、こういうふうに思っています。ですから、空洞化等々で中小企業の業績が回復しない、元気になってもらわないと町自体も意気消沈していってしまうということになる、私はこのように思っています。ですから、単に産業政策上だけではなくて、我々の地域のコミュニティーの問題としてやはり中小企業の振興というものを強力に考えていくべきだと思っておるわけでございます。
そういった観点から、いわゆる中小企業、我々は地場産業と言います。お国の方では、地域の産業集積、地域集積産業と言うわけでございますが、この問題に対して通産省としてはどういった対策を講じようとしているのか、御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○稲川政府委員 御指摘のございました大企業の海外展開に伴う空洞化によりまして、産業集積、地域のコミュニティーに大変大きな打撃を与えております。
我々、二つの産業集積を念頭に置いて検討を進めてございますが、一つは自動車、家電などの量産型産業、いわば基幹産業を支えてまいりました足元にあります鋳鍛造、メッキ、金型、試作品製造などのいわゆる物づくりの基盤でありますサポーティングインダストリーの集積でございます。いま一つは、産地などの形態で地域経済の自律的発展基盤でありました地域の中小企業の集積でございます。この二つの産業集積を念頭に置きながら空洞化問題を検討しているところでございます。
他方で、先ほど不況を耐えれば発注が戻ってくるかという先生のお話がございましたが、我が国の産業構造、大変大きな変化をいたしてございまして、我が国製造業への需要は、むしろ最終消費財よりも資本財、生産財へと変化をしておりますし、また、大量生産の一般仕様品から小ロット生産の特殊仕様品へ移行することなどの傾向が見えてございまして、資本財、生産財や研究開発、試作を中心とする分野に需要自身が大きく変わりつつあるという認識がございます。このため、我が国地域の産業の空洞化を防止しますためには、この需要構造の変化、産業構造の変化に対応しつつ新たな活力を生み出すことが必要でございまして、そのために、技術水準を上げる、あるいはネットワークの形成を広げる、新分野へ進出をする、こういったことのための基盤整備を通じまして、地域の産業集積の活性化を図ることが不可欠
ではないかというふうに考えてございます。
このため、今国会に特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案を提出いたしましたところでございまして、この法案によりまして、産業インフラの整備、研究開発、人材育成の促進あるいは新たな事業展開への投資促進などを柱といたしまして、地域における取り組みへの体系的な支援を推進したいと考えてございます。特に、建設省の道路整備事業あるいは労働省の雇用・能力開発施策、さらには文部省の教育研究施策など、関係省庁とも密接な連携を図りまして総合的な施策を講じ、その効果を最大限に発揮するよう政策を構築いたしてございます。
○新藤分科員 今の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案、これは大変すばらしい法案だと思うのです。
そこで、大臣にお尋ねを申し上げたいと思いますが、私、この中小企業の問題は、これはこれからの政策すべてにかかると思うのですけれども、めり張りをつけた運営をしていく必要がある、このように思うのです。要するに、一律、中小企業なら中小企業という枠ですべての皆さんに等しく渡るようにしようと思うと、これはどうしても最大公約数のものになってしまう。やる気のあるところと、それからそうでないところと、これはやはり差はつけていく必要があるのではないかというふうに思うのです。
先ほどサポーティングインダストリーの問題にちょっと触れていただきましたが、まさに私たちの川口はそういう、素形材の鋳物を中心として、それに関連する機械や木型関係がずっと集積しておるわけですね。こういう町で、自分の町の売り込みをしてもしようがないのですが、国の政策によらずに、川口版ニューディールなどと申しまして、公共施設に自分たちの製品をどんどん使ってくれということで独自にキャラバン隊を組んで何かやったりとか、いろいろなアイデアを自分たちで出しながら地域でやっております。特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案、ぜひこれをどんどん進めていただきたいのです。
何か、聞いている話では、地域指定を二十地域ぐらいして進めるのだということなんですが、そこで大臣にぜひ御見解というか御決意のほどを御披瀝いただきたいのは、大変にらみのきく、実力、剛腕大臣でございますから、私は、これの肝心なところは、通産省だけの政策ではなくて、もし事業者が魅力を感じるとするならば、先ほど申しました地域コミュニティー、町の運営の中での話だとするならば、要するに、いろいろな関連施策、よその省庁との連携によって総合的な町づくり事業の中に組み込められるかということだと思うのです。産業関連のインフラの整備、それからいわゆる労働関係の条件整備、こういうものが通産省主導にして強力に総合的なものになったときに、今回の中小企業に関するてこ入れ策が功を奏するのではないかな、私はこう思うのでございますが、ぜひ御決意のほどをお願い申し上げます。
○佐藤国務大臣 新藤さんにお答えいたしますが、今委員のおっしゃるとおりだと思うのです。
ただ、中小企業といっても、いわゆる工業部門と商業部門、これは大分違うと思うのです。今のお話のように、新藤さんの地元川口というと、鋳物の町ということで町ができ上がり、そこにおいて新しい技術が生まれ、まさに政治も経済も鋳物で育ったなというような気がしております。
それで、これから私の方で御審議をお願いする地域産業集積活性化法案、これは今おっしゃるように、俗に言うめり張りをきかしていかなきゃいけない、それから地域の特性をそれぞれ生かしていくということが大変大事だと思うのです。ですから、この中においては、技術開発、販路の拡張、人材育成というのを三本柱として幅広い支援を展開していく、各地域の中小企業がその必要に応じて支援策を組み合わせ、新たな事業の展開に活用していけるよう最大限の工夫をしたものであります。
こうした施策だけではなく、中小企業対策を使いやすいものとし、中小企業の方々のさまざまな悩みや課題に的確にこたえ得るよう、まず窓口機能の強化ということ、そして民間や大学の人材を活用した広範かつきめ細かなアドバイス事業の推進ということ、開発初期段階の技術シーズの助成の対象化ということで、平成九年度の予算においてはこういった施策の充実を図っていきたいと思うわけでございます。
全く委員の御指摘のとおりでございます。
○新藤分科員 ありがとうございます。いささか私どもも、町の中で自分で目の当たりにしておりますので、しかし、これは私たちの町だけではないと思いますので、御賛同いただいたと思っておりますが、ぜひ今後ともよろしくお願いを申し上げます。
それから、余り時間がなくなってきましたので、もう少し大臣にお尋ねしたがったのですが、ちょっとこれは、規制緩和のことについてはまた次の機会に回させていただきます。
そして、一つ大事な問題として、空洞化の進行、それから規制緩和、これとあわせて時短問題が大変大きな問題になってくる、このように思っております。
中小企業にとって、単純に操業時間が短くなってよかったなと喜ぶかというと、実態はなかなかそうではないわけでございまして、収入が減ったらどうしようと働いている方は思うし、それから雇っている方は、今までより時間数が減った、少なくなったから、じゃ賃金アップしろよと言われてもこれまた苦しい、こういうところだと思っております。
そういう中で、今回は、いわゆる二年間の指導期間というものを設け、時短促進法の廃止期限を二年延長するんだ、こういうことで法案も出ております。私も、この時短の意義とか、それから国際世論の中で国是になっている、こういうことも含めて重々承知をしておりますけれども、この場合に幾つかの問題が出てくると思われますので、具体的にどう対処するのか、これは中小企業庁にお伺いしたい、このように思っております。
まず、二年間の指導期間において具体的にどういう指導が行われるのか、そして、労働省の関係で中小企業庁としてはどんな役割を果たしていくおつもりなのかということでございます。それから、下請の中小企業が時短を進める場合には親企業の発注のあり方というものが、やはりこれは決めておかなければいけないと思うんですが、親企業さんに関してどういう指導が行われるのか。それから、この週四十時間労働に対する賃金の扱いの問題、これも労使間の問題なんだ、労働省ですよということかもしれませんが、しかし、中小企業庁としてこの部分にどういう御指導をされるおつもりなのか。それから最後に、やみ残業というのがあるわけでございます。いわゆるやみ残業というものが一般人から告発されたときに、仮にそういうことがあったときに、中小企業の経営者が直ちに罰則の適用を受けないような措置が法的に講じられているのかどうか。これはあってならないことなんですが、ただ、実態上時々聞く話でもあるわけでございまして、この辺についてお答えをいただきたいと思います。
○田島政府委員 労働時間の短縮の問題、私ども、ゆとりと豊かさの実感できる社会といったようなことからも、それから中小企業者の人材の確保という観点からも、大変重要な問題と考えてございます。
ただ、中小企業の皆様方、一生懸命に時間の短縮には取り組んでいただいておるわけでございますけれども、先ほど先生お話ございましたように、今景気の観点からも構造的な対応という観点からも、大変厳しい状況でございますものですから、来年の四月から四十時間制に移行するという場合に、それができるだけ円滑に移行するようにということで、政府によってきめ細かい援助、指導ということを規定する時短法という、これは労働省の法律でございますが、この改正案を今国会に御提案を申し上げておるところでございます。
また、来年度の予算案におきましては、四十時間労働制への移行に取り組む中小企業者の皆様に
助成金を創設するということで、いろいろな環境整備というようなことについても御支援を申し上げるということになっておるところでございます。
いずれにいたしましても、引き続き労働省とよく相談をして進めたいと思います。
先ほど先生からお話のございました点につきまして、やや具体的にあれしますと、指導、援助のところは、先ほど申し上げたように、時短法を改正しまして、二年間は指導、援助に徹するということで円滑な施行を図るということでございます。
それから、下請の関係につきましては、下請振興基準というガイドライン、私どもございますが、その中に、例えば、夜遅くに発注をして朝一番で持っていらっしゃいといったようなことはやはり適切ではありませんよといったようなことを盛り込みまして、いろいろな機会、大企業の下請の窓口の担当者等々に対する研修の機会等を通じて周知徹底を図っておるところでございますし、引き続きそういった努力をいたしてまいりたいと思います。
賃金の扱いのお話もございましたけれども、この点につきましては、労働省の御意見にもございますが、時間当たり賃金単価が下回らないというようなことでありますれば、大変いろいろ厳しい状況にございまして生産性も上がっていないという中小企業の対応の一つのやり方として、労働基準法上も認められるのではないかというようなことでございますので、そういった取り扱いをやむを得ない場合はしていただくというようなことを考えておるところでございます。
やみ残業の問題、最後に御指摘ございましたが、当初の二年間につきましてはそういったことも含めて御指導をし、できるだけそういうのが守られる状況を実現するということで対応いたしたいと思います。
いずれにしましても、労働省とよく、私どもも中小企業の実態を御理解いただきながら進めてまいりたい、こういうふうに思ってございます。
○新藤分科員 ただいまの問題は、ちょこちょこっとやる問題ではないわけでございまして、一つ一つが非常に重要な問題だろうと思います。
そして、例えば下請発注基準についても、これはこれまでも、時短を除きましても今まで親企業と下請の関係というのは幾つもあったわけですね。だけれども、現実にはなかなかそれが行き届かないというところがあるわけで、あくまで実業の世界の話になってしまいますから、よく注意深く見ながらやっていきたいと思っております。
特に、賃金の扱いの問題は、これは質問ではありませんが、賃金の問題については、ややこしいんですけれども、基本的には労使間の話し合いで解決すべきだ。そして、賃金が合理性があるものであれば、時間当たり賃金が減少しないと、労働時間の変更との関係から見て合理性があるものであれば、労働基準法の適用上問題とならない。うんと難しいんですけれども、要するに、ある範囲までは減っても問題にしないよということかなと思っております。しかし、なかなかこのようにはいかないんじゃないかな、やってみてからの話なんですけれども、これは今後の課題ではないかなというふうに思っております。また、次回、改めてこれはじっくり詰めていきたい、こういうふうに思っております。
そして、最後の御質問をさせていただきますけれども、今まで中小企業をめぐる情勢ということで、空洞化の問題であるとか時短の問題に少し触れさせていただきました。これとあわせて、もう一つ別の観点から、今度は中小企業を支える人材の確保、こういう観点から質問させていただきたいというふうに思います。
特に、中小企業の町工場、こういうところについては、今までの高度経済成長を支えた、そして最先端の技術を保有していた町工場というのはいっぱいあるわけなのです。この特殊技術というのは工場の職人によって引き継がれてきた、こういうふうに思っております。要するに、こういう技術というのは特殊なものですから、中には職人芸のようなものもございます。こういうものも含めて、長い年月をかけて、最先端の機械をもってもなかなか代替できないような技術を持ったところまであるということでございます。
しかし、そういう中で、私のところの町の川口なんかでは特に鋳物に顕著なのだと思うのですけれども、若い人がなかなか入ってこないということでございます。本当の基礎的な素形材ですから、高度経済成長を支えた部分なのだけれども、今いわゆる三K職場ということで若者から敬遠されてしまっている。やる気を出している若い人というのは、結局工場を継ごう、工場をやっていこうと思っている方でございまして、この工場で働いてやろうという気持ちを持った若い人が少ないのではないかな、こういうふうに思うわけでございます。
橋本総理がよくおっしゃる、私はお聞かせいただいているのですが、私たちの国は職人の国家だ、物づくりの国家だ、技術を持った人の手によって国が支えられてきたのだ、こういうふうにおっしゃっております。それでは、この部分を具体的に、特に製造業にかかわる技術者の確保そして育成、これをどうやって図っていくのかということなのです。若い人が入ってきてくれないというのは、社会全体における物づくりの現場に対する評価の低さ、これが反映されているのではないかな、総括させていただくと私はそんなふうに思っております。
これに加えて、やはり工場で働く技術労働者が自分の仕事に誇りを持って、そして子供にこの仕事はぜひ継がせたいのだ、やらせたい、こういうふうに思わせるような気風が今の日本に欠けているのかな。要するにホワイトカラーとか大企業志向、こういうことなのかなというふうに思うのですけれども、気持ちだけではなくて、やはり私は、実際にこういう人たちに誇りが持てるような、そういう社会的なステータスと処遇を、技術を持ったことによって与えられる処遇について、もう少しきちんと形をつくっていく必要があるのではないかな、こういうふうに思うわけであります。
そういう観点から、現在、技術労働者に対してどういう育成策を行っているのか、また、その育成策が社会的なステータスを得られるようなシステムになっているのかどうか、そこのところをまずお伺いしたいと思っております。
それから次に、ドイツのマイスター制度、要するにこれはドイツ固有の技術労働者のシステムなのですが、これについてどんな評価をしているのかということをお聞きしたいと思います。
それから最後に、若手の人材を確保しなければいけない、これはだれもがわかることなのですけれども、このために、やはりすばらしい技術者にきちんと日を当ててあげる、それから待遇を考えてあげる。それとあわせて、そういう人たちが今こんなことをやっているんだということを子供たちに教える必要があるのではないか。これも、教える必要があるのではないかと言うと、いいですねと言うけれども、施策が具体的にないのですよね。だから、こういう部分は特に文部省と協力して、子供たちの中にボランティアの気風を生み出すということと働く喜び、そして技術のすばらしさ、こういうものを子供のときから啓蒙していく、そして触れさすことができる、そういうことをやってみたらどうかな、こういうふうに思うのでございますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
○田島政府委員 先生御指摘のとおり、戦後我が国の製造業の成長を支えてきたのは中小企業でございますし、なかんずく、生産の現場で働いてくださっておられる技術者あるいは技能者の皆様方に大きく依存しておるということをよく認識をいたしております。
一方で、御指摘のように、空洞化の進展等々、物づくりの基盤が失われつつあるという懸念もあるところでございます。技術者、技能者については、例えば鋳物工でございますけれども、五十代後半をピークに、年齢が下がるにつれて技能工が
少なくなっているといったようなこともございまして、高齢化が進む中で若者の製造業離れ等が進む、今まで培ってきた技術を次の世代に継承することも難しくなっておるというような状況ではないか、こういうふうに思っております。私どもの国の製造業の発展にとって、やはりゆゆしい問題でございます。
技術者、技能者に対する問題、先ほども御議論ございましたけれども、今国会で御提案を申し上げております集積活性化法といったような法律、その他各種の技術開発の施策等々、産業そのものがやはり活性化をする、元気のある形になるといったこと。それから、中小労働力確保法という法律もございますけれども、職場環境を改善をしていくといったような努力、不断の努力というのが大切でございますし、こういったこととあわせて、現在私どもも、これからさらにどういった対応をしていったらいいのかというようなことを調査検討に着手しておるところでございます。
この場合に、物づくりの大切さが理解をされるということ、これが大変大事であるということもよく認識をいたしておりまして、私どももいろいろな有識者、学識経験者等々からの御意見なんかも徴しておりますけれども、そういった中でも、技術に対する社会的評価の問題あるいは物づくりに対する社会的評価の問題が重要だという御指摘も賜っております。
したがいまして、産業界で活躍をされておる立派な技術者や、あるいは熟練の技能者の皆様方の実際のお話を、学生はもちろんのこと、一般の方々、子供さんに至るまで、いろいろなお話をしていただいて、物づくりのすばらしさとか楽しさを理解していただくといったような機会をふやすことも大変重要であると思っておりますし、こういった観点も含めまして、私ども通産省も、局も含めて、いろいろな機会をとらえて、物づくりの大切さについて講演とかシンポジウムとか、そういった努力をいたしておるところでございます。
いずれにいたしましても、先ほど申し上げたように、今勉強に着手したところでございますが、中小企業庁もいろいろな補助金等々もございますので、そういったものを活用しながら、あるいは大学校の制度といったようなものも活用しながら、人材育成に係る施策の充実等々に努力をしてまいりたいと思っております。
平成9年一般会計・特別会計等予算(質疑)衆議院予算委員会第三分科会-1号 1997年03月03日
予算委員会第三分科会-1号(質疑)
140-衆-予算委員会第三分科会-1号 1997年03月03日
○新藤分科員 自由民主党の新藤義孝でございます。
何点か御質問させていただきたいと思いますが、最初に、小杉大臣、連日御苦労さまでございます。大変な激務の中ですばらしい御努力をいただいていることをまず感謝申し上げるとともに、敬服申し上げたいというふうに存じております。
まず最初に、大臣に基本的な御所見をお尋ねしたいと思っておりますが、このたび、国の五大改革に加えて教育改革が加えられたということでございます。そして、総理の指示で文部省は教育改革プログラムというものを取りまとめたということなんでございますが、まず最初に、今回なぜ新たに教育改革が取り上げられたのか、そのあたりの意義というか、必然性、必要性について、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。
○小杉国務大臣 御指摘のとおり、総理から新年早々に教育改革プログラムをまとめるようにという指示をいただきまして、一月の二十四日にこれを提出いたしました。今、国として、行政、財政、金融、経済構造、社会保障、そういった分野で五大改革を掲げているわけですけれども、それらの改革のすべての基盤である教育、この教育の改革こそこれと連動してやっていく必要があるんではないか、そういう見地からまとめたものであります。
内容については、また、お尋ねがあればお答えいたします。
○新藤分科員 それでは、これは御担当の方で結構なんですが、これまで教育制度の改善施策というのは、いろいろな提言、答申が出されてきたということでございます。もう私が言うまでもなく、昭和二十八年を第一回とする中教審、そして臨時教育審議会、さらには、昨今の行政改革委員会の中での教育にかかわる部門、それから地方分権推進委員会の中での教育にかかわるところと、それぞれずっと文教関係事項の改善施策というものが出されてきているわけでございます。それから、六十二年八月には、これは今でも続いていると思うのですけれども、文部省教育改革実施本部というのができているわけでございます。ずっと、教育制度の改善、改良、これについては営々と御検討をいただいて、そしてまた順次施策としてやってきている。
そうすると、今回の教育改革プログラムの内容で、これまでの中教審や行革委員会やそれから臨教審だとか、そういうもので提言されている以外に、新しい大きな項目というものは何かあるのでしょうか。
○富岡政府委員 先生御指摘のとおり、教育改革につきましては、臨時教育審議会とか、それから幾次にもわたります中央教育審議会、さまざまな御答申をいただいておりますし、また、各政党からもさまざまな教育改革の御提言などをいただいているわけでございます。そういうもの全体を十分現時点で精査しまして、検討しながら、現在とり得る教育改革の方途につきまして、文部省挙げて検討したわけでございます。
その中の内容といたしましては、今までは例えば中高一貫の問題などについては答申等でもさまざま指摘はございましたけれども、今次の教育改革のプログラムでは、これを具体的に、学校制度複線化構造を進めるという観点から中高一貫教育制度の導入の問題とか、それから教育制度の弾力化という観点から特にすぐれた才能を持つ子供に対します大学入学年齢の緩和の問題とか、学校週五日制への積極的な取り組みなどについて、具体的な課題と方針を今回お示ししたということでございます。
○新藤分科員 ちょっと回りくどいような言い方で恐縮だったんですけれども、私、これは持論でございます。専門家の皆さんが、それも日夜御担当いただいている方々が一生懸命やっていることは重々承知をしている上で、あえて申し上げたいのでございますが、私は、改革と名のつくもの、また、総理が今回おっしゃっている、やろうとしている、我々がやらなければいけないこと、それはまさに、明治維新、それから第二次大戦後の新しい民主主義社会、これに次ぐ第三の改革だというふうに言われております。すべてのいろいろなシステムや国家のあり方、そういうものを変えましょう、こういうことになっている。
大臣は先ほど、このもろもろの改革を進める、また社会や国を構成しているそのすべてのもとに教育があるのだ、こういうお考えを示されました。私も全く同感でございます。人がすべて運営し、人がつくり上げ、人が行うものですから。
そういう意味で、今回の教育改革が、一体全体、平成の大改革にどうやってつなげていけるのか。改善と改革の、この言葉の遊びになってしまっては困るのですが、大きな違いがあるのではないか。体制を、形を変えなければいけないのではないか。そういうことができないと、今の閉塞感というか、また子供たちにかかわるいじめだとかもろもろの無気力感、こういったものまでを取り除くのは難しいのではないか、こういうふうに私は思っているのです。
それで、北大の山口二郎教授がいいことをおっしゃっていました。これはつい最近の日経新聞のインタビューの中で、「二〇二〇年からの警鐘」ということなのですが、「教育問題も深刻だ。教育改革は民主主義を担う市民をいかにして育てるかという問題ともつながる。今の学校教育は社会の現状がこのまま変わらないという前提に立っており、それが社会を固定化してしまう要因になっている。これまで見逃しがちだった教育問題は今後、大きな政策課題になるだろう」、こういうふうにおっしゃっています。
私はこのとおりそうだとは言いませんが、少なくとも体制を変えるということ、もちろん内容が伴わなければ話にならないのですけれども。私が今一番疑問にというかじれったいなと思っているのは、教育改革というと、これからの教育のあり方、哲学、理念、こういうものにどっと行ってしまう方と、それから、どうやったら進めるのだ、いつ進めるのだという方法論がごっちゃになってしまうのですよね。我が党でも、教育ビジョンだとかつくっております。いろいろなことをやっています。教育論ばかりは、私もここでこんなことをお話しさせていただいているように、教育を受けた者ならば、そして子供を持っている者ならば、だれでも持っている、物が言えるのではないかと思うのですね。そこで大事なのは、全員がいいではないかとか満足して納得できる制度というのは、これは無理なのではないか。
江戸の藩校体制、寺子屋から、明治になって学校になったときに、それがいいと思ったというよりも、全然違う人間が、社会の仕組みが変わったのだから、運営体制が変わったのだから、今度は
こっちなのだといってつくられたものだと思うのですよね。それから戦後の今の教育制度も、当時はよその国の人まで入って、こういう形でやろうといって変わった。
そうすると、このたびの教育改革が、まさに平成の改革、日本近代史上の三回目の改革をやろうということであるならば、これはもう少し強力な体制をつくることと、それから思い切ったプログラムの内容、今まで提言されてきたものを取りまとめて、その中で具体的に一歩踏み込みましたという、そういう程度で果たしていいのかな、こんな素朴な疑問を私は持っているのです。
○小杉国務大臣 新藤委員のお気持ちは十分理解できます。
私ども、今日本が直面している状況というのは生易しいものではありません。猛烈な勢いで経済が高度化し、国際化が進み、高齢化社会が進行していく、そして情報化ももちろん進んでおります。そうした中で、日本がこれから二十一世紀、従来のような活力を維持しながら発展していくためにはどうしたらいいのか、そういう視点に立って、五つの改革が提唱された経緯がございます。
私たちは、教育の場においても、やはり新しい時代に即応した教育ということを考えなければいけない。そうなりますと、例えばこれからの経済の高度化、先端産業、独創的な産業を育成しなければいけない。そのためには、もっと独創力のある子供たちを育てなければいけませんし、また学術の振興、高度な科学技術教育もやらなければいけない、そういう時代の要請もあります。あるいはまた、情報化に伴うコンピューターとかインターネット、そういった新しい教育のあり方も追求しなければいけませんし、また高齢化社会の中で、介護とかボランティアとか、そういう教育もしていかなければいけない。たくさんの要請があるわけです。国際化にしても、留学生をもっと受け入れなければいけない、あるいは英語教育がいかにあるべきか。そういった新しい時代のさまざまな要請にこたえるために、我々は一体何をやるべきか。
そこで、従来から、御指摘のとおり中教審を初め臨教審、さまざますぐれた提言をされております。これは何もそのときの提言ではなくて、やはり二十一世紀を見据えた、将来のあるべき姿というものを考えた貴重な提言がありました。私どもは、そうした数々の提言なり報告書の中で、実現、改善できるものはどんどん取り入れてまいりました。例えば生涯教育であるとか。しかし、残念ながら国民の合意が得られずに、なかなか実現できなかったような問題もあります。中高一貫教育にしろ、週五日制の問題にしろ、そういう今まで積み残してきたものをこの辺でひとつ何とか実現したいということで、簡単に申しますと、この教育改革プログラムの目標は二つございます。
一つは、そうした新しい時代に対応できる、すぐれた人材を養成するという側面。それからもう一つは、今盛んに言われておりますのは、どうも戦後の教育は知識詰め込み主義ではないか、偏差値教育ではないかという批判も一方にあります。あるいはまた、硬直性とか、均質性ばかりを大事にするではないかという批判もあります。そういうことにこたえて、もう少し個性を持った、また自立心を持った、他に対する思いやりとかあるいは正義感とか道徳心とか、そういった豊かな人間性を育てるという人間教育、人間性というものを重視した心の教育、そういう面も大事ではないかということで、この二つの目標を考えました。
そして、その進め方としては、今御指摘がありましたように進める体制をどうするかということですけれども、私たちはできるだけオープンな形で、単に教育関係者とか学校関係者だけではなくて、広く外に目を向けてオープンな形で、経済界もあるいは地域社会もすべて加わった形で、学校外の社会との提携ということを最大限に尊重したいと思っております。そういう意味では、近々、教育改革フォーラムというようなことで、各界各層を網羅したような定期的な会合もやっていきたいと私は思っております。
それからもう一つは、余り固定的に考えないで、できるだけ柔軟性とか多様性というものを取り込んでいこうということ。それから、単に提言とかプログラムを提示するだけではなくて、このプログラムを一体いつまでにどうするのかという期限を区切って、スケジュールを示したというところに大きな前進があり、また特色があろうと私は思っております。
しかし、いずれにしても、今度の教育改革プログラムは改革のための第一歩でありまして、今いろいろな御意見をいただきましたけれども、これから国会の各党の意見もお伺いし、また経済界とかその他の広い皆様の御意見も加えながら、充実した教育改革を実行していきたい、私はそういう心境であります。
○新藤分科員 強い決意、大臣のお気持ち、お考えは理解をさせていただいたというふうに思っております。
あえて重ねて言わせていただくならば、もろもろの改革、今までの国の転換というものは、外圧で大きく変わってきた。これは総理自身もお認めになっておりますが、大きな力の中で、社会体制の変革の中で行われてきたのが、それが今回はないわけですから、それを自分たちの知性によって切りかえていこうということでございます。いろいろな知性があるわけで、ぶつかり合います。ある時期で、これはもうやるのだ、この形をもっと強力に打ち出す必要があるな。やらなければいけないのは、文部省にやれと言うよりも、国会がしっかりしなければいけないのではないかというふうにも思っております。もちろん文部省の皆さんとどうやったらいいのかということを、もう少し大きな枠組みで、そして強い枠組みをつくるべきではないかな。
今大臣は、全く同じ、わかっているというお考えだと思いますからこれ以上申しませんが、この件については、決して教育の現場で中で教えている人間ではありませんが、いずれにしても、教育改革を進めるということについては大きな関心を持っております。これが、一つこれもできました、従来懸案となっていたのだけれどもようやっとこのことだけはできましたというような程度で進んでいたのでは、これからの次代を担う人間、子供たちを育てる中で、今と大きな差のある子供ができるのかしらという懸念があります。今後も、またぜひそのことについては活動させていただきたいと思っておりますので、きょうはこの辺にさせていただきます。
それから今度は、もう一つ具体的な話で私学助成について、私学振興という観点から何点かお伺いをさせていただきます。
まず、これもまた数字を読み上げていくと時間がなくなってしまいますから、要するに教育を受けている子供たち、学生生徒の中で、大学、短大で八割、高校で三割ですか、幼稚園で約八割、私学に負うところが多いということでございます。そしてしかし、私立と国公立の納付金だとか教育研究条件ということになると、今度は随分大きな差が今出てきているということになっているわけでございます。私立学校の経常費に占める補助金の割合も低下している。私立大学がピーク時二九・五%あった補助率が、平成七年には一二・一%。
これは御存じのことだから、要するに厳しい環境の中で私立学校の果たしている役割の重要性、そしてそういう厳しい状況を認識して、私学振興の取り組みをやはり積極的に行うべきだ、こういうふうに思うのでございますが、特に今年度の予算案において強く取り組んでいただいたところ、そこの部分、どんなふうにお考えなのか、教えていただきたいと思います。
○雨宮政府委員 平成九年度予算案におきまして、特に取り組んだところというお尋ねでございます。
御案内のように、科学技術基本計画ということで、これは国公私の大学、それから国立の試験研究機関をすべて含んだ計画であるわけでございますが、その中におきまして、私立大学におきまし
ても学術研究の振興ということについて大きな役割を期待いたしたいという観点から、私どもといたしまして研究基盤の強化ということで、最先端の研究開発プロジェクトに対する支援を行うハイテク・リサーチ・センター整備事業、これは今年度もあったわけでございますが、これを引き続き実施するということが一点。それから、新規の事柄でございますけれども、新たに私立大学におきます中核的な研究拠点に対する総合的な支援を行うということで、学術フロンティア推進事業というものを創設することといたしまして、合わせまして七十四億円余りを計上しているところでございます。
また、これ以外に私立学校の施設につきまして、この近代化、高度化を推進するということのために、新たに老朽校舎の建てかえ整備事業に対する利子補給制度というものを創設することにいたしまして、そのための予算といたしまして十八億円を計上している。これが来年度に向けての私立大学関係の新しい事柄であろうかということでございます。
○新藤分科員 大変厳しい予算の中でいろいろと御苦労いただいて、また、私も当時私学助成担当の主査としていろいろ大蔵省さんにもお伺いいたしましたから、この御努力は評価したいというふうに思っております。
そこで、ちょっとこれは答えづらいのかもしれませんが、文部省の教育振興をしていくということと、それから今盛んに言われている財政再建を行う、これをどうリンクさせるかということを一つお尋ねしたいと思っております。
文部省の予算、九年度五兆八千百九十八億円余り、これは経常部門が全体の九一・九%ですよね。うち人件費だけで七八%、四兆五千億使われているということになる。橋本総理は、財政再建には聖域を設けずとおっしゃっているわけなのですけれども、質を落とさずに、そしてやらなければいけないことは数限りなく要望が出てくる。そういう中で、今後の財政再建に合わせて、財政構造改革なのかもしれませんが、どこを削っていったらいいのか。それは、私そういうことを考えていく必要はあるのじゃないか。私も含めて、あれもっけろ、これもっけろと言いますけれども、あわせて、やはり入りをはかりて出るを制すじゃないけれども、この原則にのっとったところのどこを削る必要があるんだ、また、考え方なんだということについて、よろしければ大臣。
○小杉国務大臣 まず申し上げたいのは、教育という仕事は人間がやることでありますので、まさに教育は人なりということで、人件費の占める割合というのはもう宿命的に大きくならざるを得ないのですね。これを削れということは、もう先生を全部解雇しろ、こういうことにもなるわけでございまして、そういうことで、しかも今の義務教育費国庫負担金というのが五兆八千億円の半分にもなるわけです。
これは、戦後の憲法で、教育は国の義務であり、またひとしく国民はそれを受ける権利がある、こういうことで二分の一国庫負担金制度というのができたわけですね。それで東京とか鹿児島、沖縄、北海道、そういう地域差なしに一定の財源的な保障というものが行われた。そのおかげで、この五十年間に日本の教育の機会均等は飛躍的に増したし、また教育水準が世界の中でも有数の水準になったという原動力になったと思います。
そういう根幹をなす部分でありまして、予算委員会でもこの辺は随分議論が出たのですけれども、じゃ、これを全部地方交付税対象にしてしまえ、こういう議論もあります。しかし、そうなった場合には、当然これは財政事情によって、財政の苦しいところはどんどん切り詰められていく。それでよければ、私どもはそれで結構ですと言うわけです。しかし、やはり戦後の我々の基礎を築いた教育、こういうものを、特に義務教育についてはこの根幹は維持していくのが国策上重要ではないか、そういうことで、しかしだからといって我々は、教育がすべて聖域であるなんということは思っておりません。今の大変危機的な状況にある財政状況の中で、この義務教育費国庫負担金の中身についてもやはり改めるところは改めるということで、旅費であるとか恩給費であるとか、いろいろな面で逐次改善を続けてきたところでございます。
今後も私たちは、聖域は設けない、こういう政府の方針に基づいて、どこを削ったらいいのか、これはもうとにかく削るところはないくらいみんな必要不可欠な予算でありますけれども、そういう中で、あえてやはりそういう姿勢で今臨んでいるところであります。
○雨宮政府委員 文部省全体の予算の組み立てにつきましては大臣御答弁申し上げたとおりでございますが、私学助成に関して申し上げますと、先ほど申し上げたような種々の新規事項を含めました私学助成の拡充策を含めまして、私学助成関係の予算の伸びは対前年度で四・四%ということでございます。文部省全体の予算の伸びが一・一%ということでございますので、文部省全体の予算のやりくりの中で、私学助成につきましてはかなりの程度優先度を上げて措置をいたしたというつもりでございます。
○新藤分科員 大分時間も少なくなってまいりましたので、本当にさわりだけの質問になってしまって恐縮なのですけれども、そこで私は一つ、提案をというか考えを述べさせていただきたいと思うのです。
今大臣のお話にもありましたように、先ほどは使途別に見て経常部門、人件費が突出するんだ、これは当然、仕方がないのですね。今度は主要事項別に見ると、今お話しの義務教育国庫負担金、これが半分以上、三兆、五一・九%ですね。それであとは国立学校の特別会計に一兆五千億で二六%。だから、残り一兆二千億のうちの私学助成が大体六%ぐらい、私はこんなふうに思っているのです。ここの部分に財政再建だよとぶつけていけば、それはまた、私学にも聖域なしなんだと思うから……。
これは国全体に言えるのですけれども、むだな部分というのは、恐らく、要らないなんというところはほとんどないはずなんですよね、みんなきっちり必然性があってやってきているものなんだから。しかし、じゃ、めり張りをつけるためにどこを削るんだというところで今苦労されているわけなのです。
私は、もう一つ、これからの考え方は、直接、いただいた税金をまた割り振りを考える、その中で国のいろいろな施策、いわば私はサービスと呼んでいますけれども、そういう公的なサービスが行われる中で、何も徴税だけに頼ることはないではないか。いろいろな民間の活力という、自分でこれを手伝いたいよという人は、国や公的なものを通さなくても、自分たちでやりとりをする中で活動できないかしら。要するに、民間活力というのはそこだと思うのです。それを教育分野にでも少し工夫してみたらどうかな、こういうふうに思っております。
要するに、税制面だとか融資面だとか、そういう施策で少し工夫をして民間の資金が入りやすくするような、それによって、今まで公が負担をしていた、公というよりも文部省が負担をしていた予算を振りかえることができれば、また別の展開が図られていくのではないか。これは何も教育だけに限らずに、すべてのいろいろな、福祉にしても医療にしても私は提案させてもらおうと、もちろんその最たるものが行政改革ですからと思っております。
そこで、まず要望が出ていることでなかなか取り上げられないことで、受託研究に対する課税問題ですね。これは要望が出ているのですけれども、今年度も認められなかったわけですよね。この辺について、まずはこういうことからじゃないのかなという気が私はしているのですけれども、文部省の方でのお考えと、それから、わざわざきょうはその観点で、分科会の担当外で大蔵省の方にも聞きたいということでお呼びをいたしておりますけれども、そこのあたり、ちょっと聞かせてもらいたいと思います。
○雨宮政府委員 今御指摘の、私立大学が外部からの委託を受けて行う場合の受託研究の扱いでございます。
これにつきましては、大学の社会に対する貢献としてだけでなくて、大学自身の活動を活性化する上でも有意義でございますし、また公共性も高いということから、文部省といたしましては、かねてから私学団体からも要望がございますので、これらを踏まえまして、受託研究の非課税化を税制当局にお願いしてきたところでございます。
ただ、平成九年度の税制改正の検討におきましては、医療法人とかあるいは株式会社等が行う場合につきましては課税されているということで、これとの均衡を図る必要があるのではないかということ、それから、学校法人につきましては御案内のように各種の税制上の優遇措置が既に行われているというようなことなどから、受託研究の非課税化は見送られたという経緯がございます。
他方で、受託研究課税の執行面の問題につきましては、税務当局と私学団体との間で種々検討がなされているところでございまして、文部省といたしましては、その状況も踏まえながら今後の対応について検討してまいりたい、かように考えておるところでございます。
○伏見説明員 今文部省の方から既に御説明をいただきましたが、十分御案内のことと思いますが、現行税法上の考え方を簡単に御説明させていただきたいと思います。
現行の法人税法上でございますが、私学等学校法人でございますが、税法上は公益法人等という分類になってございます。これは、その活動が公益的な活動を目的としたものであるということで、営利活動を主として行います一般法人とは異なる性格を有しております。それに応じた課税関係を、課税のカテゴリーをつくっているわけでございます。
十分御案内と思いますが、具体的に申し上げますと、一定の事業、他の民間営利法人等も行うような特定の事業を行いました際には課税関係が生じる。これも所得でございますので、単に収入全体に対してもちろん課税するというわけではございませんで、収入から経費を引きました残り、プラスがあれば課税関係が生じる。
それから、特に学校法人の特徴でございますけれども、そうした収益事業部門から公益事業部門、本来の業務、そこへ支出をいたした場合、これは税法上寄附金ということになりますが、その損金の算入限度額でございますけれども、一般の社団、財団の場合には所得金額の二割ということになりますが、学校法人につきましては所得金額の五〇%と年二百万円のいずれか多い金額、ここまでがいわば損金として認められるということになってございます。その上でもさらにいわば所得が残ったという場合に、この税率も、一般の法人が三七・五%の基本税率でございますが、それを二七%の税率で課税をさせていただいているというところでございます。
具体的な非課税の要望、これは当方としても承知をしているところでございますが、今文部省の方からもお話がございましたように、民間の例えば財団法人である研究所とか、あるいは純粋な民間企業であっても、特定のいわば研究を受託をしましてそれが事業活動の一端になっているというようなケースもございますものですから、そことの関係の整理をどうするかといったことがありまして、なかなか難しい問題があるのだろうと思っております。
以上でございます。
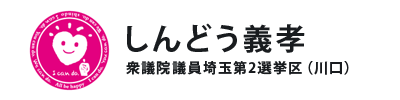


 2月4、5日にドイツのベルリンで開催される「第9回日独フォーラム」に、日本側委員として新藤議員が出席した。
2月4、5日にドイツのベルリンで開催される「第9回日独フォーラム」に、日本側委員として新藤議員が出席した。